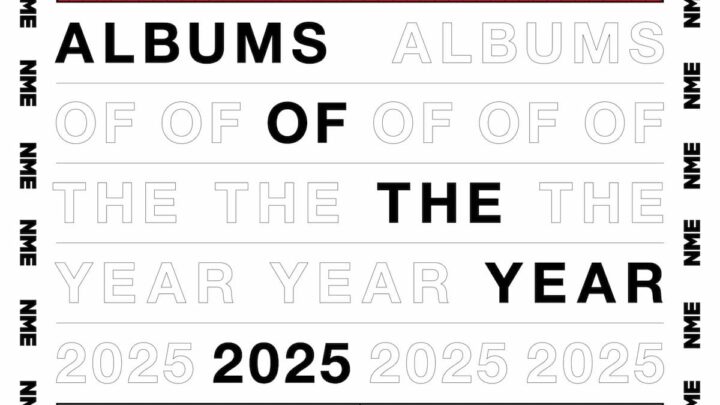20位 スレイヴス『アクツ・オブ・フィアー・アンド・ラヴ』

ケント州出身の男自慢、スレイヴスとメロディーはあまり結びつかないのかもしれない。ましてや、恐れや愛などなおさらだろう。しかしながら、スレイヴスは通算3作目となるこのフル・アルバムで、自分たちのデッキをいくらかシャッフルしている。これまでにないほどにメロディを前面に押し出し、フロントマンでドラマーのアイザック・ホールマンは吠えるよりもむしろ(なんと!)歌っているし、スレイヴスが単なる過剰なまでにフルスロットルな激しいパンク・バンドではないことをこのアルバムは証明している。それどころか、予想外にもこのアルバムは彼らをアリーナのステージへと押し上げることとなり、先月のアレクサンドラ・パレス公演では、彼らの怒りに満ちた楽曲に多くのオーディエンスが支持していることが裏付けられている。アルバムのハイライトになっている“Bugs”で「誤った情報」を植えつけられた「新たな失望世代」だと宣言するスレイヴスは、シーンに欠かせない声の一つとなった。
19位 トラヴィス・スコット『アストロワールド』

『アストロワールド』ほどの清々しさのある楽しいアルバムをリリースしたら、自分の公演をテーマパークみたいなセットにしても許されるんだよね? 驚異的な1年を過ごしているトラヴィス・スコットのジェットコースターのセットは目下、北米中のオーディエンスを夢中にさせている。トラヴィス・スコットは今年、レディング&リーズ・フェスティバルの共同ヘッドライナーを務めているほか、カイリー・ジェンナーとの間に娘のストーミ・ウェブスターも生まれている。フランク・オーシャンやテーム・インパラとのコラボから、“Stargazing”のようなサイケデリックな楽曲に至るまで、『アストロワールド』の成功は長らく記憶に刻まれることだろう。『アストロワールド』は新しいものが生まれ続けるアルバムなのだ。ベルトをしっかり締めて。この先はかなり揺れるから。
18位 ローリング・ブラックアウツ・コースタル・フィーヴァー『ホープ・ダウンズ』
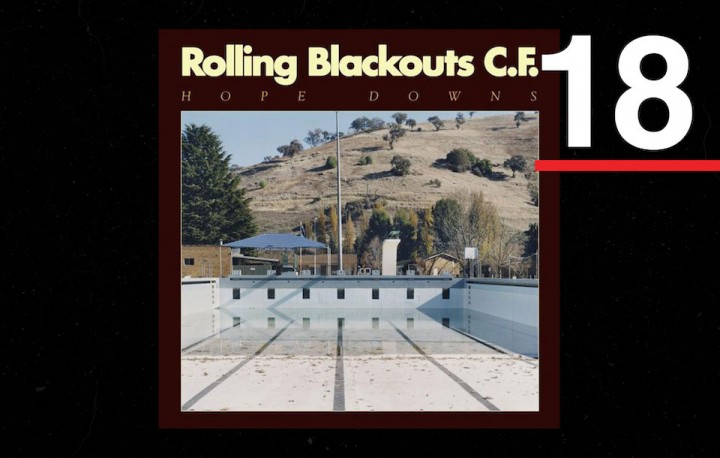
ザ・ウォー・オン・ドラッグスがついにオーストラリアにやってきた……ローリング・ブラックアウツ・コースタル・フィーヴァーのデビュー・アルバムが鳴らすのはそういうサウンドだ。アダム・グランデュシエルやカート・ヴァイルが先陣を切ってきたスペース・グランジに、ゴー・ビトウィーンズが焼きついたようなキャッチーなサウンドが魅力の『ホープ・ダウンズ』は、レモンヘッズの昔のアルバムを積んだトラックのブレーキが故障し、自由奔放に楽しんでいるような1枚だ。最高だよ。“Talking Straight”や“Mainland”、“Sister’s Jeans”……それぞれの楽曲が他よりも目立ちたいと躍起になっているのだが、すべての楽曲がそれに成功している。そう来なくっちゃね、ブラックアウツ。
17位 パーケイ・コーツ『ワイド・アウェイク!』
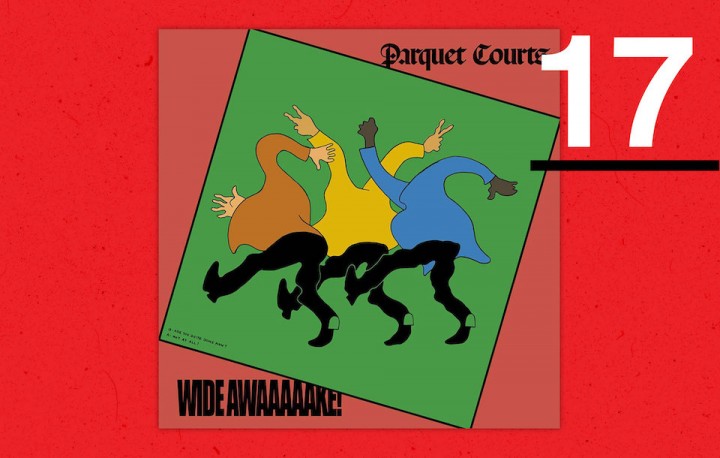
パーケイ・コーツによる通算6作目は、スペース・フォークにヒッピー・ポップ、ニューウェーヴ、ファンク、ダブ・オペラ、リオのサンバ、ガレージロック、そしてザ・ストロークスのようなシャウトを多分に入れてブレンドさせて作られた、多様なオルタナティヴ・ロック・アルバムであるにもかかわらず、彼ら史上最も包括的で取っ付きやすいアルバムになっている。MC5からペイヴメント、トーキング・ヘッズ、スクイーズ、ニュートラル・ミルク・ホテルまで、非の打ちどころのないオルタナティヴ・ロックのアクトたちが次々と入れ替わるような本作も、 パーケイ・コーツの作品であることには疑いなく、それは突飛で触発されたようなメロディの癖を聴けば明白だ。アメリカのバンドが“Total Football”という楽曲でイギリス的な意味のフットボールについて歌っているなんてね? まったく。やられたよ。
16位 ブロックハンプトン『イリデセンス』

通算4作目となるこのアルバムがリリースされる前、野性味に満ちた乱射銃のようなテキサスのオルタナ・ボーイバンドから、性的虐待疑惑が持ち上がった創設メンバーのアミアー・ヴァンが追放されている。それでもこのアルバムの核になっているのはポジティヴな側面(当初のワーキング・タイトルはボツになったことにも納得がいく『ザ・ベスト・イヤー・オブ・アワ・ライヴス』だったという)で、世界規模での成功やそこまでの長い道のりを祝福しながら、自らをビッグにした最初の要因である、正直さもきちんと保っている。音楽面について言えば、『イリデセンス』はつんざくようなサイレンから暴力的なバス・ドラム、擦り剥いたようなヴォーカルの上を飛び跳ねながら、デリケートに運ばれてきた歌詞がそれを弱める役割を担っている。
15位 キッズ・シー・ゴースト『キッズ・シー・ゴースト』
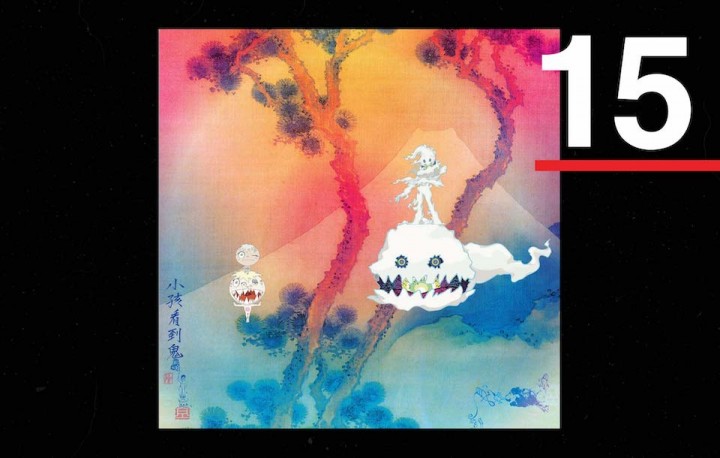
異論は認めるが、ジェイ・Zとの『ウォッチ・ザ・スローン』以来、カニエ・ウェスト史上最高のタッグかもしれない。『キッズ・シー・ゴースト』は多作な41歳のカニエが長年のコラボレーターであるキッド・カディと手を組み、多くの反響や傷つきやすさに焦点を当て、それを凝縮させたようなアルバムだ。「俺はもう痛みを感じない/いいかいベイビー、俺は自由を感じているんだ」とカニエ・ウェストはふさわしいタイトルが付けられた“Freeee (Ghost Town, Pt. 2)”で活き活きと歌っている(そして、『スクープ!』付きだ)。そして、この臆することなく自由を宣言する身震いするような姿勢こそが、『キッズ・シー・ゴースト』を2018年の最も聴くべきアルバムの1枚に仕立て上げている。『NME』は『キッズ・シー・ゴースト』について、「絶妙な加減で幽霊的で超常現象的なサウンドを鳴らす本作は、もう一つの世界の入り口を見せてくれる」と評している。そしてそこは、一度行けばもう一度行きたくなってしまうような場所なのだ。
14位 スネイル・メイル『ラッシュ』

矛盾していて、傲慢で、脆くて、威圧的。ボルティモア出身のティーンエイジャーであるリンジー・ジョーダンは、大人になっていく過程で経験する普遍的な体験をこの突風のようなインディー・ロックのデビュー・アルバムに閉じ込めている。グランジ風のヴォーカルを力強く歌うギグよりも静かでメランコリックなこのアルバムは、まさに「ラッシュ=美しい」というタイトルに相応しい。フックも儚さも愛嬌も、不均衡なギターのメロディーも、美しいとしか言いようがない。カントリー(フィンガーピックで披露される短い“Let’s Find An Out”)に向かっても、広大なオルタナティヴ・ロック(涙を誘う思慮深い“Deep Sea”)に舵を切っても、彼女がユニークな声を持った若手ミュージシャンであることには変わりなく、これからの成長過程に待ち受ける道のりに、きっとファンもついていくのだろう。
13位 ドリーム・ワイフ『ドリーム・ワイフ』

2000年代の初頭に網タイツとグリッターで彩られたヤー・ヤー・ヤーズがマンハッタンに登場して以来、パンク・ロックがこんなにも純粋に楽しかったことはない。オープニングを飾る“Let’s Make Out”の黄色い声から、アルバムを締め括る煮詰められたようないみじくも卑猥な“FUU”のコードや金切り声まで、3人の魔法使いである親友たちはスタジオで羽目を外しながら、この『ドリーム・ワイフ』で思うがままに反抗しているのだ。
12位 ブラッド・オレンジ『ネグロ・スワン』

例の如くイノヴェーションを続けるデヴ・ハインズによる、ブラッド・オレンジとしての通算4作目『ネグロ・スワン』は、私たちに彼の最も率直で人間味のある部分を覗かせてくれる。全16曲の中には著名なゲストたち(パフ・ダディにエイサップ・ロッキー、スティーヴ・レイシー)が参加し、自伝的な歌詞(「16歳の少年/混乱している。自分が他人と違うことを知っていて、身を預けたがっている/放課後に不意に殴られて倒れる/ノックダウンさ」とデヴ・ハインズは1曲目の“Orlando”で恐ろしい記憶を振り返っている)が歌われているし、『NME』が満点の5つ星をつけたレヴューで呼ぶところの「音楽制作における断片的なアプローチ」が取り入れられ、「いいとこ取りのジャズ・ピアノ、無秩序なギターやコラボレーターを用いて……何層にも積み重なった栄養満点のメランコリーなR&B・ポップ」として実を結んでいる。驚異的で、自白的な1枚だ。
11位 ロビン『ハニー』

3部作となった『ボディー・トーク』のリリースから8年の月日が経ち、待ち望まれていたロビンの復帰が発表された時には、世界中がハチミツを求めるくまのプーさんのようにお腹を空かせて今か今かと待っていた。シーンから離れていた期間に、スウェーデンのポップ・アイコンは2度の大きな喪失を立て続けに経験している。長年のボーイフレンドと離別し(彼とは後に復縁している)、バンドメイトでコラボレーターのクリスチャン・フォークを膵臓癌で失った。ロビンが悲しみをガラスに変えて作り上げた『ハニー』は思いがけず高揚してしまう、これまでの不在も腑に落ちてしまう、あたたかい傑作だ。これまでにも感情に完璧に飛び込む稀有な才能を発揮してきたロビンだが、とことん胸を締め付けられる本作も、最後には希望が一面に広がっている。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.