40位 ホールジー『マニック』
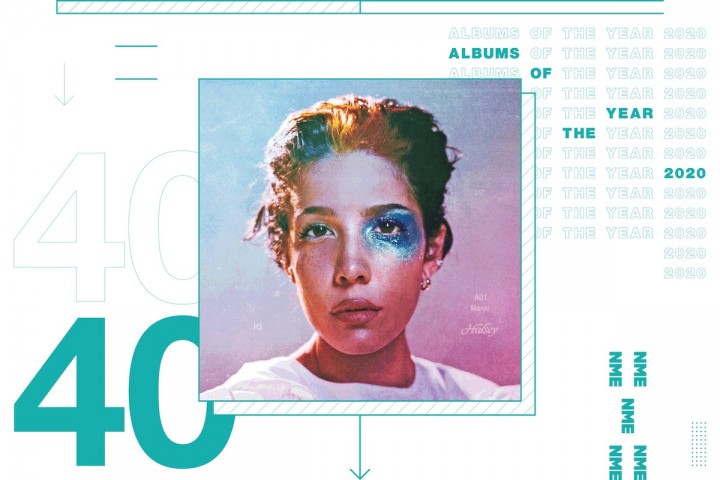
一言で言い表せば:これまでの彼女の作品では一番理解しやすいアルバムであり、オルタナティヴ・ポップのスターは相手の痛いところを容赦なく攻めている。
2枚の空想的なコンセプト・アルバムを経たのち、ホールジーは架空の世界を捨て去り、より魂をむき出しにした作品を作った。カントリー、インダストリアル、エモに影響されたアンセムが目白押しの本作は、真にポップな態度で、悲嘆と強烈な自信の間を揺れ動く。もろさの中の強さを祝福する『マニック』は本当に傑作だ。
鍵となる楽曲:“You Should Be Sad”
『NME』のレヴュー:「ホールジーは危ういのと同じくらいにスリリングなレコードを作り上げた。これまでの彼女の最高傑作だ」
39位 ドミニク・ファイク『ワット・クッド・ポッシブリー・ゴー・ロング』

一言で言い表せば:音楽的に器用で要注目のアーティストがハイプに応えてみせた。
2018年に何百万ドルものレコード契約を結んだフロリダ出身の次世代スター候補は、実際に現実の場でも「失敗するはずないよね?(What Could Possibly Go Wrong?)」と問いかけていたのかもしれない。今聞くと2020年の新年の抱負のサブタイトルのようにも思える縁起の悪いタイトルだが、ありがたいことにドミニク・ファイクのデビュー作の場合、何も失敗しなかった。確かな腕のギターを操り、ジャンルやスタイル、ヴォーカル・ピッチを縦横無尽に変えていくドミニク・ファイクは、アイディアと野心に溢れる、将来有望で快活なアルバムを作り上げ、彼が望めばここからどこへでも進んでいけるだろうことを証明してみせた。
鍵となる楽曲:“Cancel Me”
『NME』のレヴュー:「14曲の鮮烈で切れ味鋭い小品から成る本作は、なかには1分くらいしかない曲もある。これは、山の頂上に立つソングライターが胸を張って、大手を振るっているサウンドだ」
38位 ヤングブラッド『ウィアード!』

一言で言い表せば:スタジアムを見据えた楽観主義のエモ。
ヤングブラッドは悩めるアウトサイダーのアンセムで名を上げた。しかし、彼の言葉ひとつひとつに耳を傾ける世界中のファンがついたおかげで、その怒りは希望へと変わり、大人に成長した本作では自分の選択を信じることの意味を歌っている。素晴らしいアルバム『ウィアード!』は人を鼓舞し、エキサイティングでパンクな楽しさに満ちている。
鍵となる楽曲:“the freak show”
『NME』のレヴュー:『ウィアード!』でのヤングブラッドは、これまで以上にデンジャラスな姿で、人を鼓舞し、生き生きとしていて、自分が最も重要なロック・スターのひとりであることを証明している。
37位 サンダーキャット『イット・イズ・ホワット・イット・イズ』

一言で言い表せば:活動が活発なベーシストは、自身のキャリア史上最も陰鬱な気分の作品となった本作で、故マック・ミラーにトリビュートを捧げている。
本名をステファン・ブルーナーというサンダーキャットは2018年、友人のラッパーであるマック・ミラーの悲惨な死に動揺していた(「それじゃさよなら、俺は君のためにやっていくつもりだよ」と彼は感動的な“Fair Chance”で歌っている)。通算4作目となる本作で、彼は普段の元気いっぱいなサンダーキャットをいくぶん控えめにしている。だが、ジャズの影響を受けた遊び心は健在で、素晴らしい曲名を持った“Dragonball Durag”での「俺は猫の毛まみれになっているかもしれないけど、今でもいい匂いがするぜ」の一節は、2020年の最優秀歌詞の有力候補だ。
鍵となる楽曲:“Black Qualls”
『NME』のレヴュー:「サンダーキャットはアルバム全体を通して生や死、癒しについて深い思慮を巡らしながらも、必要なときには相変わらずリラックスすることができている」
36位 エラ・マイナス『アクツ・オブ・レベリオン』

一言で言い表せば:ボコタ生まれブルックリン拠点のアナログ魔術師によるDIYテクノ・パンク。
シンセサイザーを操るエラ・マイナスのデビュー・アルバムの原動力となったのは、2016年の大統領選でのドナルド・トランプ勝利を背景とした「暗い時代のための明るい音楽」というスローガンだった。確かに今年の選挙でトランプは葬り去られたが、より良い世界に向けた私たちの戦いが始まるのはまさしくこれからだ。このアルバムでは、やつれて傷ついた姿で登場したエラ・マイナスだけれど、彼女は不屈の精神で、連中があなたを打ちのめすことを決して許さない。
鍵となる楽曲:“megapunk”
『NME』のレヴュー:「この革新的なデビュー・アルバムは、緊迫感のあるアンセムと瞑想のひと時を融合して、変化のはずみのサウンドトラックになっている」
35位 サッカー・マミー『カラー・セオリー』
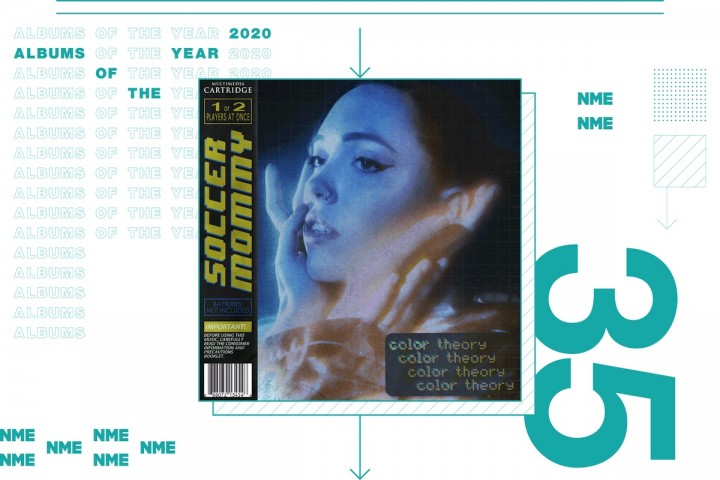
一言で言い表せば:力強い感情をメロディアスな1990年代ロックの中に書き留めた。
本名をソフィー・アリソンというサッカー・マミーの屈指の創造力が遺憾なく発揮された『カラー・セオリー』は、3色にテーマ分けされた感情のカタルシスを通して、鬱の問題を語っていく。すなわち、MTVに流れるエモのような憂鬱の青色、あてどもないローファイ・サウンドによる病の黄色、オルタナティヴ・ポップのカプセルに包まれた喪失の灰色だ。以上の3色が素晴らしい統一感で一体となっている。本作は最も感動的な意味を持ったコンセプト・アルバムなのだ。
鍵となる楽曲:“circle the drain”
『NME』のレヴュー:「アリソンは歌詞で鮮やかな絵を描く名人だ。耳に残るメロディーとあたたかい編曲を、ショッキングな言葉を融合して、感情のパンチを食らわせる」
34位 ウィズキッド『メイド・イン・ラゴス』

一言で言い表せば:サックスの音が彩る官能的な移住の旅。
『メイド・イン・ラゴス』でウィズキッドは、セクシーな大人の仲間たちのためにレコードを作った。自身の故郷に敬意を払ったタイトルを冠し、ジャズから由緒あるアフロビートに至るまで豊かで落ち着きのあるプロダクションが施された本作には、バーナ・ボーイ、スケプタ、H.E.R.、テイ・イヴァル、テムス、ダミアン・マーリーといった多くの客演が参加している。大きく膨らんでいくプロジェクトの幅広さとインスピレーションで、彼はナイジェリアの首都ラゴスから遥か遠くの地まで進出したのだ。
鍵となる楽曲:“Blessed” feat. Damian Marley
『NME』のレヴュー:「このアルバムのプロダクションはおおよそヨルバ、アフロ・ラテン、アフロビートのパーカッションに集中していて、里帰りらしい空気感を作り出している」
33位 デクラン・マッケンナ『ゼロズ』

一言で言い表せば:インディー界の天才少年が厭世的な1970年代回帰の吟遊詩人として再出発している。
2017年のファンのお気に入り曲“What Do You Think About The Car?”での若者らしい野心をバックミラーで尻目に見ながら、最新作『ゼロズ』に至って、デクラン・マッケンナは破壊と生存のディストピアの空想世界を進み始めた。気の滅入る実存主義を、壮大で芝居じみたスペースロックのサウンドの上に投影することで、彼は変化途中のアーティストとしての印象的な自画像を描いてみせたのだ。
鍵となる楽曲:“The Key To Life On Earth”
『NME』のレヴュー:「デクラン・マッケンナのスペース・シャトルに乗り込んで、踊ることとディープになることが等しく奨励される場所へ連れて行ってもらおうじゃないか」
32位 マイリー・サイラス『プラスティック・ハーツ』
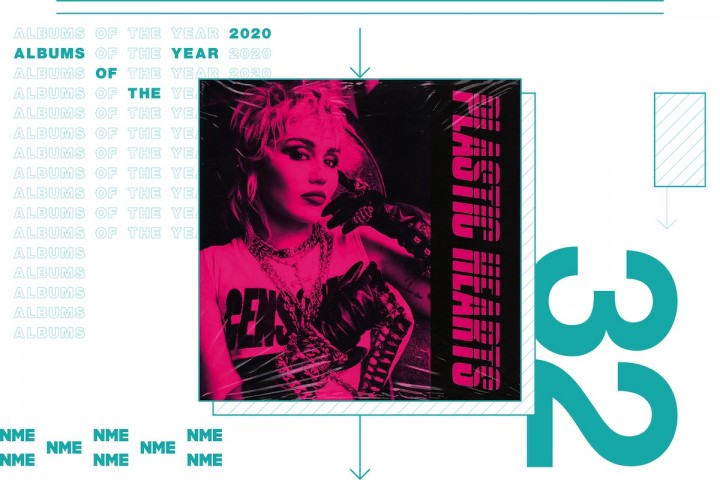
一言で言い表せば:ポップ界の気骨あるスターが遂に完全にモッシュピットに飛び込んだ。
マイリー・サイラスは長年にわたって、ブロンディ、フリートウッド・マック、メタリカといった敬服すべきロックの名作をカヴァーしてきたし、さらに素晴らしいのは、それらをしっかり自分のモノにしていたことだった。彼女のパワフルでしゃがれたロックンロールな歌声はポップ界では公然の秘密だったが、その声自体が彼女自身の作品で披露されることは今までなかった。しかし、今回の『プラスティック・ハーツ』では遂に、気取った1980年代のシンセ・ポップやグラム・ロック、そしてアヴリル・ラヴィーンやアシュリー・シンプソンのような2000年代初期のオルタナティヴ・ポップが一緒に繋ぎ合わされ、勝手な期待はすっかり全て実現することになった。すごい!
鍵となる楽曲:“Midnight Sky”
『NME』のレヴュー:「『プラスティック・ハーツ』ではポップ・スターからロック・スターへの変貌が大急ぎで進んでいくさまを見ることができる。そして、マイリー・サイラスがスロットルを全開にするとき、それはまさしく突風だ」
31位 エンプレス・オブ『アイム・ユア・エンプレス・オブ』

一言で言い表せば:ロサンゼルスの実験的アーティストがこれまでで一番良いアルバムで悲嘆を踊って吹き飛ばす。
ロサンゼルスを拠点とするエンプレス・オブは常にアヴァンギャルドなものに耳の肥えたアーティストだった。2015年のファースト・アルバム『ミー』、2018年のセカンド・アルバム『アス』は細部までこだわり抜いた内容で、骨の折れる制作作業に数年以上を要している。一方、本作『アイム・ユア・エンプレス・オブ』はまったく対照的に、隔離期間の数か月であふれ出てきた作品だ。置かれた状況に動かされる形で制作された彼女の最新作は、シカゴの自宅、ホンジュラス系アメリカ人という出自、悲嘆に暮れたあとで徐々に見えてくる自分自身の再発見といった事柄の影響を受けている。言わば即時的に解き放たれた作品なのだ。
鍵となる楽曲:“Love is a Drug”
『NME』のレヴュー:「エンプレス・オブは、心の悲嘆を、見事な30分間のクラブ向きのエレクトロに変換してみせた。『アイム・ユア・エンプレス・オブ』は息をのむ瞬間に事欠かない」
Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.















