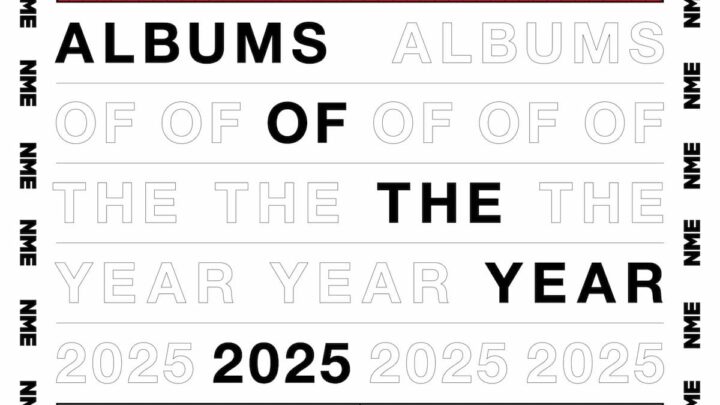10位 ザ・チェインスモーカーズ(8/18 MARINE STAGE)

アラン・ウォーカーとゼッドによってすっかりあたためられたマリン・ステージで、今年の最終日のヘッドライナーを務めたのがザ・チェインスモーカーズだった。彼らがロック/エモの方向へと進み始めていることは昨年にリリースされたアルバム『シック・ボーイ』でも明らかだったが、ドリュー・タガートが時にはDJプレイもこなしながらフロントに立ち、アレックス・ポールとサポート・ドラマーとして帯同しているマット・マグワイアが音楽面を支えるという構図が徹底されていたこの日のステージは、ザ・チェインスモーカーズの現在の姿勢を体現したものだった。それと同時に楽曲こそがすべてを語る。その潔さを感じたステージだった。“Paris”も、“Don’t Let Me Down”も、そして挙げずにはいられない“Closer”も、彼らの存在を超えたヒット曲が次々と演奏されていく。最後は“Something Just Like This”だったが、曲の力を思い知らされるようなステージだった。
9位 チャーチズ(8/18 MOUNTAIN STAGE)
華やかなチュールワンピースに身を包んだローレン・メイベリーを中心に堂々と登場したグラスゴー出身のチャーチズだが、先日衣装の露出度に関する批判を受けたものの、「何を着るかだって、クリエイティビティを表現したり、メッセージを伝えるための一つの手段」と一蹴していたローレン。ドリーミーでいて、しかしパワフルなローレンのヴォーカルは、まさに華麗な衣装を身にまといながらも芯の強さを持つローレン自身そのものだった。そしてそれを支える骨太なシンセ・サウンドは、少し聴いただけでそのUK北部ならではの彼らの出自を体感することができた。「次のアルバムの制作期間に入る前に戻ってこられて嬉しい!」とMCを挟むローレン。今までに3枚のアルバムをリリースしているチャーチズ、5曲目には人気番組「テラスハウス」のオープニング曲として使われている“Graves”も披露しながら、1曲目の“Get Out”から締めの“Never Say Die”まで、デビューから着実に積み上げてきた抜群の安定感で魅せられたステージだった。
8位 マシン・ガン・ケリー(8/17 MOUNTAIN STAGE)

ヒップホップはグローバルな波の渦中の中心で、それぞれのアーティストが自分の立場を鮮明にしながら、ワールドワイドな世界に乗り出していく姿がある。けれど、その中でも模範回答を示してくれたようなステージだった。マシン・ガン・ケリーは2015年にリリースしたキッド・ロックとのロックなナンバー“Bad Mother Fucker”からこの日のステージをスタートさせると、コブラのオブジェが付けられたマイクを片手にラップしながら、時にはギターを掻き鳴らし、自身が伝記映画でトミー・リー役を演じたモトリー・クルーの“Shout at the Devil”のカヴァーなんかも披露しながら、同曲ではドラムまで叩いてみせる。白人としてのヒップホップは何なのか、それを過剰なまでに見せつけていくスタイルは挑発的だが、それが言い訳のない形でプレゼンテーションされていく。革新の途中にあるマシン・ガン・ケリーを観られたのがなによりも嬉しかった。
7位 ゼッド(8/18 MARINE STAGE)

高性能なアーティストだなとしみじみ思う。ダンス・ミュージックとポップ・ミュージックのクロスオーヴァーが急速に進むなかで正解を出し続けた人がゼッドだった。当然、この日も正解を出し続ける。ショーン・メンデスの“Lost In Japan”のリミックスを初めとした他アーティストのヒット曲や、EDMの定番のバンガーももちろん投下されるのだが、どこを切り取ってもアンセムとなる彼自身の持つレパートリーは、やはり他とは一線を画すものだ。特筆すべきは“Stay”や“The Middle”、“Stay The Night”と代表曲が立て続けに披露された後半のステージで、キャリアの初期を決定付けた“Clarity”で締めくくられる頃には、スタジアムが満員となったオーディエンスの携帯電話の明かりとシンガロングに包まれ、このポップ・ミュージックの優等生を祝福するような圧巻の光景が広がることとなった。
6位 ブリング・ミー・ザ・ホライズン(8/17 MOUNTAIN STAGE)

前回予定されていた来日公演がキャンセルとなり、実に5年ぶりの日本でのライヴとなったブリング・ミー・ザ・ホライズンだが、フロアに満ちた飢餓感とも言える熱気が彼らがどれだけ待ち侘びられていたかを物語っていた。“MANTRA”からスタートしたこの日のセットリストは、可能性を恐れずに新たな領域を探求し、バンドが大きく飛躍を遂げることとなった前作『ザッツ・ザ・スピリット』と最新作『アモ』の楽曲を中心としたもの。途中、オリヴァー・サイクスが「BABYMETALを楽しみにしている人は?」と次のアクトに言及する一幕もありながら、最後は前作『ザッツ・ザ・スピリット』から“Follow You”、“Drown”、“Throne”のアンセム3連発で締めくくられたのだが、彼らが直近の2作品で成し遂げた功績は偉大なもので、きっとまだライヴ・アクトとしてもさらに上のステージへ向かう余力を残しているはずだ。
5位 ブロックハンプトン(8/18 MOUNTAIN STAGE)

「インターネット発のアメリカン・ボーイバンド」を自称している彼らだが、そのライヴを観るまではこれは彼らなりの冗談だろうと思っていた。しかし、ついに初来日で目撃することのできた彼らはまさにボーイバンドだったのだ。最新作の“I Been Born Again”で幕を開けたステージは、メンバーが1人、また1人と自分のパートで登場していく展開となったのだが、そのフレッシュさやキャッチーさはまさにアイドルを彷彿とさせるもので、これまでのヒップホップ・コレクティヴとは一味も二味も違う。全身シルバーのジャンプスーツに身を包んだメンバーたちがエネルギッシュにステージを交差して楽曲を披露していくのだが、とにかくその存在感がポップなのだ。最後に披露された“Boogie”ではモッシュピットまで生まれていたが、この曲のケヴィン・アブストラクトのヴァースにはこんな一節がある。「ワン・ダイレクション以来の最高のボーイバンド」、まさに彼らはそんな鮮烈な印象を残してステージを降りていった。
4位 フォールズ(8/17 SONIC STAGE)

最新作の“On the Luna”で幕を開けた瞬間、その出音のあまりの素晴らしさに至福のライヴになることを確信する。シーンの風潮などものともせず、2000年代のUKギター・バンドとして独自の進化を遂げてきたフォールズだが、その真価を堪能できるのが他でもないライヴだ。2曲目の“Mountain at My Gates”に入る頃には既にとんでもないことになっている。ドラム、ベースに加え、パーカッション、シンセ、2本のギターが絡むアンサンブルが見事に肉体化され、こちらの予想をはるかに凌駕していくサウンドが鳴る。最新作の楽曲を軸としながらも、“Olympic Airways”、“Spanish Sahara”といった往年の名曲も披露され、最後に投下されるのはもちろん“Two Steps, Twice”だ。レッド・ホット・チリ・ペッパーズの直前という時間帯もあり、決してお客さんの数は多くなかった。しかし、ギター・ミュージックの未来を描くこの完全無欠のアンサンブルはもっと多くの人に観てほしかった。
3位 フルーム(8/18 SONIC STAGE)

ステンシルでスプレーを吹き付け、「こんにちは。FLUMEです」という挨拶を描いた冒頭から、実にらしいと思ったが、まあすさまじいライヴだった。現在のシーンにおいて最も自由なDJ/プロデューサーと言っても過言ではないフルームだが、そのステージはさらに奔放なものだった。自身の楽曲をかけながら、ステージの上で鉢の植え替え作業をし、機材だって破壊するし、その後で清掃員を入れて掃き掃除までを行い、旋盤で火花まで散らしてみせる。それはまるで、ステージの上で音源をかけるだけの昨今のEDMシーンへのアイロニーのようで、その上で“Never Be Like You”や“Holding On”といった代表曲をプレゼンテーションしていく。それはポップ・ミュージックの在り方そのものに疑問を投げかけるようで、それがパフォーマンスとして成立するものとなっている。最後に披露されたディスクロージャーの“You & Me”のリミックスではゲスト・ヴォーカルと共にフロアへと降りたフルームだが、その姿はあまりに神々しかった。
2位 レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(8/17 MARINE STAGE)

フジロックの20周年でヘッドライナーを務めたレッチリが、サマーソニックの20周年でもヘッドライナーを務める。前日に行った大阪会場でのライヴから大幅にセットリストを変更して臨んだこの日、レッチリはそんな日本のオーディエンスの深い愛情に真正面から応えるステージを披露してくれた。“Can’t Stop”と“Scar Tissue”で幕を開け、“Dani California”も“Californication”も、“Around the World”も“By the Way”も披露されるという、まさに盤石だったセットリストもそうだし、何度も感謝を述べるフリーのMCも、“Under The Bridge”で自然発生的に全員が点けた携帯電話の明かりも、そのすべてが両者がこれまでに築き上げてきた深い関係性を象徴していた。アンコールでは“Dreams of a Samurai”を披露して見事にフジロックのリヴェンジも果たしてみせるなど、サマソニの20周年と日本のオーディエンスを目一杯に祝福してくれたレッチリだが、バック・スクリーンに日の丸が大きく映し出される最後の瞬間まで、スタジアムはバンドとファンの深い愛情に包まれ続けていた。
1位 ザ・1975(8/16 MARINE STAGE)

ロックも、ポップも、エモも、UKインディも、エレクトロも、テクノロジーも、政治も、文学も、ソーシャル・メディアも、ザ・1975はそのすべてを引き受け、あくまでロック・バンドとして現代のシーンに君臨している。“Give Yourself a Try”からスタートしたこの日、プレイステーションが描かれた衣装を着てステージに登場したマット・ヒーリーは2曲目の“TOOTIMETOOTIMETOOTIME”で早くも衣装を変え、ライドの『ノーホエア』のジャケットが描かれたTシャツがお目見えする。“Sincerity Is Scary”でお馴染みのウサギの耳を被り、その格好でタバコを吸ってみせる姿も、「ポップ」「危険さがない」「説得力のない歌詞」というメディアやファンからの批判と思われるメッセージが次々と投影される最後の“The Sound”の演出も、そのすべては「どこでもない場所」というメッセージに結実していて、あらゆるレッテルから逃れていく。もちろん初期の名曲“Chocolate”は今も色褪せることなくセットの中心的な役割を担っているのだが、マット・ヒーリー率いるザ・1975は「ポップ・バンド」と形容された時代などとっくに乗り越え、新時代のロックスターとして非の打ち所のない存在感を放っていた。最後にスクリーンに映し出された「ロックンロールは死んだ。ザ・1975に神をご加護を」のメッセージは最高に痛快だった。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.


_2563 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415lxbfrdVL._AC_SL1000_.jpg)