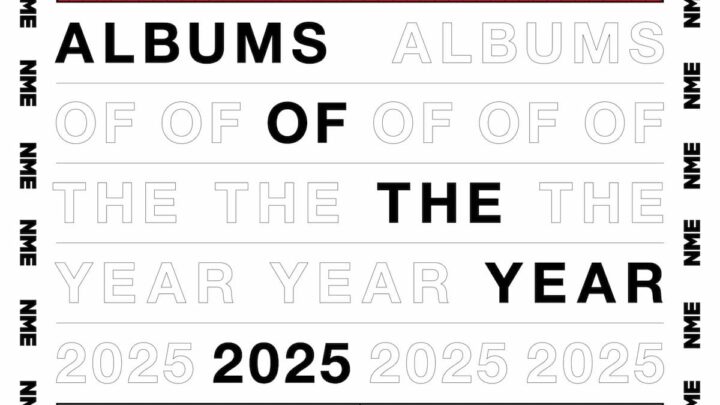10位 クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ『クリス』

自画像の大部分に落書きし、鼻高々なキャラクターへと変貌を遂げたクリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズによるセカンド・アルバム『クリス』は、デビュー・アルバムの『ぬくもり(シャルール・ユメンヌ)』にあった喚情的な優しさに紙やすりをかけたようなアルバムだ。力学を探求しながら、上位に君臨する性的に権限を与えられた女性が警鐘を鳴らす『クリス』は、前作よりもラフで、人間味を増している。彼女は本作で、ジミー・ジャムやテリー・ルイスらの影響を受けた奔放なポップ・ミュージックにアプローチし、ポエティックな歌詞では自らの欲望に真正面から向き合っている。ミュージカル風のテクニカラーが施された照明に照らされながら、徹底的な世界観の中で周囲を取り囲むダンサーたちと共に披露されるライヴが、年間を通して話題になっているのにも合点が行く。クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズは、現代が誇る最も重要で境界線を押し広げてくれるポップスターの一人である。
9位 ミツキ『ビー・ザ・カウボーイ』

これまでのキャリアを通じて4枚のアルバムをリリースしているミツキに奇妙にもスポットライトが当たったのは、前作『ピュバーティ2』の成功によるところが大きい。日本人とアメリカ人のハーフであるミツキは前作で、分厚いディストーションにまみれながら、のぼせるようなロマンスと孤独の両極を同居させ、アイデンティティや現状の安息、インディ・ロックの伝統に疑問を投げかけてみせた。『ビー・ザ・カウボーイ』は同じようなむず痒い場所から生まれながらも、そこにある陽気な要素をさらに結集させている。聴いてすぐに快活なディスコだと分かる“Nobody”には、弾むようなピアノとキーを飛ばしていくコーラスによって、荒涼とした孤独感が覆い隠されている。一方で“Lonesome Love”では、セイント・ヴィンセントの“Birth in Reverse”以来、ベストとも言える自己愛についての歌詞が歌われている。「あなたほど私におべっかを使う人はいないから/私ほど私とうまく交われる人なんていない」。ミツキは今、最高に冴えわたっている。
8位 カーディ・B『インヴェイジョン・オブ・プライバシー』

カーディ・Bの切れ味の鋭いデビュー・アルバム『インヴェイジョン・オブ・プライバシー』には、ウィットに富んだ自慢話が詰め込まれているが、何ら不思議なことではない。ブロンクス出身のラッパーはこの数年で無一文から大金持ちに出世した。“Get Up 10”で低所得者の妊婦や幼い子供を持つ女性を支援する「WIC(ウィメン・インファンツ・アンド・チルドレン)」に言及しているように、カーディ・Bは「WICから光をもたらしに」来た。『インヴェイジョン・オブ・プライバシー』は、今や世界一のラッパーになったカーディ・Bが頂点に登り詰めるまでの物語だ。器用に私たちを驚かせ続けてくれる彼女の次の動きを予測することは、もはや不可能に近い。とことん正直になったかと思えば、立て続けにジョークを飛ばしたりもする。「可愛い双子がビヨンセみたいでしょ」とカーディ・Bは“Money Bags”で自分の胸(他に何が双子と言えるだろう)についてラップしている。カーディ・Bが世界を制覇すると宣言したところで、それを疑うようであればその人はよっぽどだ。
7位 カリ・ウチス『アイソレーション』

カリ・ウチスの世界に「ジャンル」が入る余地はない。コロンビア系アメリカ人のカリ・ウチスによるデビュー・アルバムは、R&Bやディスコ、レトロなソウル、そして少しのボサノバの間を踊り回るように、最高のパーティーのプレイリストとして流したくなるようなサウンドを行き交っている。ジョルジャ・スミスやタイラー・ザ・クリエイターといった既に高い評価を得ているアーティストらも参加しているが、いつだって主役に躍り出るのはカリ・ウチスで、波打つようなサウンドに囁くようなファルセットを乗せる“Dead To Me”を聴けば、彼女が次のポップの王座に就く存在であることは明白だ。自身の弱みを打ち明けている時(跳ねるような“Feel Like A Fool’”)でさえ、彼女は自分の世界に君臨し続けている。
6位 シェイム『ソングス・オブ・プレイズ』

ファット・ホワイト・ファミリーの汚れた下着に住み着いたシラミのごとく、彼らから新たに産み落とされた、サウス・ロンドンの次世代を担うスジ肉のようなロックバンドだ。汗臭くて、コブだらけで、しばしばシャツを着ることにアレルギー反応を引き起こす。それがシェイムである。しかしながら、ギラついた“Dust On Trial”や“Tasteless”のような楽曲が、腐敗したロックの血糊のような“The Lick”らと見事に中和されるデビュー・アルバム『ソングス・オブ・プレイズ』のエアリーでアンフェタミンなインディ・ロックは、(わずかながらにも)リスナーたちに付け入る隙を与えてくれている。エコー&ザ・バニーメンがアイドルズのツアー・バスの下敷きになったところを想像してみてほしい。
5位 プシャ・T『デイトナ』

分かる人には分かる話だ。一連のおびただしいレコーディング・セッションのためにワイオミングに籠るというカニエ・ウェストの試みは、その第1弾となった後世に間違いなくヒップホップの名盤として名を残すであろう『デイトナ』で、見事に金鉱を掘り当ててみせた。カニエ・ウェストがプロデュースを手掛けた本作で、プシャ・Tはその21分間のすべてを薬物や銃、ドレイクへのディス(しかしマイルドに)についての魅惑的で好戦的なリリックのラップに費やしている。プシャ・T自身が以前インタヴューで語っていたことが、このアルバムを最もうまく表しているかもしれない。「『デイトナ』は今年1番のラップ・アルバムだよ。プロデュース面でも、リリックの面でも1番さ。その二つについてのコンテストはないんだろうけどね」。反論はしないよ、キング・プシャ。
4位 サンフラワー・ビーン『トゥエンティトゥー・イン・ブルー』

ジメジメとしたニューヨークの地下室から、そよ風が吹くようなローレル・キャニオンへ。サンフラワー・ビーンはフルスロットルでフリートウッド・マックの方向へと舵を切り、注目を集めようと奮闘する、多くのアンダーグラウンドなロック・バンドたちと同じように跳躍してみせた。“Crisis Fest”や“Puppet Strings”のようなグラマラスな楽曲を初め、“I Was A Fool”や“Twentytwo”、“Memoria”というドリーミーなフォーク・ロックまで『トゥエンティトゥー・イン・ブルー』には、一風変わった走り回るようなサイケデリック・ロック(“Human For”)も、ゴート人しかいないようなプロムでMDMAを盛られたようなサウンドの楽曲(“Only A Moment”)だって入っている。輝かしい進化だ。
3位 アイドルズ『ジョイ・アズ・アン・アクト・オブ・レジスタンス。』

アイドルズは何に対してレジスタンスを起こしているのだろう? ざっとこんな感じだろうか。毒された男性性に、EU離脱、サグ・カルチャー、外国人嫌悪……パンクによる新たな反抗の最前線に自らを送り込むこととなったこのセカンド・アルバムで、ジョー・タルボットは情熱や力、血気を目一杯に込めて現代社会に蔓延する病気に蹴りを入れている。“Colossus”や“Samaritans”でのブルータリズムから、“Cry To Me”というエモーショナルなハードコア、そして“Danny Nedelko”での飛び跳ねるようなポップに至るまで、『ジョイ・アズ・アン・アクト・オブ・レジスタンス。』は巧みに練られたサウンドや偽りのスタイルが蔓延する現代世界において、生々しく真っ当で正直なアルバムが精子を持った男たちに勝るとも劣らないほどの突き刺す力を持っていることを証明している。
2位 アークティック・モンキーズ『トランクイリティ・ベース・ホテル・アンド・カジノ』

「キャラクターに扮した」アルバムはしばしば、その人のパレットを一度洗い流すような役割を果たしてくれる。2018年は、それを一度に提供されたような年になった。ミューズの『シミュレーション・セオリー』(1980年代に自分たちが愛していた者に扮している)に、ローラ・マーリングとマイク・リンゼイによる『ランプ』(毛深い雪男に扮している)、そして『トランクイリティ・ベース・ホテル・アンド・カジノ』では、アレックス・ターナー率いるアークティック・モンキーズが『デイリー・スポーツ』紙の紙面が現実になったような月の上のカクテルラウンジでエルヴィス・プレスリー風のキャラクターに扮している。手の込んでない重力に逆らうような耳に優しい楽曲ばかりが詰まったアルバムとなれば、盛大な失敗として終わることになりかねないはずだが、本作は興味をそそられる愛らしい変化をアークティック・モンキーズの物語にもたらしている。彼らが地球に戻った時にどんなバンドになっているのか、一体誰が想像できるだろう?
1位 ザ・1975『ネット上の人間関係についての簡単な調査』
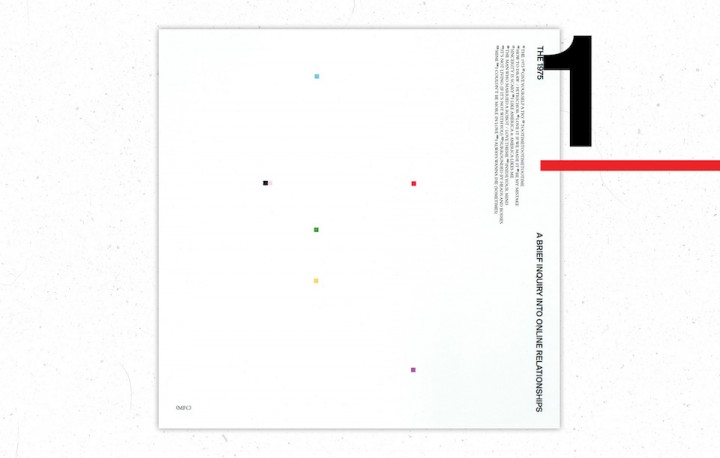
ザ・1975は人気を二分するバンドとして有名だ。『NME』のソーシャル・メディアに(頻繁に)寄せられるコメントに目を通して頂ければ、そのことをお分かりになって頂けることだろう。
『ネット上の人間関係についての簡単な調査』がリリースされるより前、マット・ヒーリーにロサンゼルスでインタヴューをした『NME』の副編集長は、本作について「新しい『OKコンピューター』だよ」と言っていた。それを聞いた私の頭に浮かんだのは、親指を顎に当て、首を傾げるあの絵文字。確かに前作『君が寝てる姿が好きなんだ。なぜなら君は とても美しいのにそれに全く 気がついていないから。』のバンガーは好きだったが、このバンドにはどこか完全にはのめり込めないところがあったのだ。ビッグマウスで、誰もが羨望の眼差しを向けるような自惚れ屋のマット・ヒーリーが、フロントマンとして非の打ち所がない人であることには違いなかったが、私にはまだ、ザ・1975のカルト的な人気について行けていなかったのである。
あらゆる傑作もそうであるように、『ネット上の人間関係についての簡単な調査』を完全に理解するまでには何周かかかったが、すぐに明白になったのは、マット・ヒーリーとドラマーのジョージ・ダニエルが、アルバムとして一つになった本作でも、シングルにあったような多様性を保ちながら、ミレニアル世代を取り巻く世界を一つのカプセルに閉じ込めているということだ。
「僕くらいの歳になれば、見えてくるものもある」と歌われる“Give Yourself A Try”の冒頭の歌詞を聴けば、マット・ヒーリーが大人になったことは明白だ。彼の依存症との闘いはここ数年間で広く知られることになっていたし、今回のアルバムでもたびたび言及されている。けれど、今回のマット・ヒーリーは、自信に満ちた“UGH”時代の生意気な彼とは違う。周囲の世界に対する抜け目のない観察眼はいまだ健在だが、クリーンになるために馬と触れ合ったセラピーを通して自らの内と向き合ったことで、新たに自己認識がそこに備わっているのだ。
速いペースで進んでいく“Give Yourself A Try”や“TOOTIMETOOTIMETOOTIME”から、ディズニー映画『ファンタジア』を彷彿とさせるオープニングから始まるもの、目を閉じて聴きたくなるようなもの、物思いに耽るもの、感覚を刺激するものまで……『ネット上の人間関係についての簡単な調査』とはまるで、サプライズが詰まったチョコレートの箱のようなアルバムなのだ。
我らが「ソング・オブ・ザ・イヤー」のリストでも2位にランクインしている“Love It If We Made It”はアルバムのハイライトで、ファンたちが数ヶ月間ずっと「ファッキング・イン・ザ・カー!」と大声で叫んでいるという事実がこの曲をさらに偉大なものにしている。
“Be My Mistake”には涙が出てしまった。こんなこと、ロードの“Liability”を聴いた時以来、初めてのことだった。“Sincerity is Scary”のミュージック・ビデオが公開された時には、その中でマット・ヒーリーが被っていたウサギの帽子が飛ぶように売れた。おかしな話に聞こえるだろうが、それほどの影響力がこのバンドにはあるのだ。
このランキングに異論を唱える方々へ(きっと大勢いらっしゃるんでしょうけど)。どうか、試しに聴いてみてほしい。一度じゃなく、一曲も飛ばすことなく2回か3回通して聴いてみてほしい。このアルバムはユニークで、複雑で、美しいものだ。このアルバムが特別なのは何も、私たちの時代の政治情勢や感情、人間関係を鋭く観察しているからだけでなく、多岐にわたる様々なスタイルの音楽を取り入れているからでもある。「現代化は私たちを置いていった」かもしれないが、ザ・1975は確実にクオリティを上げている。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.