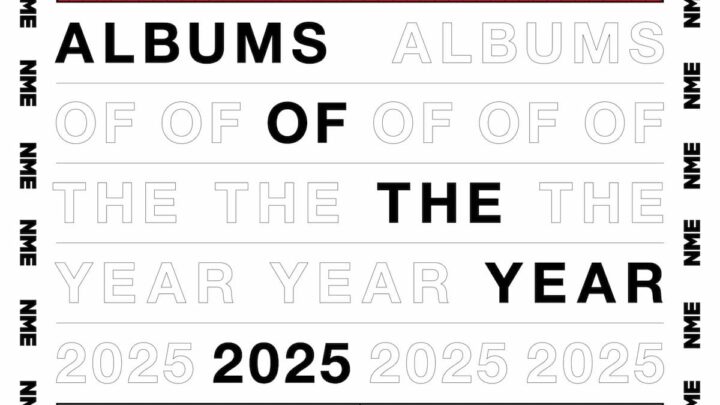30位 ベック『カラーズ』

ベックは、2015年から『カラーズ』を小出しにしてきた――初めはアメリカでヒットとなった“Dreams”に、それから昨夏には“Wow”がリリースされている。ようやく完成したアルバムが届いた時、リリースまでこれほどまでに時間を要した理由は明白に感じることができた。グレッグ・カースティンによる、煌びやかなプロダクションの手助けを受けたアルバムは万華鏡のようであり、ベックはかつてないほどにメインストリームを抱擁したことが分かる様々な楽曲のコレクションとなっていたのだ。臆することなく活気に満ちた“Up All Night”にはメン・アット・ワークのようなフルートのリフもあり、ベックは13作目のソロ・アルバムをもって、今なお聴くのが不可欠であることを証明したのだ。
29位 アーケイド・ファイア『エヴリシング・ナウ』

「少女たちは自分が憎くて仕方ない/睡眠薬を使って身を隠すんだ」とアーケイド・ファイアのヴォーカリストであるウィン・バトラーは感傷的なシンセポップ“Creature Comfort”で陽気に囁いてみせる。勇気のいる内容を率直に語ることと絶対的な音楽的歓喜を並べるという方法論は『エヴリシング・ナウ』で繰り返されているものだ。70年代のMORと80年代のディスコやファンクを彼らのトレードマークであるアート・ロックに融合させ、彼らは世界の現状を歌い、アルバムを通して過駆動のABBAのようなサウンドを(できうる最善のやり方で)奏でている。世界は終焉に向かっているのかもしれないが、アーケイド・ファイアはこれからもパーティーを開き続けてくれることだろう。
28位 メチル・エチル『エヴリシング・イズ・フォーガットゥン』

テーム・インパラやポンドを産み出したサイケ・ワンダーランド――パース出身のメチル・エチルは、どういう訳か、複雑なインディ・ロックを数学的な正しさでもって鳴らしてみせる。オーストラリアからのこのセカンド・アルバムには、彼らにとって初となる純然たるバンガー“Ubu”が収録されており、散髪についてのナンセンスなコーラスが巻き起こす旋風は、聴く者の脳を優しく支配する。しかしながらそれは、あくまでも氷山の一角でしかない:そこには、1曲目の脈動するシンセポップ“Drink Wine”からムーディな“Hyakki Yako”、次元を歪ませる“No. 28”に至るまで、享受すべきソングライティングの真理がまだまだ存在しているのだ。
27位 フー・ファイターズ『コンクリート・アンド・ゴールド』

『コンクリート・アンド・ゴールド』の冒頭の部分で、デイヴ・グロールは自身が落ち着いてしまったこと、もしくはロックの玉座にある自分の地位を放棄することすら示唆している。「王様にはなりたくない。俺はただラヴ・ソングを歌いたいだけなんだ」とデイヴ・グロールは“T-Shirt”で歌い始める。実に紛らわしいイントロだ。楽曲は突如として、クイーンを彷彿とさせる壮大な地を揺るがす咆哮へと雪崩れ込んでいき、それはまさにグラストンベリー・フェスティバルのヘッドライナーに期待する類のものであり、バンドは一向に速度を落とす気配は見せない。そこに続くのはフー・ファイターズの正典に仲間入りを果たす摩天楼に届くような勝ち誇った楽曲と、ちょっとデリカシーを放棄してみせることだけだ。
[cntad1]
26位 ブリーチャーズ『ゴーン・ナウ』

ジャック・アントノフは、内的世界を完全無欠のバンガーに結びつける2017年のポップ・アルバムにおける「絶対的な少年」となった。ロードの『メロドラマ』やテイラー・スウィフトの『レピュテーション』で楽曲をプロデュースした元ファンの男は、2017年の残りを休暇に充てるありとあらゆる権利を有していた。休暇とは引き換えに、ジャック・アントノフは自身のブリーチャーズによるサード・アルバム『ゴーン・ナウ』で異常に活発な感情のジェットコースターを作り出している。ジャック・アントノフは、決して成層圏に届くようなフックを書くのに苦労することはなく、輝かしいピアノに涙を誘う歌詞世界と率直な感情を融合させている。
25位 ケリー・リー・オーウェンス『ケリー・リー・オーウェンス』

インディ・バンド、ザ・ヒストリー・オブ・アップル・パイの元メンバーであるウェールズ出身のミュージシャンのデビュー作は、彼らが秀でていた病的に甘いインディ・ポップとは程遠い位置にある。代わりにケリー・リー・オーウェンスによるセルフタイトルを冠したデビュー作は、ハウスやテクノ、アンビエント、インディ、そしてポップの中を旅している。予測不能な彼女のアルバムの中で、彼女はすべての曲で新たな境地を開いてみせる。ドリーミーな“Keep Walking”からクラブ向けのバンガー“Evolution”に至るまで、ケリー・リー・オーウェンスは自身の多岐に渡った音楽のアイデンティティが美しく魅力的なものであることを証明している。本当にその通りだ。
24位 パフューム・ジーニアス『ノー・シェイプ』
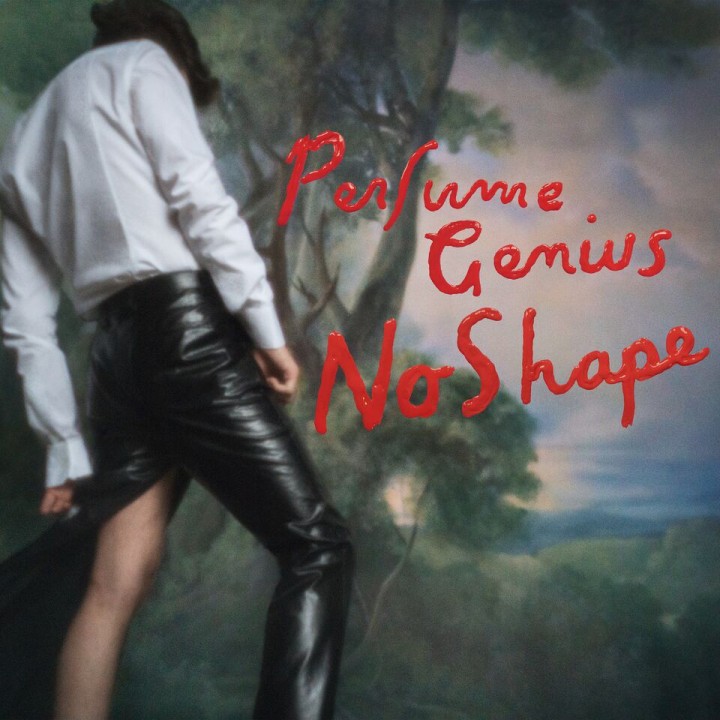
『ノー・シェイプ』はゴージャスな一手と共に幕を開ける。デリケートなピアノ・バラードはマイク・ハドレアスの音楽の主要産物となっており、この通算4作目となるアルバムもまたピアノ・バラードをもってスタートしているものの、“Otherside”では1分にわたって、膨大なベースの鼓動と何百万にも輝く煌びやかな音たちをもって、聴く者の期待を爆発させている。楽曲の音楽性や歌詞は彼の過去のアルバムたちにおけるテーマ――疎外感、依存、怒り――とは反するものとなっており、代わりに実に野心的な楽器編成に乗せて、永遠の愛についての様々な一面を探求している。アルバムにおける優しさのピーク(“Die 4 You”)で、彼は官能的な窒息プレイについてのスロー・ジャムにシャーデーを落とし込んでいる。この前進は実に魅惑的だ。
[cntad2]
23位 サンファ『プロセス』

サンファはこれまでコラボレーション相手の男だった。彼と一緒に作業をした相手の中にはソランジュ、ドレイク、カニエ・ウェストなどがいる。しかし、マーキュリー・プライズを受賞した彼のデビュー作『プロセス』で、彼は中心に存在しており、自身をサポートするための重要人物など必要でないことを示している。複雑に入り組んだ楽器が織りなす流れるような光り輝く音色と、(癌で亡くした自身の母親について率直に語っている)圧倒的なまでに正直なリリックは卓越している。しかし、キラリと光るプロダクションやエネルギーに溢れたボーカルを脇に置いて1曲ずつ骨の芯まで突き詰めていったとしても、『プロセス』は最上級のものであり、サンファは最善を尽くして見事に完璧な楽曲の数々を作り上げている。
22位 ケヴィン・モービー『シティー・ミュージック』

通算4作目となるソロ・アルバムで、彼はこれまでで最も共感しやすく親しみやすいアルバムに到達している。前作『シンギング・ソウ』は、ワシントン山周辺にあるカリフォルニアの静かな地域で生まれたものだったが、『シティ・ミュージック』ではすべてが変わったことを証明している。“Aboard My Train”や“Cry Baby”といった曲の中では現代の都会暮らしの物語が飛び交っており、お祝いムードながら好奇の目にさらされているモービー自身を描いている。“1234”はパンク・レジェンドであるザ・ラモーンズへのゾクゾクするトリビュートのようであるし、アルバムの中間に位置するタイトルトラックは歪んだリフがヘヴィーだ。モービーがどこにいようとも、彼の才能は否定しようがないものなのだ。
21位 シアー・マグ『ニード・トゥ・フィール・ユア・ラヴ』

フィラデルフィア出身のロック・バンドであるシアー・マグは戦闘態勢が整っている。例えば、彼女たちのデビュー・アルバムのオープニングを飾る“Meet Me In The Street”は、リリースの6ヶ月前に起きたドナルド・トランプの大統領就任に伴う抗議や運動から影響を受けた曲である。だからといって、反抗の悪臭が初めに登場するだけではない。『ニード・トゥ・フィール・ユア・ラヴ』における、ヘヴィーなメタルっぽいギター・フレーズの一つ一つや、フロントを務める女性のティナ・ハラデイの耳をつんざくようなボーカルの一瞬一瞬が、曲の真っ只中にあってまさにピッタリなのだと思える。猛烈な始まりである。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.