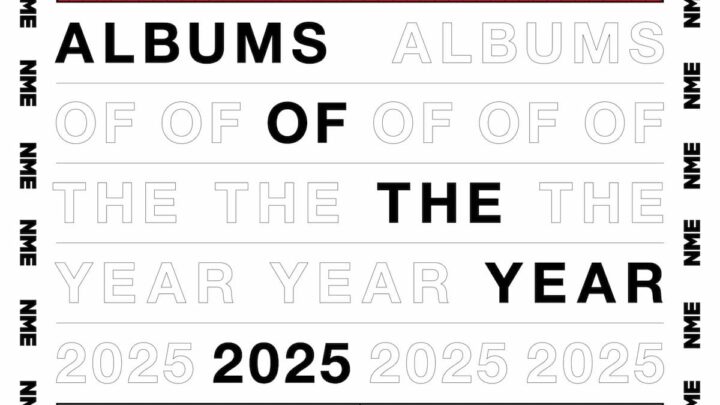10位 カマシ・ワシントン(7/24 FIELD OF HEVAEN)
最終日のフィールド・オブ・ヘヴンのトリを飾ったのは、ジャンルを超え、多くのミュージシャンから支持されるサックス奏者のカマシ・ワシントンだ。約3時間におよぶ超大作の新譜『ザ・エピック』が大きな話題となり、ステージ登場前から嬉しさを抑えきれない熱心なファンが集まっている。出演者全員、技術やミュージシャンシップについては言うまでもないけれど、ただ奇をてらうところはまったくなく、ステージ中央のカマシも悠然としている。それが既存のジャズなどの座標軸とまったく違うところに彼を位置づけていた。その掛け値のない音楽力だけで興奮を生み出し、すべてをさらっていく。こういうアクトをフジで、ヘヴンで観られるのがなによりの至福だった。
9位 バトルス(7/24 WHITE STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi/PRESS
レッド・ホット・チリ・ペッパーズの後にホワイト・ステージの最後のトリを務めたのは彼らだった。やっぱり頭上高くに設置されたあのシンバルを見ると、胸が高鳴る。最新作からの“DOT COM”から始まったステージ、早くも序盤“Ice Cream”でハイライトが訪れる。いつだって間違いのない人たちだけれど、ジョン・ステニアーのドラムのキレがいつにも増してすさまじい。ライヴでしか聴けないこの人のドラムはやっぱり好きだ。3日間の最後だけれど、自然と身体が動き出す。機材トラブルもあったがなんのその、初期の楽曲もかなりやっていて、そこに今のバトルスの自信を感じる。最後が最新作からの“The Yabba”というのも最高。しっかりと今年のフジを締めくくってくれた。
8位 リオン・ブリッジズ(7/24 FIELD OF HEVAEN)
時代を感じさせるレトロなシャツを着て現れたリオン・ブリッジズ。そして、1曲目となった“Smooth Sailin’”を歌い出しただけで、ガラッと自分の中の時代意識が変わる。50~60年代のR&Bを追及するその姿勢は音源からも十分感じ取れるものだったけれど、生は違う。素朴だけれど、その声は凛々しく、そしてあたたかい。グルーヴによって自然とスイングしていくバンドを引き連れながら、その後も彼は真っ直ぐな歌を響かせていく。デビュー作のタイトル曲である”Coming Home”の頃にはすっかり観客との間にも阿吽の呼吸ができている。ライヴを締めくくったのはコーラスとキーボードとの3人だけで披露された”River”。最後に歌声だけですべてを伝えきって、ステージを降りていった。
7位 レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(7/24 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse/PRESS
20周年の最終日を締めくくるヘッドライナーがレッチリ。これほど完璧な舞台があるだろうか。会場に漂う期待感もすごかった。それに較べると、レッチリらしさが全開のステージとは言えない部分もあった。新作からの楽曲が数多く聞けたのは嬉しかったが、”Dreams Of A Samurai”でマイクを投げつけたアンソニーをはじめ、不安に思う場面もあった。なによりやってほしい曲がたくさんあったファンは少なくないはずだ。でも、あのグリーン・ステージを埋めた観客の数が何よりも雄弁に物語っていたけれど、それはレッチリが愛されている証拠でもある。大団円となった”Give It Away”で爆発するように盛り上がるオーディエンスを見ながら、その愛を感じていた。
6位 イヤーズ&イヤーズ(7/24 RED MARQUEE)
レッチリ直前のレッド・マーキーということで心配していたのだが、杞憂に過ぎなかった。“Foundation”から始まったステージ、とにかく彼らの武器はデビュー作『コミュニオン』が楽曲の数々が素晴らしいこと。そして、UK産エレクトロ・ポップとしてヒューマン・リーグ〜ペット・ショップ・ボーイズに連なる独特の徒花感と享楽姓を持ち合わせていることだ。これがフジのレッド・マーキーにはハマった。”Desire”や”Shine”といったヒット曲はもちろん、ケイティ・ペリーの”Dark Horse”のカヴァーなども織り交ぜ、ライヴを締めくくる”King”の大合唱まで、結局レッド・マーキーを離れることができなかった。レッチリのスタートが少し遅れて、胸を撫で下ろしていた。
5位 ジェイムス・ブレイク(7/22 GREEN STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi/PRESS
闇に包まれ始めたグリーン・ステージに、あの静謐なサウンドスケープが広がっていく。マルチプレイヤーのエアヘッド、パーカッションのべン・アシッターと共に今回も3人のバンド編成で登場したジェイムス・ブレイク。しかし、過去の来日と較べても音の重厚感がすごい。エレクトロ・ミュージックでありながら打ち込みを使わず、肉体だけであの研ぎ澄まされたアンサンブルを再現していくわけだが、3作で培った経験値が見事にライヴにも反映されている。ルコックのトレーナーに身を包んだパジャマのような格好には笑ったが、音のシリアスさが今の現在地を雄弁に語っていた。終盤、虫を払うために演奏を止めたジェイムス・ブレイク、そんな彼も可愛かった。
4位 ジャック・ガラット(7/24 RED MARQUEE)
BBC サウンド・オブ・2016の1位ということで、優等生的に見られることの多い彼だが、初来日の今回はいい意味で驚かされることになった。デビュー作収録の“Coalesce”で始まったステージ、彼も一人ディスクロージャー状態で、歌からパッドからシンセ、ギターまで、すべて一人でこなすのだが、その肉体性のレベルが非常に高い。音源ではシンガーソングライター的な佇まいがあるが、ライヴではそれがエレクトロニック/ダンスになる。レッド・マーキーがそれに歓声でもって応じたところ、恥ずかしいのか、突如笑い出す。この時点でこの日のステージは約束されたようなものだった。ちょっとトチる部分もあったりしたが、最後の“Worry”まで盛り上がりが収まることはなかった。
3位 コートニー・バーネット(7/22 RED MARQUEE)
昨年リリースのデビュー作が各種イヤー・エンド・チャートで軒並み上位にランクインし、グラミーの最優秀新人賞にもノミネートされた彼女、そこまでの評価を獲得している理由は一目瞭然だった。アンプ直鳴りのようなギター・サウンド、中性的なけだるい声、そして、ロックではなくロールすることに重心を置いたソングライティング。それが彼女のもとで一つになった時、魔法が起きる。ストレート極まりないガレージ/ロックンロールがサイケデリアを帯び、2016年に寄り添うサウンドトラックになる。頭の“Dead Fox”から“Elevator Operator”、最後の“Nobody Really Cares If You Don’t Go to the Part”まで、新たなロックンロールの可能性に興奮しっぱなしだった。
2位 ディスクロージャー(7/22 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse/PRESS
徹頭徹尾、完璧なステージだった。ディスクロージャーというのは抱えるものが大きいグループだ。ダンス・ミュージックとして、ポップ・ミュージックとして、ライヴ・アクトとして、プロデューサーとして、そのすべてに応えなければならない。そして、フジの場で彼らは見事に応えてみせた。特に感動的だったのはセカンド『カラカル』の楽曲が見事にライヴで機能していたこと。ブレンダン・ライリーをゲストに迎え入れた“Moving Mountains”はもちろん、“Holding On”も、“Omen”も、“Jaded”も昇華されて、ディスクロージャーのライヴに血肉化されていた。イントロのサンプリングを再生しただけで、大歓声が巻き起こった最後の“Latch”は美しい光景だった。
1位 ベック(7/23 GREEN STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi/PRESS
“Devil’s Haircut”のイントロが流れた瞬間、グリーン・ステージ全体が瞬間沸騰する。”Black Tambourine”に続いて、今度は3曲目に“Loser”である。さらに4曲目は“The New Pollution”なのだ。キャリアを代表する名曲中の名曲が序盤で矢継ぎ早に投入される。でも、ここからがすごかった。『ミューテイションズ』の楽曲をはじめ、“Everybody’s Got to Learn Sometime”など、緻密な計算の元、セットリストのすべての曲が絶妙な位置にあり、後半でも”Dreams”のような最新の楽曲がハイライトを生み出す。そして、アンコールの“Where It’s At”では、メンバー紹介を交えながら、デヴィッド・ボウイ、プリンスのカヴァーを披露してみせる。2016年に、フジ20周年のヘッドライナーを務めるという、そのすべてを引き受けてくれたステージだった。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.