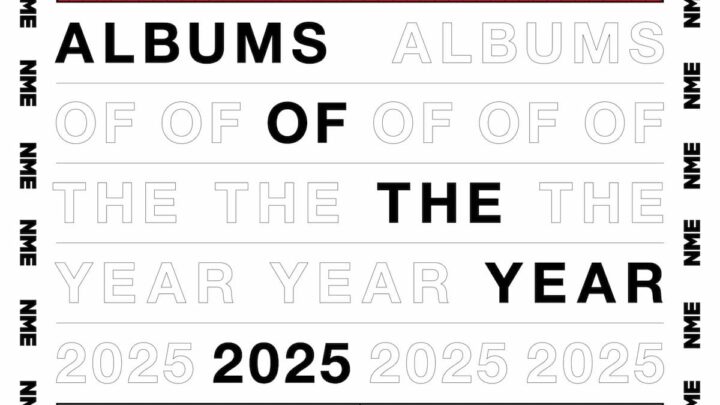10位 ブラー『ザ・バラード・オブ・ダーレン』

ブリットポップの英雄であるブラーが2022年後半に再始動を発表した時、『ザ・バラード・オブ・ダーレン』はそのアイディアの核心ではなかった。デーモン・アルバーンは当初『モダン・ライフ・イズ・ラビッシュ』の30周年のためにブッキングされていた差し迫るウェンブリー・スタジアムでの公演がバンド全員をスタジオに戻すクリエイティヴな機運になったと語っている。2003年発表の『シンク・タンク』で経験したグレアム・コクソンの不在、2015年発表の『ザ・マジック・ウィップ』での突飛なレコーディングを経て、『ザ・バラード・オブ・ダーレン』は2000年以降で一番いい作品であり、失われた人間関係と中年のやるせなさが描かれている。
9位 ミツキ『ザ・ランド・イズ・インホスピタブル・アンド・ソー・アー・ウィ』

ミツキは他の誰とも違う形で失恋について曲にしてきたが、ここ数作はそれをきらびやかなシンセサイザーと真逆のポップ・ソングでコーティングしてきた。しかし、今回は違う。アコースティック・ギターにスライド・ギター、ストリングスが主体となった通算7作目のアルバムは悲しげなカントリーの雰囲気がある。楽器陣が豪華な時は独自の世界を構築しているようで、削ぎ落とされると郷愁で打ちのめされる。ミツキの素晴らしい声が中心となって、スモーキーで憂いを帯びたメロディーは操り人形のように予想外の方向へと動き出す。今となっては彼女がその世代において最高のソングライターの一人であることを否定する声はほとんどないだろう。
8位 アマレイ『ファウンテン・ベイビー』
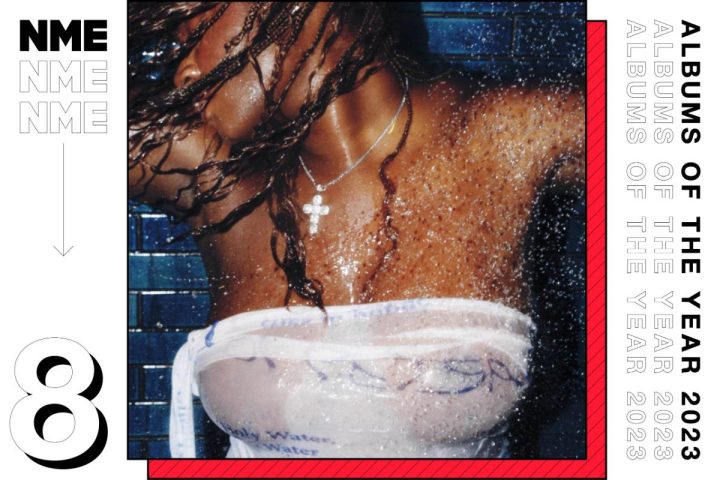
オルタナティヴ・アフロポップの領域を再定義することになった本作でガーナ系アメリカ人のアマレイは直球のストーリーテリングでアルバムの舵取りをしながら、ラグジュアリーなサウンドを作り上げる能力を発揮している。彼女のセカンド・アルバムは崇高なアラビア音階やパンク・ロックの反抗的な奔放さなど、多種多様なグローバルな影響を受けながら、この人ならではの甘い声と組み合わさることで忘れられないような体験を生み出すことになった。
7位 ソフィア・コルテシス『マドレス』

ペルー生まれでベルリンを拠点とするDJ/プロデューサーのソフィア・コルテシスのデビュー・アルバムは2021年にガンと診断された母親を救った神経外科医のペーター・ヴァイコッツィー医師に捧げられている。「彼は私を勇敢に、よりリスクを請け負うようにしてくれた」とソフィア・コルテシスは『NME』に語っており、その感謝の思いと強靭さがアルバムを通して弾けるような喜びと癒やしと共に輝いている。ソフィア・コルテシスのビートは太陽の光と歓喜に満ちていて、「さあ、前に進もう」と歌うハイライト“Si Te Portas Bonito”はこの特別なアルバムに収録された無数の感動的な瞬間の一つとなっている。
6位 キャロライン・ポラチェック『ディザイア、アイ・ウォント・ターン・イントゥ・ユー』

キャロライン・ポラチェックは広範にわたる『ディザイア、アイ・ウォント・ターン・イントゥ・ユー』で自身のサウンドをよりオープンに広げている。『パング』のアヴァンギャルド・ポップを経て、ここにはジャンルもトラックもアレンジも恐れずに弄んでみせる革新的なアーティストがいる。アルバムにはスパニッシュ・ギターもバグパイプもトリップ・ホップもUKガラージもグライムスもダイドも登場するが、そんな幅広さにもかかわらず、彼女は本作でこれらの異質なサウンドを独自のものに作り上げることに成功している。
5位 パラモア『ディス・イズ・ホワイ』

ブリティッシュ・インディへの愛情を前面に押し出した『ディス・イズ・ホワイ』で米国の主唱者であるパラモアは痛々しく窮屈な感情に焦点を合わせながら、自分を見失うことなく、人間としてバンドメイトとして恋人として社会的な提唱者としてよりよき存在であろうとしている。“Running Out Of Time”や“C’est Comme Ça”など、ポップ・ロックの華々しいダンサブルな瞬間もあるが、ピクシーズ風の最終曲“Thick Skull”では親密さを見せ、ヘイリー・ウィリアムスのヴォーカルの繊細さと力強さをスリリングな形で活かしている。3人のメンバーが同じ方向を向いていることは明らかで、グループとしての未来がここまで明るいことはこれまでなかった。
4位 トロイ・シヴァン『サムシング・トゥ・ギヴ・イーチ・アザー』

“Honey”を決定づける滴るような熱い欲望に、“Got Me Started”での完璧なタイミングでのバッグ・レイダースのサンプリング、『サムシング・トゥ・ギヴ・イーチ・アザー』でのエクスタシーの瞬間の数々といったら、そこには深い気品の感覚まであるのだ。別れを経て第二の故郷であるメルボルンに慣れるまで、トロイ・シヴァンは奇妙な数年間を過ごすことになったが、キャリア最高の作品にすべてを注ぎ込み、彼は後悔を放棄して恥じる気持ちをなくしてみせた。
3曲の楽曲がなぜポップ・ミュージックが傷心時の光の道しるべとなるのかという核心に踏み込んでいる。欲望の持つ可能性と明るくセクシーな未来が“Rush”や“Silly”のBPMと共に強まっていき、ここでの主張に踏み切った姿勢は新しく現れたアイコンとしてのトロイ・シヴァンの地位を確固たるものにするだろう。
3位 ヤング・ファーザーズ『ヘヴィ・ヘヴィ』

スコットランド出身のヤング・ファーザーズは通算4作目となるアルバム『ヘヴィ・ヘヴィ』で自身のクリエイティヴ面での力を証明することになった。アルバムは歓喜と共に進みながら、人間性やクリエイティヴィティにも切り込み、一つ一つの曲や瞬間がなぜこれほどまでに影響を与えるのか、突き止めようとしても無駄にさえ感じられる。“I Saw”は直接的でありながら、探究的でもあり、2023年の最良のロック・ナンバーの一つだろう。一方、“Rice”はアフリカの天然資源略奪の問題にも触れている。
「アンセム風でありながら同等の感染力も備えるプロジェクトにこのような政治的な歌詞がさりげなく盛り込まれているのは素晴らしいソングライティングの賜物だ」と『NME』は五つ星のレヴューで述べている。傑作だ。
2位 オリヴィア・ロドリゴ『ガッツ』

オリヴィア・ロドリゴほど楽しげに臆面もなくエンタテインメント界の少女をやってのける人はいない。痛烈で、時に熱に浮かされたような12曲には何百万人という世界中の聴衆に向けて放送することはおろか、友人と共有することも恥ずかしくてできないような告白が詰め込まれている。「好きな人はみんなゲイなの」と20歳の彼女は“Ballad Of A Homeschooled Girl”で叫び、その誇張されたかのような事実がアルバムの主な収穫を強調している。『ガッツ』は最近の痛みから生まれているのだ。
オリヴィア・ロドリゴは本作で若い成人になった今、人生を理解できるのだろうかと度々思いを馳せている。その所感はアドレナリン全開のギターと叫ぶようなヴォーカルによって語られていくが、彼女はまさにそうした自分の中にある激しい部分に敢えて入り込むことで、自分自身を祝福してみせた。
1位 ボーイジーニアス『ザ・レコード』

ボーイジーニアスのように2023年を制覇してみせたアーティストはほとんどいない。フィービー・ブリジャーズ、ルーシー・ダッカス、ジュリアン・ベイカーは以前から熱狂的なファンの注目を集めていたかもしれないが、2023年は待望のフル・アルバム『ザ・レコード』のおかげで新たなレベルのカルト的崇拝にまで達することになった。
アルバムでは様々な形の人間関係が扱われているが、その中心にあるのは世代でも最も鋭い3人のソングライターの友情であり、それは歌詞でもパフォーマンスでも描かれている。“Leonard Cohen”では友人と間違った方向に車を走らせてしまったというありふれた逸話が、自分のことを知ってもらうとはどういうことかという人との繋がりに関する感動的な内容の楽曲に生まれ変わっており、友情はどこまで続くのか? 悪さえをも切り抜けるのか?という疑問を投げかけている。そして、ハイライトの一つと言える“Not Strong Enough”では弱さをさらけ出すことに強さを見出した。この曲はボーイジーニアスについて「常に天使であって、決して神ではない」と位置づけているかもしれないが、『ザ・レコード』は音楽界における神としての立場にボーイジーニアスを近づけることになっている。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.