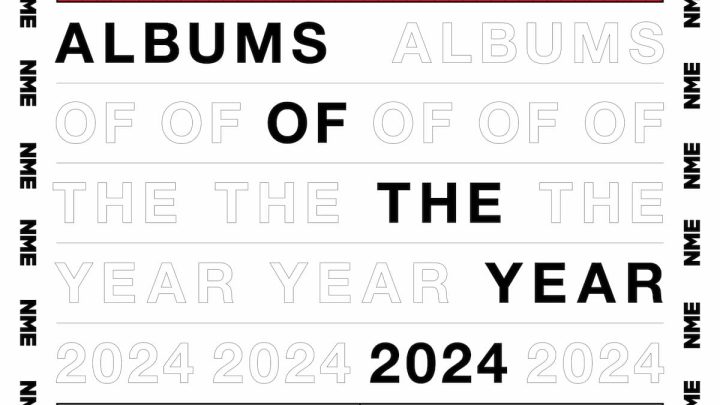Photo: 宇宙大使☆スター
NME Japanでは今年のフジロックフェスティバルでベスト・アクトの1〜15位を選んでみました。とはいっても、多くのアーティストが出演するフジロックです。すべてのアーティストを観ることはできません。なので、あくまで独断で、編集部で観たいと思ったアーティストのなかから、議論を重ねて、このランキングを作成してみました。みなさんのベスト・アクトとぜひ較べてみてください。
15位 アルトゥン・ギュン(7/31 FIELD OF HEAVEN)
今年のラインナップで最もフジロックフェスティバルらしいアクトだったと言ってもいいのではないだろうか? 知名度はそこそこだったとしても、ライヴを一目観ると、音楽を長年聴いてきた人たちの心が思わず掴まれてしまうようなアクトを、フジロックフェスティバルというのはいつも必ず用意してくる。3日目のフィールド・オブ・ヘヴンに登場したアルトゥン・ギュンはまさにそんなアーティストだった。まったくノー・マークで観たのだが、フォークとサイケデリック・ロックを混ぜたサウンドでとっさに思い浮かべたのはクルアンビンやテーム・インパラといったアーティストで、後半には“Leyla”のようなハード・ロック色が強い曲やスピード感のある曲もあったのだが、浮遊感のあるグルーヴという現在のギター・ミュージックのトレンドを踏まえながらも、ルーツと民族性を前面に出した音楽性は観た者に強いインパクトを残すのには十分だった。
14位 スーパーオーガニズム(7/31 WHITE STAGE)

Photo: Kazuma Kobayashi
7月15日にセカンド・アルバム『ワールド・ワイド・ポップ』をリリースして、その直後にフジロックフェスティバルへの出演となったスーパーオーガニズムだが、これまでの2枚のアルバムでユニバーサル・デザインのポップ・ミュージックを作る能力というのは既に証明済みだ。新作の表題曲“World Wide Pop”から始まったステージは、展開されるダンスも含めて、気持ちいいほどクリアかつヴィヴィッドで、その思いは曲を重ねるにつれて強くなっていく。ゆるめの“The Prawn Song”や挨拶代わりの“SPRORGNSM”といった曲の間にセカンド・アルバムからの曲を挟みながらもトーンは一貫している。後半にはもちろん“Nobody Cares”や“Everybody Wants to Be Famous”といったアンセムが投下されていくのだが、そのパステル・カラーのポップネスの裏にある、その先をもっとパフォーマンスとして観られることになるのは次の機会なんじゃないかと思っている。
13位 モグワイ(7/31 RED MARQUEE)

Photo: Yuki Kuroyanagi
今回のランキングにはダイナソーJr.が入っていない。それはタイムテーブルの関係で最初の2曲しか観られなかった事情もあるのだけど、その時抱いた思いとモグワイのステージを観ながら自分が考えたことは非常に近かったので、この順位はその2組の同率順位だと思ってもらえればと思う。自分がモグワイを観た回数をちゃんと数えたことはないけれど、おそらく2桁は行っているんじゃないかと思う。基本的な原理は大きく変わらないバンドなので、目新しさはない。人力でアンサンブルが丁寧に積み上げられていって、それが終盤カタルシスを迎える。なので、飽きそうなものなのだが、その快感を潜在意識とは言わないでも深い記憶が知っていて、“Mogwai Fear Satan”を迎える頃にはやっぱりこれだよとなる。そして、モグワイやダイナソーJr.が日本でライヴをやる度に初めて観る人がいて、自分のような記憶を持つことになる。その連環に思いを馳せた。
12位 ジャパニーズ・ブレックファースト(7/31 GREEN STAGE)

Photo: Taio Konishi
ビーバドゥービーやミツキなど、オルタナティヴ・ポップの分野でアジアをルーツに持つ優れたアーティストが次々と登場しているが、それは偶然ではないのだと思う。ジャパニーズ・ブレックファーストのステージを観て強く思ったのはそれだった。最初の3曲は最新作『ジュビリー』とまったく同じ流れで始まったのだが、古き良きインディ・マナーをオーセンティックに再現していくその手腕は実に見事。中盤の“The Body Is a Blade”では幼い頃の母親の写真が次々と映像に登場して、彼女の出自が観客に向けてメッセージとして発信される。それは世界に向けた表現となっていて、ノスタルジーではなく、あくまで現在進行系としてインディ・ポップを鳴らしている彼女の立ち位置を端的に伝えてくれる。後半にはあの“Dreams”という技ありなカヴァーもありつつ、最後に演奏されたのは前作でも出色の出来だった“Diving Woman”。世界的認知を急速に広げている彼女の今が表れたステージだった。
11位 トム・ミッシュ(7/31 GREEN STAGE)

Photo: Taio Konishi
ステージには巨大なミラーボールが吊るされている。ヘッドライナー直前のスロットという気合の表れだったのだろう。事前にツアーをキャンセルした事情などは知らずに観たのだが、トム・ミッシュの音楽の根幹が垣間見えたステージになった。ユセフ・デイズとのコラボ作のタイトル曲から始まったのだが、2曲目で『ジオグラフィー』からの人気曲“It Run’s Through Me”のイントロが演奏されると大きな拍手が起こる。3曲目の“Losing My Way”を終えたところで「コンニチハ、来られて嬉しいよ」と短く挨拶。その後もマイケル・キワヌーカとのコラボである“Money”、アップテンポな“Disco Yes”など、キャリアを彩る楽曲が続くのだが、音源を聴いた時から思っていたのはトム・ミッシュの音楽において最も重要な要素はデザインなのだと思う。その構図や色使いの見事さはライヴでも逸脱したり崩れることはない。その印象は最後の人気曲“Lost in Paris”と“South of the River”まで変わることはなかった。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.