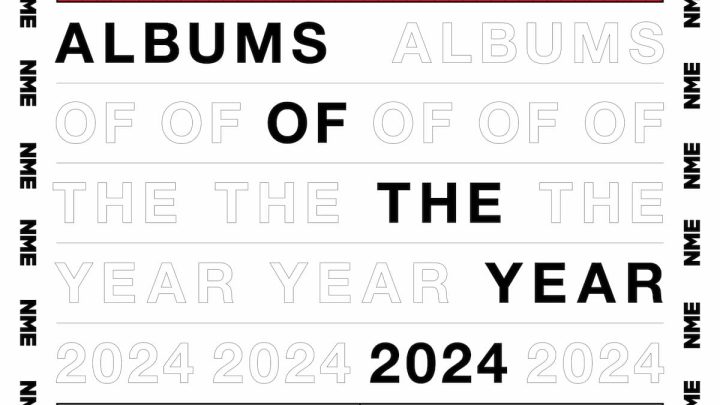Photo: 78 Productions Limited 2023
ルイ・トムリンソンのドキュメンタリー映画『オール・オブ・ゾーズ・ヴォイシズ(ALL OF THOSE VOICES)』が3月22日より期間限定で日本各地で劇場公開される。本作は絶頂の真っ只中で活動を停止させることになったワン・ダイレクションの最後のコンサート・シーンから始まり、悲劇を経て、ソロとしてのキャリアを歩み出したルイ・トムリンソンの実像ついて至近距離で迫るものとなっている。監督を務めたのはチャーリー・ライトニングという人で、リアム・ギャラガーのドキュメンタリー『アズ・イット・ワズ』を手掛け、ポール・マッカートニー帯同の映像作家を長年にわたって務めている人物だ。NME Japanと彼とは何年も前からの知り合いで、今回は友人として本作について話を聞かせてもらった。彼の作品は常に被写体との距離の近さが魅力で、飾らない形で真実の姿が明らかにされていくのだが、それはボーイ・バンドにいたルイ・トムリンソンが対象になっても変わっていない。「この映画は、結局はヒューマン・ストーリー、ある人間の『旅』を描いたものなんだ。だからこそ普遍的な内容になっているんだと思う。ファン向けなだけじゃなくてね。もちろん、観て夢中になってくれるのはファンだけど、ファンじゃない人が観たとしても楽しめる内容になっているし、考えさせられるものがきっとある」とチャーリー・ライトニングは語ってくれたが、その背景を聞いた。
――数年前に遡ると思うんですが、このプロジェクトの話があなたのところに来た経緯というのは、どのようなものだったのでしょう?
「最終的には4年くらいかけて撮ったのかな?リアム・ギャラガーの映画『アズ・イット・ワズ』を撮ったんだけど、ルイ・トムリンソンがそのプレミアに来たんだ。同じ空間にいたのは見かけたけど、特に話した訳ではなかった。その後、彼の関係者から連絡があって、ミュージック・ビデオを一緒に作ることになった。そこから割と自然な形で今に至るんだ。彼のストーリーについては知っていたしね。というか、ワン・ダイレクションのメンバーだったし、そのストーリーを知らない訳がないという感じだよね。結成したシーズンの『Xファクター』も見ていた。ということで、彼や彼のキャリアについては認識していた。何をやっているかとかね。実際、ミュージック・ビデオ作りで出会ったら意気投合して、彼をとても気に入った。すごく感銘を受けたよ。彼のポテンシャルや才能を垣間見て、これから息の長いアーティストになると思ったんだ。それで彼を撮るようになってから自然な流れで発展していったんだ」
――今回の作品はすごくエモーショナルな内容ですよね。プロジェクトによって異なると思うんですけど、被写体となるアーティストとは最初にどこまで話すものなんでしょうか?
「話さなかったね。この映画の素晴らしいところは彼の誠実さであって……彼は被写体になるのがとても上手なんだ。リラックスして撮影に臨むことができる。ワン・ダイレクションで、いつもカメラに囲まれて育ってきたからね。それと、僕たちがウマが合ったからというのもあるな。かなり早く意気投合したし、だからこそ、この映画が実現したんだと思う。すべてが自然体に感じられたからね。通常、この規模の映画というのはクルーがたくさんいるんだ。監督がいてカメラマンが何人かいて、音声を録る人がいて。撮影もすごくきっちりしていて、2週間とか決められた期間や予算の中でこれを撮る、と決まっている。その2週間の中であれを撮らないといけない、これを撮らないといけない、という感じでさ。まるで強制的に物事を起こすような感じでね。でも、この映画の場合は9割方僕と彼とカメラだけだ。『これを撮る』というよりもひたすら撮り続けて、何かが自然に起こるに任せることができる。もちろん、頭の中にはストーリーが全部頭に入っていて、その合間に起こる彼のちょっとした発言やちょっとした出来事を見落とさないようにしないといけないけどね。内容も時間をかけて発展していく。初めはとにかくできるだけ長い時間を一緒に過ごすことが大事なんだ。彼が自分の人生やストーリーを語ってくれて、お互いを知る時間が必要だからね。お互いを知ることができれば、相手の人生にとって大切な人々が誰かわかる。例えば彼の息子とか、それから彼といつも一緒にいて仕事しているオリヴァー・ライトとかね。彼らの関係はとても興味深いよ。映画の中でもとても面白い存在として描かれていると思う。それがルイのいいところなんだ。彼はあまり自分自身にはこだわりがないけど、自分のやることに対しては真摯に向き合う。一緒にいて楽しい人だし、この仕事も素晴らしい経験になったよ」
――こういうことを訊いたのは、実はこの作品において、ひとつ大きなトピックとして「肉親の死」というものがありますよね。それも結構自然に取り扱うことになったという感じなんですか?
「そういうのが報道されるたびに、彼がどんな思いをしていたのか僕は知っていた。というか、みんな知っていたと思うけどね。彼自身が口を開いて自分の視点で語った訳ではないけど。僕たちは彼のストーリーを伝えるために映画を作っていたから、映画の中で(肉親の死を)採り上げるべきということは分かっていた。ただ、その伝え方については僕にとても強いこだわりがあった。彼の人生だからね。彼の人生に起こったこと、彼が経験したことだから、それを正しい形で見せることに重大な責任を感じたよ。その状況を『利用』することのないようにね。観る側の感情をかき立てるためにそういうものを取り上げている映画というのもあるけど、それは彼の軌跡の一部なんだ。それが彼にどんな変化をもたらしたか、何を学んだか、どうやって前に進んでいったかが重要だから、今回は採り上げることにした」
――あなたはこれまでも錚々たるアーティストと仕事をしてきた訳ですが、このプロジェクトに取り掛かる前のワン・ダイレクションの印象というのはどのようなものがありましたか?
「彼らがどれほどビッグだったかは見過ごすことはできないよね。ファンだったよ。彼らは本当に素晴らしい活動をしていたと思う。曲もよく書かれていたし、ルックスもとてもクールだったし、スタイルも良かった。ボーイ・バンドらしさもありながら、ボーイ・バンドに期待されるもの……同じ服装とかダンスのルーティンとか、そういうものではなかった、そういうところが大好きだった。そこから生まれる信憑性もね。その多くはルイからも来ていると思うよ。彼と話しているとその一面を強調したくなるんだ。彼らは自分らしいファッションをして自分らしく振舞っていた。彼はいつもそういう面を持っていたと思う」
「僕はテレビで彼らを見ていて、彼らが結成されるいきさつも観てきた。確か番組の中では3位じゃなかったかな? 成功すると思ったのを憶えているよ。僕はその頃、確かポール・マッカートニーの仕事でニューヨークにいたんだと思うけど、マディソン・スクウェア・ガーデンにいたんだ。マディソン・スクウェア・ガーデンを出たところにワン・ダイレクションのポップアップ・ショップがあってね。『マジか! ニューヨークに自分のお店があるなんて』と思ったよ(笑)。彼らが何だったのか、その事実を見過ごすことは、さっきも言ったけど不可能なんだ。彼やバンドのこと、何が起こったのかを知っていくと……彼らがどんなにビッグになったかを理解するだけでも興味深いよ。自分としては、ポール・マッカートニーのザ・ビートルズ時代をある意味彷彿とさせた。ポールとリンゴ・スターを見ていると面白いんだ。当時がどんな感じだったか知っているのは当事者だった彼らだけだからね。ワン・ダイレクションとしての人生もそんな感じだったんじゃないかと思う。みんな外から見てどんな感じだったか考えることはできるけど、実際を知っているのは5人だけだからね。彼らが経験してきたことを経験してきた人たちはそう多くない。彼らのポップ・バンドとしての成功はザ・ビートルズ以来だと思うしね。イン・シンクやバックストリート・ボーイズはいたけど、ワン・ダイレクションはもっとユニークな存在だったと思う。それが彼らが個別にやっていたことに表れていると思うんだ。バックストリート・ボーイズとかは違うよね。(イン・シンクの)ジャスティン・ティンバーレイクは成功したけど、他の人たちは何をやっている? そして、ご存じの通りハリー・スタイルズもまた独特の存在だよね。ワン・ダイレクションは個別にやっていることが違うというのもいいと思う。ハリーがやっていることはルイとちょっと違うし、ルイもナイル・ホーランとは違う。それぞれファンに見せているものが違うんだ。これほど多彩な才能がバンドにいたんだということを表していると思うね。ルイについては初めからそういう風に見ていた。実際、彼がワン・ダイレクションの曲では一番ソングライティングのクレジットが多いんだよね。驚く人も多いと思うけど、彼が曲のことを考えている時は本当に没頭している。彼の最新作は本当にいいアルバムだと思うよ」
――今回のプロジェクトでより彼のことを知ることになったと思うんですけど、一番驚かされた一面ってどういうところでしょう?
「彼の成熟ぶりだね。まだ29、30歳くらいだったのにずっと歳上みたいな感じだった。人生経験や彼が経験せざるを得なかったこと……妹を失ってしまったこと、あるいはあのバンドにいたという経験だけでもすごいことだし……深みのある人なんだ。それも驚きだったね。もっとも、彼に何を予想していたのか自分でも分からないところがあるんだけど、興味深かった。だからこそ、映画を作ることができた。彼の深みのおかげだよ。それに彼には言いたいことがあった。多くの人は彼がボーイ・バンドにいたということであまり彼の才能に目が向いていなかったかもしれない……ともあれ、深い会話をいろいろしたよ。人生についてとか、彼の価値観とかね。彼は今までの30年間の中で人生を何周もしたんだ」
――本作の一つの大きな印象として、インタビューでルイ・トムリンソンが非常に赤裸々に語っている印象を受けたんですよね。その点で、今、かなり深い話をしてきたということでしたけれど、工夫されたことはあったのでしょうか?
「いや、初めから特に何もなかったよ。話題にしてはいけないこともなかった。どんなことでもあらゆることが話題になった。パーソナルな話も含めてね。何でも撮って、最終的にそれらをどう使うのかを話し合ったくらいかな。彼は僕がその映像をどう映画に使うのか、どういう見せ方をするのか、その見せ方で自分は大丈夫なのかを知りたがっていたんだ。僕は人好きで、いつも人と仲良くしてきた。それが僕のスキルの一つだ。人と話すのも、新しい人に出会うのも好きだね。僕とカメラしかないから、結構長い間やってきた訳だけど、カメラの存在を忘れてしまうことがあるんだ。だから、普通の会話みたいになる。人と仕事をする時はいつもこう言うんだ。『僕たちはただ一緒につるむだけだ』ってね。ただ、僕がカメラを持っているだけでね。それによってよりパーソナルなものを撮ることができる。でも同時に、ワン・ダイレクションのメンバーだからこそ、彼はカメラと一緒に成長してきたし、カメラの前でも自然体でいられるんだ。彼はたくさん考えるし、言いたいこともたくさんある人だから、僕にとっては気が楽だね。普通に話せばいいだけだから。じっくり腰を落ち着ければ、何時間だって、何年だって、いるんな話題で話し続けることができるんだ。絆ができて、とても親しくなったからね。それが映画にも表れていると思う。この映画を作るのは最高に楽しかったよ。彼と仕事する経験も素晴らしかったし、軌跡が発展していって、1歩進むたびに状況が大きくなっていくのを垣間見るのも楽しかった。ツアーなんかでも、彼がステージに出ていく頃には……アメリカ・ツアーの会場をシアターにしたのは、彼がオーディエンスがどんななのか見てみたいと考えていたからだったと思う。いきなりビッグな会場にしないで、どんな感触かを知るためにね。単独ではツアーしたことがなかったわけだから。それでアメリカ・ツアーに出た訳だけど、なかにはキャパ2,500人程度のところもあった。大半はそれより大きかったけどね。その後、ヨーロッパを回ったときは、需要が高かったということで、会場がアリーナにアップグレードされていた。その次に南米を回ったときは、アリーナ3日間もあった。全部1回のツアーでだよ? クレイジーだよね。現場でその様子をすべて捉えることができたのは、本当に素晴らしい出来事だったし、彼のキャリアの素晴らしい時期でもあると思う。彼はある境地に辿り着いた。あとはもう進み続けるだけだね。この映画を観た人が、彼の生業や、彼がその生業にいかに秀でているか、彼のショウがどんなに楽しいかを知ってくれることを願っているんだ」
――本作の中でルイ・トムリンソンは「自分は一般人である」というのを強調していますが、あなたが見た実像からもそれは感じますか?
「そうだね。それが彼の素晴らしいところだよ。初めて出会った時からそうだった。彼は理不尽なところが一切ないんだ。本当に誠実で……セレブ・ワールドに巻き込まれていない。何はなくともノーマルでいることを強く望んでいて、できるだけノーマルな生活を送りたいと思っている人なんだ。だからこそオリヴァー・ライトも彼とずっと一緒にいる。みんなと同じようにノーマルな生活を送っているよ。僕はワン・ダイレクションを取り巻くクレイジーさも見てきた……ワン・ダイレクションのファン、彼のファンの熱心さをね。彼はその状態も多いに楽しんでいる。ファンのことは大好きだし、熱心に慕われていることも最高だと思っている。でも、映画の中でジェームズ・コーデンの番組に出たときもそうだったけど、あの時彼はあの手の番組に出たのが久しぶりだったこともあって、ある種の『ペルソナ』になりきらないといけなかったのが面白かったな。何かのキャラクターを身に着けるような感じ。というのも、彼の世界の中では、彼はただのノーマルな人、ただのルイだから。あるいは『ルイス』かな。オリヴァー・ライトは彼を『ルイス』って呼ぶんだよね、学校でそう呼ばれていたから。彼が友だちといる時を見ていると、本当にノーマルでほほ笑ましいよ。この映画は、結局はヒューマン・ストーリー、ある人間の『旅』を描いたものなんだ。だからこそ普遍的な内容になっているんだと思う。ファン向けなだけじゃなくてね。もちろん、観て夢中になってくれるのはファンだけど、ファンじゃない人が観たとしても楽しめる内容になっているし、考えさせられるものがきっとある。僕たちが作ったものはクロスオーヴァーできて、必ずしもファンでなくても観ることのできるものだと思っているよ」
――家族を含めた周辺人物のインタヴューもこの作品ではふんだんに使われていますが、その時に気を遣ったことはありましたか?
「彼のおじいさんとおばあさんとは、ライヴに来ていたことがきっかけで知り合いになったんだ。家に尋ねていって昔の写真を見るほほ笑ましいシーンがあるけど、あれも僕が頼んでそうしてもらった訳じゃなくて、自然に起こったことでね。セットアップしてああなった訳じゃなくて、すべてが自然の流れで発生したことなんだ。面白い話があって、ルイとの仕事を始めるようになるちょっと前に僕の母が亡くなってね。彼のおばあさんは僕の母を思い出させるところがある。僕たちは二人ともイングランド北部出身だし、おばあさんは本当にすてきな人で、あたたかみを感じたんだ。同時に生活の中に受け入れてくれて、撮影をさせてくれるというのは責任も感じるね。結局は彼らの生活を表に出す訳だから。しかも、極めてパーソナルなストーリーを僕と共有してくれて、それがグローバルな規模で消費されるんだからね。そうすることの責任を僕は感じている。そして願わくは……彼の家族が映画を観たかどうか僕は確信が持てないけど、気に入ってもらえることを願うよ(笑)」
「きっと気に入ってくれるとは思うけどね。うん。あの家族に捧げる素敵な作品になっていると思うから。本当に素敵な家族で、ルイの強さや人柄はここから来ているんだなとつくづく思う。残念ながら彼のお母さんには会えなかったけど、話を聞く限り、素晴らしい女性みたいだしね。とても強いレディーで。そのお母さんが彼に身に着けさせた強さがあるから、彼は実年齢より成熟した大人なんだと思う。あの家族を知ることができたことを光栄に思うよ。イギリスのプレミアで彼らに会えるのを楽しみにしているんだ。彼のおばあさんにハグしたいね。そうなったら結構グッとくるんじゃないかな」
――本作はスタッフやファンのことも作品の中で大切に扱っている印象があります。それは他のミュージック・ドキュメンタリーだとカットされてしまう印象というか、あまり見られないことなんですけども、スタッフを大切にしたいという気持ちは結構あったりするんでしょうか。
「僕は自分がこういう仕事をできること、そしてやり始めて何年も経った今も続けていられることをとても光栄に思っている。ネットフリックスなどのストリーミング・サービスが台頭したおかげで、この手の映画の大きなプラットフォームができた。今では世界中の映画館で上映されていて、人々がドキュメンタリーを観に映画館に足を運ぶようになっている。ネットフリックスなどのストリーミング・サービスが始まった当初は、みんなハリウッド映画とかそういうのを見るために会員になるんだろうと思っていた。でも、ドキュメンタリーはシリーズものと同じで、それにみんな興味を持ってくれている。思ったより影響力もスケールもインパクトも大きいのが興味深いね。音楽ドキュメンタリーとしても冥利に尽きるよ、何年もかけてずっと撮影してきたからね。リアム・ギャラガーの映画も10年以上かけて撮ったんだ。もしかしたらもっとかかったかもしれないけど、映画にする意図で撮っていた訳ではなかった。彼がビーディ・アイでアルバムを作っていたところから始まって、その後、彼がソロになったときは、YouTubeのコンテンツ用に小さなドキュメンタリーを作っているような感覚だった。それから彼が洋服のブランドを立ち上げた時もそれを撮った。その後、もう1枚アルバムを作って……そんな中での彼のパーソナルな部分も目の当たりにしていたんだ。バンドが終わってしまったり、離婚したり……それからスタジオに入って新しいアルバムを作った。彼と一緒にスタジオに入った時は、みんなが嘲笑していたのを憶えているよ。どうせ大した作品にはならないだろう、ビーディ・アイと似たような感じになるんじゃないか、とかね。でも、そこで魔法が起こったんだ。『アズ・ユー・ワー』は素晴らしかったし、ファンもできて……突如として自分がそのストーリーの中にいることに気づいた。その一部始終の瞬間をそれぞれ撮影できていたからね。ルイについても、これはいずれ映画になるだろうということが分かっていた。ただ、彼のストーリーの中で何が起こることになるのか、どういう経路をたどることになるかは分からなかった。彼があのバンドにいてああいう経験をした、とか、そういう断片的なことは知っていても、ストーリー自体は自然発生的に発展していくものだからね」
――今後、ルイ・トムリンソンにはどんなキャリアを歩んでいってもらいたいと思いますか?
「彼はさらにどんどん良くなっていくと思うよ。ファースト・アルバムとセカンド・アルバムを聴いて、彼がこの2作を作った時点でどんな状況だったか、彼自身がアイデアに対する自信を深めたことを考えると、そう思う。例えば、これから行うツアーも素晴らしいものになるんじゃないかな。セットリストの中の新曲も素晴らしいからね。バンドを観る時もいつもそうだけど、ファーストとセカンドを較べて、レパートリーも増えているのを見ていると……彼は強力な状況が続いていくような気がする。彼はパフォーマーとしてもさらに良くなっているし、ショウも音楽もさらに良くなって、この調子で進んでいくと思うね。このアルバムを作ることで彼が感じた自由が、次のアルバムでさらに発展していくんじゃないかな。ワン・ダイレクションにいたメンバーにとってソロ活動はいつだって大変だよ。あまりに大きな存在だったから、何をやってもグループ時代と較べられるし、クリエイティヴ面でも、ボーイ・バンドという概念の中で許されたことの縛りから自由になってソロ・アーティストになって、自分の方向性に従わなきゃならないからね。でも、彼はこの調子で進んでいくと思うね。もし、僕がワン・ダイレクションのファンだったら、いや、そうじゃなかったとしても、音楽ファンでこの映画を観たら、僕もコンサートに行って、どんなものか体験したいと思う」
――最近、ルイ・トムリンソンのインタヴューを読んでみても、彼はハリー・スタイルズの成功もすごく冷静に捉えている印象を受けたんですけど、あなたはどう思いますか?
「彼にとって初めは大変だったんじゃないかな。一緒に曲を出したりツアーをしたりしていたのが、ルイはプライベートでいろいろあったから暫く曲を出すことができなかったし、嫉妬とは思わないけど、フラストレーションを感じていたと思う。自分も出したいと思っていたんじゃないかな。それは彼自身の中での比較だけど、今は自分も作品を出して成功しているからね。出すことさえできればうまくやれる、素晴らしいものにすることができるという確信は持っていたと思う。彼も映画の最後の方で『僕はこうなってしかるべきだと思う』と言っていたけど、彼は自分を他人と比較する必要がないんだ。彼のやっていることは彼独自のものだからね」
――リアム・ギャラガーも含めて、あなたは音楽ドキュメンタリーを多数作られてきているんですけど、その中で最も大切にしていることと言ったらそれは何でしょうか?
「さっきのクルーの話じゃないけど、僕が作るものにはすべてオーセンティシティがあるんだ。その人が本当にすぐ傍にいるような気がするリアル感がある。僕が実際傍にいたからね。それで気づいたんだけど……僕はポール・マッカートニーと15年、ジャミロクワイとも長い間一緒に仕事をしていた。リアムとも長い間仕事をしたし、カサビアンともそうだ。彼らを撮っているうちに、どこかの時点で『これは最終的に映画になるな』と気づいたんだ。リアムの時はそう思わなかったけどね、最初の作品だったから。あの映画を作っていた時、エイミー・ワインハウスの『AMY』やオアシスの『スーパーソニック』みたいなドキュメンタリーの大作はみんなレガシーが題材だった。既に大きく話題になっていた、過去に起こったストーリーを伝えるというものだったんだ。リアムの映画はその時々に起こったことを取り上げていたから……レガシーとどう勝負するか?というのがあった。ああいう映画はものすごくビッグで、人々にとって本当に意味のある作品だからね。それもあって、僕はリアムの映画を作る時にとても心配だったんだ。ただ、公開されてから思ったのは、レガシーと勝負するにはハートが必要だということだった。自分の映画の作り方がかなりユニークなことにも気づいた。僕の仕事は一人の人間としてのハートが前面に出ているんだ。この映画にはそのオーセンティシティと誠実さが引き継がれている。とにかくリアルであることが必要なんだ。つまるところ、これはヒューマン・ストーリーだからね。僕たちはただの人間だ。ただ、人生だったり、仕事だったり、何かに興味を持っている人の映画を作っているだけでね。最終的には僕が興味を持っているのはその人のありのままの人となりだ。それこそが人の心を惹きつけるんだと思う。この映画を観てもらえれば、僕が撮っている人たちの中に、観る側が自分自身のひとりの人間としての特徴を見いだすことができるかもしれないね。エンタテインメントのために人から何かを引き出そうとか、利用しようとか、操ろうとかそういう気はない。こういう映画を作る時の撮影は映画の制作過程の半分くらいにすぎないんだ。他に編集過程とかがあって、僕には素晴らしいエディターがついてくれている。その人は作り方を心得ているから、素材を渡して希望を伝えて、カットしたりしながらじっくり一緒に編集していく。プロデュースを手掛けてくれたエイミー・ジェームズも一緒にね。彼女は大活躍だよ。あらゆる許可を取るのも担当してくれているし、署名をもらうとか、そういう表には出てこない部分を手伝ってくれているんだ。ただ、映像を撮影する実際のプロセスは僕一人で担当している。それが僕の映画の作り方のユニークなところだね。それがこの映画のパーソナルな、生々しい感触にも表れていると思う。僕の撮影の仕方というのは……僕は必ずしも自分のことをカメラマンだとは思っていないんだ。実際の撮影ではカメラから離れていることもある。ただ、友だちとつるんでいるだけみたいな時もある。仕事的な感覚はあまりないね。ただ楽しんでいるだけで。もちろんタフな時もあるけど、こういう仕事ができて自分は恵まれていると思う。旅することもできるし、人と出会うこともできるしね。僕は人が好きなんだ。昔からずっと」
――あなた自身のことも聞きたいんですけれども、ロニー・ウッドのプロジェクトからキャリアが始まったと読みました。どういう経緯だったのですか?
「ある人と出会ったんだ。僕はビール・フェスティヴァルでウェイターとして働いていたから、レーダーホーゼン(ドイツのチロル地方の革製半ズボン)を穿いたり、ヘンな帽子を被ったりしないといけなかった。20歳か21歳くらいの頃だよ。そのビール・フェスティヴァルを主催していたのがザ・ミーン・フィドラー(※現フェスティヴァル・リパブリック)という会社でね。レディング&リーズ・フェスティバルも主催している、大規模なイベントをやる会社なんだ。そこで出会った友人に、『僕のところで働かないか』と誘われたんだ。それでローディみたいなものになって、そういうショウのステージ・クルーの仕事をした。その後、彼はミーン・フィドラーを離れて、ロニー・ウッドの息子と仕事をするようになったんだ。ロニー・ウッドの息子のジェイミーとね。ジェイミーはザ・ローリング・ストーンズのバックステージや楽屋を担当する会社を立ち上げたのが発展して、いろんなコンサートやイベントに家具なんかを調達するようになっていた。僕の友人はそういうイベントの監督として雇われたんだ。僕はその下で働いていた。ここでもクルーとして、ビッグなパーティーなんかを担当していた。パーティでジャミロクワイなんかのアーティストに演奏してもたってね。そんな中、とある映画監督に出会って、大学を卒業したばかりだった僕は彼に自分の作品を見せたら『これは本当にクールだな。君はきっと素晴らしい仕事をするようになるよ』と言ってくれた。卒業していたこともあって、そういうパーティーを運営するよりも撮影したほうがいいんじゃないかと勧めてくれたんだ。企業用のビデオを作ったりすればいいんじゃないかと。それで、そういう仕事をしていたら、ロニー・ウッドがソロのライヴをやった。シェパーズ・ブッシュ・エンパイアでガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュとか、ザ・コアーズのアンドレア・コアーも出演していたんだけど、その時、僕はロニーの家族を知っていたから、DVD向けに舞台裏のドキュメンタリーみたいなのを撮らないかと言われたんだ。それで『撮る』と言ったよ。当日のことを憶えている。ロニーがサウンド・チェックを終えて、僕が彼の楽屋に入りたいと思って、彼の息子に『入れる?』と訊いたら『もう少し待って。様子を見計らうから』と言われた。でも、僕はドアをノックしたんだ。そうしたら、ロニーがドアを開けて、僕のことを知っていたから、『おいで』と中に入れてくれた。僕は部屋の片隅にいて、他にはロニーとスラッシュもいた。(ファッション・フォトグラファーの)マリオ・テスティーノが写真を撮っていた。僕は壁にハエみたいに引っ付いて、その瞬間を撮っていたんだ。そこには20分くらいいたかな。特に言葉も発さずにすべてを撮って『この部屋に居合わせるなんて、なんて素晴らしいことなんだ!』と思いながらね。部屋を出ていくときに、『これが僕のやりたいことだ! 最高じゃないか』と思ったのを憶えているよ。彼のライヴは6人のカメラマンで撮った。それを全部繋ぎ合わせる作業は僕にさせてくれた。ソロのライヴで彼はドイツの小さなレーベル所属だったし、ザ・ローリング・ストーンズみたいな大ごとじゃなかったから、僕にそんな機会が回ってきたんだ。その後は僕のことを気にかけてくれていた師匠みたいな人がいたんだけど、ある時電話をくれて、『僕はカイリー・ミノーグのツアーのライヴ・ディレクターなんだ。6週間後、ツアーの終盤にマンチェスターに行く。最終公演でDVDの収録をやるから、小さいカメラを1つ担当しないか? 走り回って断片的な動画をやる役なんだけど』と言ってくれた。僕は『素晴らしいですね! ぜひ6週間後にお会いしましょう』と言って電話を切るべきだったのに『素晴らしいですね!でも、僕はライヴが観たいんです』と言ってしまった。そうしたら『明日はカーディフでやる』と言う。マンチェスターから車で4時間くらいのところだから、『ゲストリストに載せてください。ライヴを観に行きます』と言ったよ。それで僕は車を走らせて、現場ではミキシング・デスクの後ろに陣取ってライヴを観ていた。そうしたら1人の男が僕の隣に座ってきて『君は誰?』と言うんだ。『チャーリー・ライトニングです。マンチェスターで、DVD撮影のカメラを1台担当します』と言ったら『そうか、いいね。今までどんな仕事をしてきたの?』と訊かれた。『ロニー・ウッドのDVDを撮ったばかりです』と言ったら、『僕はカイリー・ミノーグのクリエイティヴ・ディレクターのウィリアム・ベイカーだ。彼女のドキュメンタリーを撮る人を探しているんだけど、やる気はある?』と言われたんだ。未経験なのにだよ? 僕は機会を得るという意味で本当にラッキーだった。でも、トリッキーなことがあって、機会を得ることの一部はやっぱり運だ。だけど、チャンスをもらったら、そこでしっかり仕事をしないといけない。次のチャンスを得るためにもね。僕は仕事が続いて本当にラッキーだった。『6週間後に会おう』と電話で言われて、次の日に車で現場に行っていなかったら、今みたいなキャリアが展開していたかどうかは分からない。カイリー・ミノーグと仕事をするようになって、これも彼女が僕といるのを居心地いいと思ってくれたからなんだ。ツアーが終わったら電話がかかってきて『彼女の下着CMを撮らないか』と言われてね。この時も僕と彼女と、ヘア・スタイリストとクリエイティヴ・ディレクターしかいなかった。すごく素敵なホテルの部屋で、下着姿のカイリー・ミノーグを撮ったんだ」
「他にもレコード会社に勤めている男の友だちがミュージック・ビデオの担当者の女性に引き合わせてくれたりした。DVDを見せようとしたけど、当時は黎明期で、DVDを再生できるのが彼女の上司の部屋だけだったんだ。カイリー・ミノーグの映像を見せたら、彼女は出ていってしまって、上司と2人きりになってしまった。そうしたら、その日は木曜日だったんだけど、その上司の彼が『火曜日の予定は?』と言ってきてね。『ウエストライフがミュージック・ビデオを撮影するんだけど、その舞台裏を撮ってくれないか』と言われたんだよ。いわゆるCDに収録されていたエンハンスト映像というやつだよね。当時はビデオ撮影に2日間くらいかけて、僕はすべてを撮った。『これだけコンテンツがあるから、このくらいの長さのものを作ることができる』とアピールしたのが良かった。写真も自分で撮ってね。それが巡り巡って、ジャミロクワイと出会って、彼らのミュージック・ビデオを作ることができたんだ。『とにかく撮り続けて』と言われたから、舞台裏も含めてフィルム10巻分撮ったよ。写真を持ってジェイ・ケイの家に行ったら全部買い取ってくれた。それが『ダイナマイト』のジャケットになったんだ。それまで僕はフォトグラファーとして何か委託されたことなんてなかったのに。これもまたアクセスがあったおかげでこういうことになった。僕のキャリアはずっとこんな感じなんだ。その状況から最大限のものを生み出そうとしたんだ」
「そして、努めてクールにすることだね。嫌な奴になるんじゃなくて。でも、この業界には嫌な奴があまりに多い。エゴだらけだし……そんな訳で人生が変わった。ポール・マッカートニーと15年一緒に仕事していることもね。ポールは僕がより良い仕事をできるようにプッシュしてくれる人なんだ。僕に間違う余地を与えてくれるし、何か間違えても手助けしてくれる。『それはだめだよ、こうしてごらん』とか、『もっといいものを作ってまた持っておいで』と言ってくれるんだ。それに彼自身の振る舞いや謙虚さも……ポール・マッカートニーだというのにだよ。彼と仕事をしたことのある人がみんな言っていると思うけど、このチームの一員でいることは光栄だし、一緒にやっている人たちも本当に素晴らしい人なんだ。何のエゴもなくてね。他の人もみんなそうなんだ。本当に素晴らしいよ。ポール・マッカートニーのチームの一員として受ける扱いも素晴らしいけど、同時に、そういう扱いを受けられるのはポールのおかげだってことも忘れちゃいけない。自分の手柄じゃないんだ。とにかく真実に忠実であり続けることだね。いろんな人に『謙虚だなあ』『こんなにいろいろやってきたのに』とか言われるけど、僕自身はまだ前進していると思っている。46歳でこれだけの実績を持っていても、まだやるべきことがたくさんあるし、行きたいところもたくさんある。そういう状態でいられることが本当に嬉しいよ」
通訳:染谷和美
劇場公開情報
作品名: ALL OF THOSE VOICES
素材フォーマット: 2D DCP サウンド: 5.1
上映時間: 約104分
監督:チャーリー・ライトニング
出演:ルイ・トムリンソンほか
公開表記:3/22(水)TOHOシネマズ 六本木ヒルズほか公開
映画クレジット:(C)78 Productions Limited 2023
鑑賞料:2200円一律
公開劇場
札幌 ユナイテッド・シネマ札幌 3/22のみ
宮城 TOHOシネマズ 仙台 3/22のみ
新潟 ユナイテッド・シネマ新潟 3/22, 3/25 二日間限定
東京
TOHOシネマズ 日本橋 3/22〜3/25
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ 3/22〜3/25
ヒューマントラストシネマ渋谷 3/22〜3/25
吉祥寺オデヲン 3/22のみ
TOHOシネマズ 立川立飛 3/22のみ
神奈川
TOHOシネマズ ららぽーと横浜 3/22のみ
TOHOシネマズ 川崎 3/22のみ
千葉
TOHOシネマズ 流山おおたかの森 3/22のみ
TOHOシネマズ ららぽーと船橋 3/22のみ
埼玉 ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷 3/22, 3/25 二日間限定
栃木 TOHOシネマズ 宇都宮 3/22のみ
長野 長野グランドシネマズ 3/22のみ
静岡 静岡東宝会館 3/22のみ
愛知 109シネマズ名古屋 3/22, 3/25 二日間限定
大阪
TOHOシネマズ 梅田 3/22〜3/25
TOHOシネマズ なんば 3/22のみ
兵庫 TOHOシネマズ 西宮OS 3/22のみ
京都 TOHOシネマズ 二条 3/22のみ
岡山 TOHOシネマズ 岡南 3/22のみ
広島 TOHOシネマズ 緑井 3/22のみ
福岡 TOHOシネマズ ららぽーと福岡 3/22のみ
熊本 TOHOシネマズ 熊本サクラマチ 3/22のみ
更なる詳細は以下のサイトで御確認ください。
https://www.culture-ville.jp/allofthosevoices
ルイ・トムリンソン来日公演情報
4月17日(月)丸善インテックアリーナ(大阪市中央体育館)
OPEN 18:00/ START 19:00
S指定席¥17,000、A指定席¥14,000(税込)
4月19日(水)名古屋国際会議場センチュリーホール
OPEN 18:00/ START 19:00
S指定席¥17,000、A指定席¥14,000(税込)
4月20日(木)東京ガーデンシアター
OPEN 18:00/ START 19:00
S指定席¥17,000、A指定席¥14,000(税込)
更なる公演の詳細は以下のサイトで御確認ください。
https://www.creativeman.co.jp/artist/2023/04louistomlinson/
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.