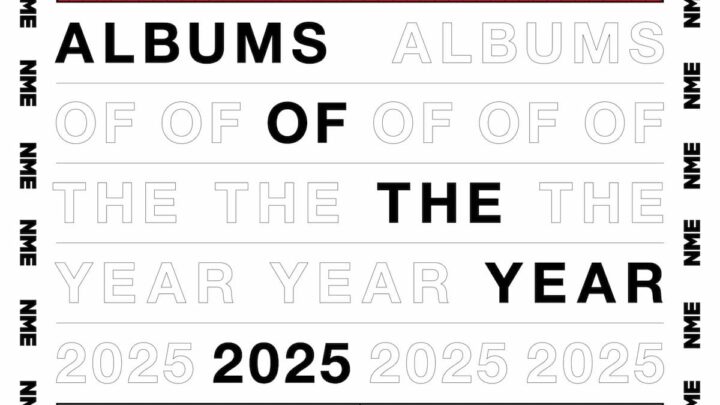10位 サンファ(7/28 RED MARQUEE)

Photo: Masanori Naruse / PRESS
ザ・エックスエックスと同じヤング・タークスに所属し、昨年12月には彼らの来日公演でサポート・アクトを務めたサンファ。タイムテーブル上では直前のグリーン・ステージでの彼らの終演時間と被っていた開演時間も、運命の悪戯か彼らのステージの終演が早く、RED MARQUEEへ駆け込んで開演時間に間に合ったオーディエンスは胸を撫で下ろしていた。”Timmy’s Prayer”で冒頭から観客の心を掴むと、代わる代わるカラフルに彩られるステージの上で4人編成のバンドが打ち出すビートはまさに圧巻の一言で、そのくぐもったセクシーなヴォーカルもさることながら、曲の力が強い。ハイライトは”Without”の4人での打楽器セッションで、上質なサウンドに留まらない躍動感をステージで実現していた。
9位 ジ・アマゾンズ(7/29 RED MARQUEE)
ギター・ロックの凋落が叫ばれる中、これほどまでに自信漲るアティテュードを持った新人バンドも珍しい。イギリスはレディングを出自とする4人組は、間違いなく自分たちの信じるロックンロールを真っすぐに搔き鳴らしていた。ステージ後方に映し出されていた、セルフ・タイトルを冠したデビュー・アルバムの燃え盛る車のアートワークの如く、レッド・マーキーのステージを熱く燃え上がらせていたジ・アマゾンズに、オーディエンスも万雷の手拍子でそれに応える。熱いアティテュードを冷ますことなくラスト曲に突入した彼らは、ここで「そうそう、俺たちはジ・アマゾンズって言うんだ。」と自己紹介。初めて自分たちを観たオーディエンスを確実に惹き付けたことを分かっていたのだろう。ラストに投下された“Junk Food Forever“に対する観客からのシンガロングが、それを紛れもなく証明していた。
8位 ゴリラズ(7/28 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse / PRESS
1日目のGREEN STAGEのトリを飾ったのは、ブラーでもソロでもフジの場に立ったことのあるデーモン・アルバーン率いるゴリラズだった。最新シングル“Strobelite”ではペヴェン・エヴェレットによるソウルフルな歌声が響き、“Sex Murder Party”ではジェイミー・プリンシプルとゼブラ・カッツによる色気とダークネスに満ちたショウが展開する。そしてその中心にいたのは紛れもなくデーモンであり、このダイヴァーシティに富んだステージを牽引してみせる。彼は歌いながら、鍵盤ハーモニカを吹きながら、あるいはファンへ手を伸ばしながら、ライヴに熱量を注ぎ込んでいく。代表曲“Clint Eastwood”では大合唱が起こり、ヴォルテージも最高潮に。ヴァーチャルとリアル、様々な音楽のジャンル、そうしたものを越境しながらヘッドライナーの役割に応えてみせる。デーモン・アルバーンの試合巧者ぶりに溢れたステージだった。
7位 LCDサウンドシステム(7/29 WHITE STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi / PRESS
海外ではメイン・ステージのヘッドライナーとして登場する彼らをWHITE STAGEのトリとして観られるなんて、なんという贅沢なのだろう。名作『サウンド・オブ・シルヴァー』の“Us v Them”でライヴが幕を開けると、すぐにLCDサウンドシステムならではのグルーヴに包まれる。続く“Daft Punk Is Playing at My House”は大喝采で迎えられ、“I Can Change”の浮遊感によってWHITE STAGE全体がゆらゆらと揺れる。ファーストからの“Tribulation”で再びギヤを上げた後は本編後半では9月リリースの7年ぶりとなる新作『アメリカン・ドリーム』からの楽曲も披露されていく。しかし、LCDサウンドシステムのサウンドはこんなにも身体を動かされるのに、心の奥底にも何かを残していくのだろう。アンコールでは“Dance Yrself Clean”の後に大名曲“All my friends”で締めくくられ、訪れた多くのファンも納得のステージだった。
6位 ファーザー・ジョン・ミスティ(7/28 FIELD OF HEAVEN)
雨の上がった夕暮れの時のフィールド・オブ・ヘヴンにスーツ姿で颯爽と姿を現したファーザー・ジョン・ミスティは、まるで連日出演しているミュージカルの冒頭の台詞を読み上げるかのように、手慣れた身振りで“Pure Comedy”からステージをスタートさせた。リリックを身振り手振りで体現する様はまさに「生粋の(ピュア)コメディアン」で、シンガーというよりもむしろ代弁者を演じる喜劇俳優そのものでもある。MCでもウィットに富んだジョークを飛ばしていく彼だが、“True Affection”での踊り狂う姿は愛に狂うロマンティックなセックス・シンボルだし、楽曲に応じて様々なキャラクターを体現する本物のエンタテイナーであった。圧巻だったのは日が暮れてからの演出で、美しくライトアップされたステージが、ファーザー・ジョン・ミスティによる現代喜劇のクライマックスを見事なまでに彩っていた。
5位 アヴァランチーズ(7/29 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse / PRESS
16年ぶりにアルバムをリリースした昨年のフジロックに出演予定だったものの、メンバーの体調不良で残念ながらキャンセルとなったアヴァランチーズ。緻密な構成のサンプリングミュージックを世に送り出している彼らとだけあって、ライヴではどのような姿を見せるのか。蓋を開けてみると、DJ、ギター、ボーカル、ラッパー、ドラマーという生音を全面的に押し出したバンド体制で、いい意味で期待を裏切るものであった。そのサウンドはおもちゃ箱をひっくり返したように色彩豊かなもので、愉快さとノスタルジーが同居している。観客を煽るパフォーマンスとメンバーの掛け合いは、音源では味わうことの出来ない臨場感を生み出し、背後には彼ららしくサンプリング映像が流れる。新譜・旧譜まんべんない選曲のセットリスト。最後の“Since I Left You”で会場は一気に沸き、観客は至極のメロディーと甘美な空気に酔いしれていた。
4位 ビョーク(7/29 GREEN STAGE)

Photo: Santiago Felipe / PRESS
時折挟む「アリガトウ」然り、50歳を超えた今も相変わらずチャーミングで、ビョークは何度観たってビョークで、相も変わらず期待を遥かに上回るパフォーマンスを私たちに魅せてくれた。オーケストラとアルカをDJとして引き連れて、最新作『ヴァルニキュラ』の一曲目“Stonemilker”で幕を開けたステージは、終始観客の目を離すことなく進んでいった。巨大なスクリーンに映し出された映像も相まって、まるで生演奏でビョークによる長編映画を鑑賞している気分になる。中でも後半の“5 Years“から立て続けに映し出された圧巻の映像美はステージ上のビョークの存在を一時忘れてしまうほど、観る者の目を釘付けにし、“Notget“で放たれた火花でオーディエンスの熱気は最高潮に達していた。最後を締めくくった名曲“Hyperballd“で打ち上げられた花火は、4度目のヘッドライナーを務めた彼女からの、21年目に突入したフジロックへの祝福の花火のようだった。
3位 クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ(7/28 WHITE STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi / PRESS
この日一番とも言える歓声に迎えられてホワイト・ステージに登場した彼らは、2曲目に早くも“No One Knows“を演奏して会場をいきなりの絶頂へと導くと、ジョシュ・オムの「アリガトウゴザイマス」に、もう日本では観られないんじゃないかと思っていただけに深い感慨を覚えてしまう。セミアコを搔き鳴らすジョシュ・オム率いるバンドが奏でるサウンドは一筋縄ではいかないものだが、ロックンロールの裏側を知り尽くしたこのバンドにしか鳴らせないサウンドを叩きつける。くぐもったディストーションを気怠そうに響かせているかと思えば、ハードロック的なリフを長時間反復させたりと、ステレオタイプ的なロックのショウからは逸脱したパフォーマンスが続いていく。メインストリームへのパロディに聴こえるロックンロールも、その根底に感じるのはロックンロールに対するジョシュ・オムの不滅の愛だ。金曜日最後のホワイト・ステージには、究極までにオーセンティックなロックンロールの音景が広がっていた。
2位 ロード(7/30 GREEN STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi / PRESS
なぜ弱冠20歳のこの人は、ポップ・ミュージックというものをこんなにも美しい形で具現化できてしまうのだろう。黒の衣装に下はスニーカーという出で立ちで登場した彼女だが、1曲目の”Tennis Court”が始まった瞬間に会場の空気は一変する。『メロドラマ』を書き上げた経緯を延々と話すときも、”Liability”の前に19歳で経験した初めての失恋について語るときも、ステージの淵に腰掛ける時もそこにいたのは紛れもない20歳のエラ・イェリッチ・オコナーその人だった。けれど、一度曲が始まってしまえば、そこに展開するのは完璧なフォルムのポップ・ミュージックだ。“Royals”も素晴らしかったけれど、ライヴのクライマックスを形作ったのは”Perfect Places”など、最新作からの楽曲だった。”Green Light”で観客を否応なしに踊らせていたその瞬間、ポップ・ミュージックから愛されているとしか形容できない神懸かった光景がそこには広がっていた。
1位 ザ・エックス・エックス(7/28 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse / PRESS
オープニングの“Intro”が流れるや否や、グリーン・ステージに広がる苗場の大自然と見事にシンクロしてオーディエンスを彼らの音空間へと誘っていく。3曲目にプレイされた新作からの“Say Something Loving”で彼らの遂げた音楽的な進化に感慨を覚えていると、会場もそんな彼らの成長を祝福するように、続くファーストからの“Islands”でさらに温度を上げていく。新旧の名曲たちが惜しみなく披露されていく中で、オリヴァーとロミーが終始楽しそうな笑顔を絶やさずにフロントに立っていたこと然り、バンドと並行して行われたソロが最終的にバンドに大きな影響を与えたジェイミーの単独DJ然り、彼らは「天才児」としての当惑の時期を抜け、1人1人が大人として向かい合う成熟した存在になっていた。それは内省世界から外界世界へと抜け出たようでもあり、ロンドン出身の3人組はその音楽的先鋭性だけでなく、肉体的なバンドとして今年のクライマックスを形作ってみせた。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.