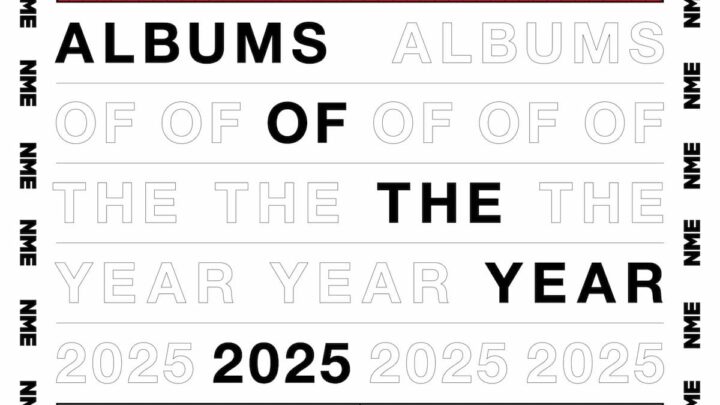10位 ベス・ギボンズ(7/27 GREEN STAGE)

Photo: Taio Konishi
裸足で登場したベス・ギボンズは首から提げているアーティスト・パスを外そうとするのだが、少しイヤモニとからまっているようだ。この一幕だけで彼女の人柄が伝わる。アーティスト然としたところはまったくない。しかし、希代の声を持っている。1曲目は初のソロ作と同じく“Tell Me Who You Are Today”で、バンドにはプロデューサーのジェームス・フォード自らが参加している。ストリングスの聴かせ方を含め、アンサンブルのクオリティはずば抜けている。“Burden of Life”、“Floating on a Moment”と続くが、ステージに満ちているのはベス・ギボンズへのリスペクトだ。彼女の歌と世界を壊したくないという風に繊細に音が鳴らされていく。中盤ではラスティン・マンとの“Mysteries”や“Tom the Model”も披露されるが、終盤に披露されたのはポーティスヘッドの“Roads”。98年の幻の来日公演を経て、「みなさんは優しい」というベス・ギボンズの日本語と共にその楽曲が演奏されたのは歴史的瞬間に他ならなかった。
09位 ザ・ラスト・ディナー・パーティー(7/27 GREEN STAGE)

Photo: Yuta Kato
やっと生で観られた。その感慨が何より強かったかもしれない。今回が初来日となったザ・ラスト・ディナー・パーティーだが、『NME』では昨年4月にリリースされたデビュー・シングル“Nothing Matters”から注目してきたアーティストだ。メンバーが“Prelude To Ecstasy”に乗って登場する形で“Burn Alive”から始まったライヴは、“The Feminine Urge”のライヴでしか感じられない熱量も、「新幹線で来ました」というベーシストのジョージア・デイヴィーズによる流暢な日本語MCも、新曲“Second Best”も、アビゲイル・モリスがステージを降りることになった“Sinner”のギターも、心待ちにしていたものをようやく観られたという思いが強かったのだけれど、ザ・ラスト・ディナー・パーティーのライヴを生で体験して最も痛感したのは、5人が揃った時の器のデカさだろう。それはちょっと圧倒的で、最後に披露された“Nothing Matters”を観ても、マーキュリー・プライズにノミネートされることになったファースト・アルバムが始まりに過ぎないと思わせてくれるものだった。
08位 フローティング・ポインツ(7/26 RED MARQUEE)

Photo: Masanori Naruse
フィルターのかかった一音目からしてフローティング・ポインツことサム・シェパードという人の存在を感じる。フィルターはどんどんと周波数を下げていって、低音が次第に厚さを増していき、そこに高音のビープ音が入ってきて、すっかりRED MARQUEEが彼の世界に染まったところに、ビートが入ってくる。このオープニングの時点で、磨き上げられたそのサウンドのクオリティの違いを意識せずにはいられない。その上で、フローティング・ポインツの音楽が特異なのはそのクオリティゆえに観客に内省をも促してしまうところだろう。だから、鋭いキックが入ってきても、お気楽なパーティー空間になることはない。近作のアートワークやビデオともリンクする映像と共に生命の鼓動にまで意識が及ぶような世界観があって、それは後半にレーザーの歓喜があっても変わらない。ザ・キラーズのステージが待ち受けているところもあって、最後の最後までは観られなかったが、俄然9月リリースの新作が楽しみになるステージだった。
07位 フォンテインズD.C.(7/28 RED MARQUEE)

Photo: Hachi Ooshio
フジロックからほどなくして来夏にフィンズベリー・パークで行われる大規模屋外公演が発表されたが、フォンテインズD.C.はここ数ヶ月でもスケールが急拡大している最中で、今回のフジロックはプレシーズン・マッチというか、だからこそRED MARQUEEで観られてしまうという破格の機会だった。しかも、グラストンベリーに近いパフォーマンスで、緑の照明にグリアン・チャッテン不在で始まった“Romance”然り、“Jackie Down the Line”、“Televised Mind”、“Roman Holiday”の3連発然り、バンドはフルスロットルで、来たるべきシーズンを見据えて、今までのキャリアを彩ってきた楽曲を披露していく。“A Hero’s Death”の後にはパレスチナへの姿勢も表明し、“Sha Sha Sha”は演奏されなかったものの、終盤には“Boys in the Better Land”も披露された。しかし、なんといってもバンドの今後を照らしていたのは最後の2曲で、“Favourite”と“Starburster”が予感させる未来はあまりに眩しかった。
06位 サンファ(7/27 WHITE STAGE)
ベス・ギボンズから駆けつけることになったので頭からは観られなかったのだけど、到着するやいなや、そのステージに驚かされる。デジタル機材をはじめ楽器類があたかも祭壇かのように並べられており、サポートのミュージシャンはさながら侍者のようだ。けれど、“Can’t Go Back”のパフォーマンスを観ている内にあながち比喩でもないのかもしれないと思えてくる。その機材を駆使して、音源で作り上げられた楽曲にライヴという場で新たな生命を吹き込んでいく所作はまさに儀式で、時折前に出てきて、ダンスを披露するサンファの姿はお茶目さがありながらも、神秘性をも感じさせる。“Stereo Colour Cloud (Shaman’s Dream)”から“Spirit 2.0”という最新作の流れも素晴らしかったけれど、白眉だったのは円陣パーカッションから披露された“Without”で、サンファというアーティストは儀式を形式として終わらせないために何よりも肉体性が大事だということを分かっていることが伝わってきた。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.
関連タグ