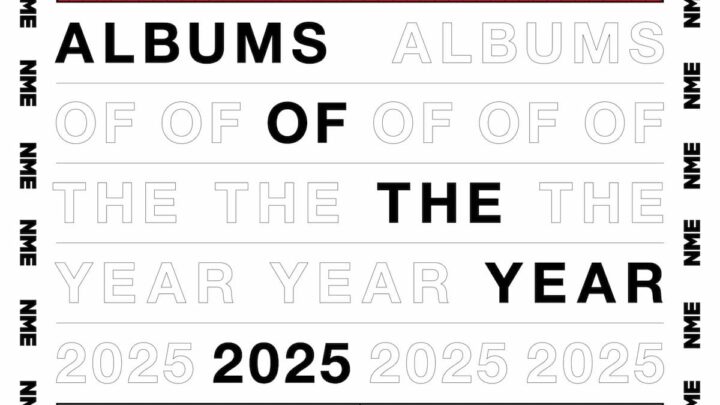15位 エリカ・デ・カシエール(7/26 RED MARQUEE)
単独公演も発表されたフリコのパフォーマンスを後にステージに向かうと、スツールに座って歌う本人と1人のドラム兼パーカッションというシンプルな編成に驚かされる。“Photo Of You”を経て、ピアノの旋律が流れ始めたところに人力のドラムンベースのリズムが入ってくると、観客からは歓声が上がる。最新アルバム『スティル』のリード・トラックだった“Lucky”が早くも序盤で披露される。キャッチーなコーラスも相俟って一つのピークをここで迎えるのだが、エリカ・デ・カシエールの音楽というのはシンプルなトラックをバックに、本人の歌とキャラクターに加えて、リズムが主役であり、だからこそこの編成になっているということが“Lucky”では如実に伝わってくる。そこからは『スティル』の曲を中心にキャリアを彩る楽曲が披露されていくのだけれど、固定カメラによるライヴ映像やフェイスタイムと同期してラップが入ってきたりと、映像がYouTube的で、それが彼女のキャラクターにもぴったりと合っていた。
14位 ジーザス&メリー・チェイン(7/28 WHITE STAGE)

Photo: Ruriko Inagaki
インドネシア発の3ピースであるアリのやわらかなグルーヴに包まれた後に待ち受けていたのは強いエフェクトのかかった硬質なリズムのシーケンスだった。1曲目は今年3月リリースの最新作からの“Jamcod”で、聴き込んだ曲というわけではないものの、こうした新しい曲でもジーザス&メリー・チェインらしさというものを感じる。それはこの日のステージに貫かれていたものだったと思う。キャリア全体に及ぶような様々なアルバムからの曲が演奏されたこの日のセットリストだったが、どの曲でもそこにははっきりと分かる彼らならではの記名性がサウンドに刻み込まれている。序盤で演奏された“Head On”でのジム・リードの歌い方も、“Happy When It Rains”のウィリアム・リードの一筆書きとも言えるギターも、“Some Candy Talking”の気だるさとキャッチーさもオリジネイターだからこそDNAレベルで組み込まれていて、『サイコキャンディー』の曲は決して多くなかったものの彼らの真髄を感じられるステージだった。
13位 グラス・ビームス(7/27 RED MARQUEE)

Photo: Yuta Kato
雨が降り出したこともあって、RED MARQUEEには多くの人の波が押し寄せてきて、テントの後ろまでぎっしりと観客で埋まる。かつてジョージ・ハリスン追悼コンサートのラヴィ・シャンカールを観て、大きな影響を受けたというラジャン・シルヴァ率いるグラス・ビームスだが、このバンドの存在を初めて知った時から、その真価が分かるのはライヴだろうと思っていた。ついにその機会が訪れたわけだけれど、その強度はさすがで世界のフェスティバルを唸らしてきただけのことはある。ルーツのインド的な旋律を使いながらも、バンドとしてのアンサンブルはロックで、反復がもたらす陶酔感はレイヴ的であり、3ピースが一丸となってそれを展開していく。“Rattlesnake”のようなダンサブルなトラックでは会場の熱を一段と上げながら、そうしたサウンド力学は終始一貫していて、最後は自ら積み上げてきたグルーヴの塔を破壊するかのようで、そのカタルシスは昼下がりのRED MARQUEEに大きな余韻を残していた。
12位 2manydjs(7/28 FIELD OF HEAVEN)

Photo: Yuta Kato
ガール・イン・レッドが終わってから駆けつけた感じだったので、観られた時間はそんなに長くはないのだけれど、久々に目にすることのできた彼らのパフォーマンスの醍醐味を感じるには十分だった。とは言っても、唯一の公式コンピがリリースされたのは22年前、そこからDJという概念自体もだいぶ変容したため、年齢層が高くなることは想定していたが、集まった人々は勝手知ったる様子だ。ダンス・ミュージックで土台を作りながら、反則とも言えるネタをマッシュアップしていくというスタイルだが、ウェット・レッグの“Too Late Now”あり、直前にヘッドライナーを務めていたクラフトワークへのオマージュありという中で迎えた後半のクライマックスは、ブラーの“Girls & Boys”からケミカル・ブラザーズという流れだったりしたのだが、最後の最後には日本のファンに向けたYMOの“Behind The Mask”という粋な選曲が待ち受けていて、唯一無二のミュージック・キュレーターとしての実力を見せつけてくれた。
11位 セレブレイション・オブ・ザ・ミーターズ(7/28 FIELD OF HEAVEN)
ジョージ・ポーター・ジュニアにとって5年ぶりの苗場だが、まずはダンプスタファンクによるセッションから始まった。ステージ左手のトロンボーンとトランペットが会場に熱を与えていく中で、アイヴァン・ネヴィルは観客にハンドクラップを求めていく。そして、いよいよレジェンドが登場して始まったのは“Hey Pocky A-Way”だった。ジョージ・ポーター・ジュニアは中央の椅子に腰掛けて「ハロー!」の声と共に演奏に入っていく。“People Say”も早々に披露されて、会場はさらに盛り上がりを見せることになる。その後はもちろん、ニューオーリンズならではの個々のメンバーによるソロなども展開されていことになるのだが、ステージ全体から感じていたのは開かれた空気であり、まさに名前通り“お祝い”であり、“継承”であり、“伝承”であるということで、その印象は“No More Okey Doke”や“Just Kissed My Baby”といった、その後に演奏された曲でも変わることはなかった。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.