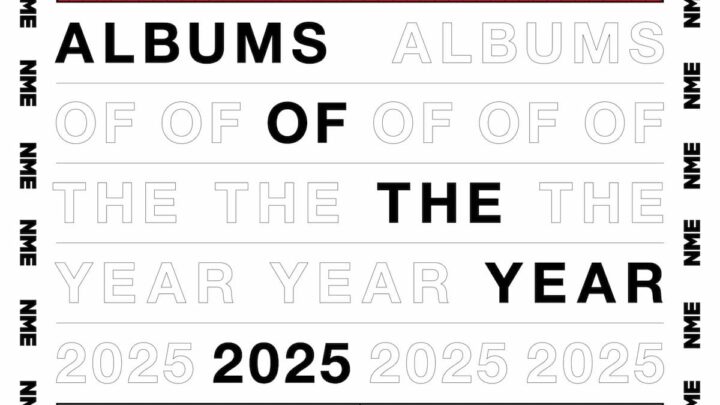15位 インヘイラー(8/20 MOUNTAIN STAGE)

Photo: SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.
新型コロナウイルスでライヴ・エンタテインメントがストップする直前に観たインヘイラーの初来日公演は新人バンドならではのどこにでも行ける可能性に満ちたものだった。何の色もついておらず、進むべき方向が決まっているわけでもなく、目の前には大海原が広がっている。そんなイメージを受けたのだけど、セカンド・アルバム『カッツ&ブルーゼス』を経た今回のライヴでも受けた印象はそれに近いものだった。もちろん、あの頃にはなかった風格のようなものも芽生え始めていたし、冒頭を飾った“These Are the Days”を初め、セットリストには新作の曲が加わっている。けれど、彼らは安易に「答え」を出すのではなく、様々な可能性に対して自分たちを開いておくことを重視しているように見える。最後に演奏された“It Won’t Always Be Like This”と“My Honest Face”、それらはやっぱり今なおイノセントな輝きを放っていて、このバンドのまだ見ぬ未来について思いを馳せてしまうものになっていた。
14位 ジェイコブ・コリアー(8/19 BEACH STAGE)

Photo: SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.
インヘイラーを終えてシマファンクに向かったのだが、間一髪で間に合わず、振り返ってみれば今年のビーチ・ステージで一番長く観られたのは、このアーティストだった。ブラーが終わってから観たのだけど、進行が遅れていたのか、このインストゥルメンタルの魔術師のステージを思っていた以上に堪能することができた。ある意味、何でもできてしまう人なので、エルヴィス・プレスリーの“Can’t Help Falling in Love”だろうが、クイーンの“Somebody to Love”だろうが、カヴァーであっても万人が楽しめるパフォーマンスに仕立て上げることは難なくできてしまう。後者ではオーディエンスを分割して、観客の声でハーモニーを作り、それで歌わせるなんていうこともやってのける。一方で7月にリリースしたばかりの“WELLLL”を演奏してソングライターとしての現在地を見せることも忘れない。最後は“In My Bones”で、ドローン群が脇に見える中で1日目を締めくくってみせた。
13位 サンダーキャット(8/18 MOUNTAIN STAGE)

Photo: SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.
黒の浴衣姿で陽気に登場した時点から明白だったが、すっかり日本仕様のライヴだった。歌詞に「東京」という言葉を入れてみたり、18歳の頃に初めて日本にやってきた時のことを曲間で振り返ってみたり、もちろんアニメ『ドラゴンボール』や日本の地名が登場する曲があったりと、他のアーティストとは較べ物にならない距離感の近さを感じさせてくれる。しかし、当然、彼のベースプレイは異次元のもので、手の届きようがない屈指の世界的ベーシストである事実も改めて突きつけられる。しかし、この日のライヴを決定づけていたのは今年3月に亡くなった坂本龍一の追悼セクションだった。バルセロナ五輪の開会式のテーマ曲だった“El Mar Mediterrani”を使った“A Message For Austin”を演奏した後、“Thousand Knives”をカヴァーする。“No More Lies”では軽やかな現在地も見せてくれたサンダーキャットだったが、日本のフェスティバルだからこそ大きな意味を持つパフォーマンスを見せてくれた。
12位 ウェット・レッグ(8/19 SONIC STAGE)

Photo: SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.
ナイル・ホーランのステージは惜しくも観ることができなかったのだけれど、こちらは前半のステージを観ることができた。ライヴは今年2月の単独来日公演と同じく、デビュー・アルバムでも冒頭を飾った“Being in Love”で始まり、2曲目では代名詞とも言えるシングル“Wat Dream”が早速投入されていく。リアン・ティーズデイルは2月の公演では足が大胆に見える衣装を着ていたのだが、今回のステージではニットキャップ風の紐付き帽を被っていて、季節感の逆を行くのが趣味なのだろうかなんて考える。“Supermarket”では飾らないキャラクターを見せつつ、“Convincing”ではギターを前面に出し、“Oh No”ではオーガニックなライヴ感を見せつけてみせる。そして、後半に差し掛かった“Ur Mum”ではお馴染みの絶叫パートもあったのだが、観られたのはここまで。ヘッドライナーのブラーの直前という事情がもちろんあったのだが、もっと多くの観客に観てもらいたいパフォーマンスだった。
11位 ゲイブリエルズ(8/19 MOUNTAIN STAGE)

Photo: SUMMER SONIC All Copyrights Reserved.
かつて『アメリカン・アイドル』に出演したもののキャリアを見失った黒人シンガーが合唱隊をやっていた時にヴァイオリニストの作曲家とミュージック・ビデオの監督もやるDJと出会って、こんな音楽が生まれるとは出来すぎな話だと思ったが、ライヴを観てすぐに彼らに肩入れしたくなる気持ちが分かってしまった。ドゥーワップやゴスペルといったジャンル/形容で語られることの多い彼らだが、序盤に披露された“Taboo”など、そのサウンドは実にオーセンティックなもので、“Love and Hate in a Different Time”には一筋縄ではないかない気品がある。そして、なによりステージ上の全員がヴォーカリストのジェイコブ・ラスクの歌に全幅の信頼を置いていることが伝わってくる。ティナ・ターナーの“Private Dancer”という技ありなカヴァーも披露しつつ、個人的に白眉だったのは“One and Only”で、初めての日本でもまったくブレないライヴを見せてくれた。
Gorillaz - The Mountain (Casebound Book with Studio Album & Live Mystery Show) (輸入盤)
Amazonで見る
価格・在庫はAmazonでご確認ください
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.
関連タグ