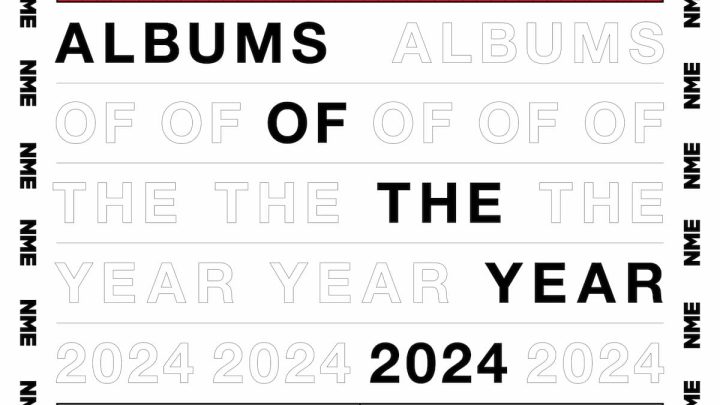Photo: Santiago Felipe / PRESS
NME Japanでは大盛況だった今年のフジロックフェスティバルでベスト・アクトの1~20位を選んでみました。とはいっても、あれだけ多くのアーティストが出演するフジロックです。すべてのアーティストを観ることはできません。なので、あくまで独断で、編集部で観たいと思ったアーティストのなかから、議論を重ねて、このランキングを作成してみました。みなさんのベスト・アクトとぜひ較べてみてください。
20位 ドクトル・プラッツ(7/28 WHITE STAGE)
初日となる金曜日のホワイト・ステージの一番手として登場したのは、前夜祭でもフジロックの開幕を待ちきれないオーディエンスの心を満たしてくれたスペイン出身のバンド、ドクトル・プラッツだった。祭りの国からやってきたラテン・バンドは、“Ara!”から今年のホワイト・ステージ最初のパフォーマンスを開始すると、トロンボーンとトランペットが前面に打ち出される陽気なサウンドで正午にすらなっていない会場をルール無用のお祭り状態へと変貌させていく。恐らく彼らの音楽を初めて聴いたオーディエンスも少なくなかったはずだが、確かな演奏力を以て最初から最後までオーディエンスを惹きつけていた彼らのフィエスタはアヴィーチー“The Nights”のカヴァーでピークを迎え、これからやってくる3日間への期待感に十二分に応えてくれた。
19位 アルカ(7/28 PLANET GROOVE)
初日の興奮冷めやまぬ中、深夜のレッドマーキーに姿を現したアルカ。ハイヒールを履いてステージに登場したアルカの身を包むのは、ピンクのタンクトップに下はボンテージのような衣装である。あらゆる境界を超えていく、紛れもない「アルカ」がそこにはあった。VJを務めるのはビョークやFKAツイッグスらとの仕事でも知られる相棒のジェシー・カンダだ。彼が創り出す攻撃性のある映像美に合わせて音楽を繋ぎ合わせて行くアルカの姿は実にエキセントリックなのだが、同時に見えて来たのはエンタテイナーとしてのアルカの矜持だった。無秩序なサウンドを次々に放り込んで来たかと思えば、時折挟まれるダンサブルな音楽ではターンテーブルの前で妖艶に踊り出す。自身の抱え込む抑圧を映像や音楽、ダンスで見事に体現しながらも、観客に楽しんでもらおうとするエンターテイナーとしての覚悟を見ることができた。
18位 ラグンボーン・マン(7/28 GREEN STAGE)
まだ雨が降り出す前の昼下がりにグリーン・ステージに登場したのは、今年のブリット・アウォーズで批評家が選んだ新人賞を受賞し、BBCサウンド・オブ・2017でも2位となったラグンボーン・マンだった。デビュー作が本国イギリスでは今年の上半期を代表する作品の一つとなっている彼だが、こういうアーティストが売れるのも今のイギリスの一つの側面かもしれない。鼻ピアスに腕にタトゥーがびっしりと彫られた恰幅のよい身体、しかしその声で歌われるのは深みを持った上質なポップ・ミュージックだった。観客の数はステージの大きさに対していまひとつだったけれど、“Skin”などのヒット曲では、前方の熱心な観客からはシンガロングも上がる。クライマックスの“Human”はもちろん、最後の“Hell Yeah”に至るまで、観る者の心に刻まれるヴォーカル体験になったはずだ。
17位 マギー・ロジャース(7/30 RED MARQUEE)
ファレル・ウィリアムスに見出され、今年2月にデビューEPをリリースしたばかりにもかかわらず、既に欧米で軒並み高い評価を得ている彼女を大歓声で出迎えたレッドマーキーからは、ここ日本でも彼女が高い注目度を集めていることが窺い知れた。白を基調としたカラフルな衣装に身を包んで登場したマギー・ロジャースは、デビューEPの一曲目に収録された”Color Song“から初来日のステージをスタート。唯一無比の透き通った歌声はもちろん、力強いダンスで観客を魅了してく姿からは、新人らしからぬ風格が漂っていた。デビューEPの楽曲を中心としたセットリストに、ニール・ヤングの”Harvest Moon“のカヴァーが組み込まれていたのもいい。もちろん最後はアンセム“Alaska“でステージを締め括り、オーディエンスをこの上ない甘美な空間へと誘っていった。
16位 ライ(7/28 FIELD OF HEAVEN)

Photo: Tsuyoshi Ikegami / PRESS
演奏が始まりマイク・ミロシュの歌声が発せられた瞬間にオーディエンスの神経は全て「聴覚」に集まったのではないだろうか。中性的な透明感のある美声で歌われる”Verse”でショウがスタート、ストリングスを含む6人編成で奏でられるオーガニックでありながらサイケデリックなサウンド、控えめなライティングとの相乗効果でFIELD OF HEAVENは更に神秘的な空間となった。チェロ奏者が楽器をトロンボーンに持ち替えた”Last Dance”では躍動的な側面も見せるが、あくまでも上品で心地よいパフォーマンス。2013年に続く2度目の出演となった今回、FIELD OF HEAVENのトリを新旧の楽曲を交えながら独自の世界観で優しく支配したRHYEがこの日の最後の曲”It’s Over”を終えステージを降りた後も、オーディエンスはしばらくの間ヘヴンを離れることなく惜しむように美しい余韻に浸っていた。
15位 スロウダイヴ(7/30 RED MARQUEE)
3日目も中盤に差し掛かり、苗場の山を歩き続けて少し疲れてきたオーディエンスを癒してくれたのは、レッドマーキーに響いていたスロウダイヴによるディストーションのシャワーだった。オープニングを飾ったのは、22年ぶりとなるセルフ・タイトル作からの“Slomo”だ。ニール・ハルステッドとレイチェル・ゴスウェルが刷新されたハーモニーを奏でていることに思わず目頭も熱くなる。もちろん今なおシューゲイザー・シーンのクラシックとして君臨する“Catch the Breeze”も、“Avalyn”も、“Slowvaki Space Station”も、“When The Sun Hits”も披露されていく。これまでの儚げなエッセンスはまったく衰えることなくアップデートされており、彼らの新しい姿を見届けようと詰め掛けたオーディエンスたちを望み通りのエクスタシーへと導いてくれた。
14位 キャットフィッシュ・アンド・ザ・ボトルメン(7/28 WHITE STAGE)

Photo: Yasuyuki Kasagi / PRESS
常に熱いライヴをやるバンドだが、それにしてもこの日のキャットフィッシュ・アンド・ザ・ボトルメンは熱かった。フジロックへの出演がキャンセルとなり、日本公演としてはライヴハウスでの公演が続いていただけに、バンド側もようやくフルスケールの自分たちを見せられるという手応えもあったのかもしれない。だんだんと日が落ちていく美しい時間帯だが、いきなりファースト・アルバムの冒頭を飾る“Homesick”と“Kathleen”を叩きつける展開からして圧倒されたが、フロントマンのヴァン・マッキャンはロックンロールの黄金比が今の時代でも信じて疑わない。その姿はまるで獰猛な獣のようだ。“Soundcheck”や“7”といったセカンドの佳曲を中盤に挟みながら、最後は再びファーストからの“Cocoon”と“Tyrants”で締め。しかし、応援したくなってしまうバンドだ。
13位 メジャー・レイザー(7/30 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse / PRESS
「ディプロ」と書かれた白い帽子を被ったディプロとその脇を固めるジリオネアとウォルシー・ファイアが、3日間でまだ悶々としていた人々の消化不良を一手に引き受けていた。終盤にジャスティン・ビーバー版”Despacito“からのエド・シーランの“Shape Of You“に続けて“Lean On“を投下してくるディプロのやりたい放題さ加減に脱帽するのは言うまでもないが、特筆すべきは野蛮とも形容出来るとことんまでに肉欲的な彼らのパフォーマンスである。ダンサーがビキニ姿で登場したかと思えば、紙吹雪は飛んでくるし、ディプロは「Tシャツを脱げよ」と観客を煽る。そう、この3日間で不足していたのは、私たちの根底にあるこのワイルドな欲求だったのだ。メジャー・レイザーは最終日のホワイト・ステージを野蛮なレイヴ・パーティーへと変貌させ、満ち足りていなかったオーディエンスたちを家路へと導いてくれた。
12位 スタージル・シンプソン(7/30 FIELD OF HEAVEN)
今年のグラミー賞で最優秀アルバム賞にノミネートされ、一躍その名が広まることなったスタージル・シンプソン。少々オーディエンスの数は寂しかったものの、実は米軍として横須賀基地で働いた経歴を持つ意外にも日本とは縁の深いアーティストである。オルガンにベース、ドラムを引き連れて武骨な身体にアメリカンなジーンズを履き、日本愛を感じる甚平を上に羽織った彼が鳴らしていくギター・サウンドは、そのライヴ・アクトとしての実力をあまりにも雄弁に物語っていて、グラミー賞へのノミネートも納得させるものだった。テイラー・スウィフトの成功を挙げるまでもなく、最近はポップ化も進むカントリー・シーンだが、卓越したバンド・アンサンブルによってオーセンティックでありながら、強度の高いサウンドを鳴らすそのライヴはカントリーとしても異彩を放っていた。
11位 エイフェックス・ツイン(7/29 GREEN STAGE)
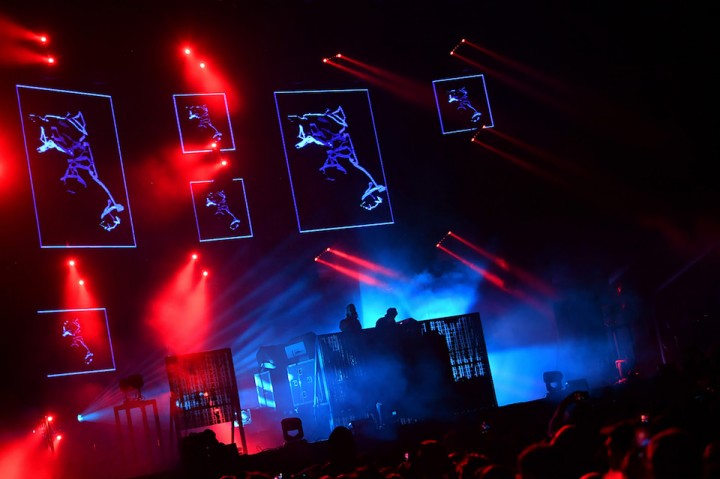
Photo: Masanori Naruse / PRESS
第1回のフジロックへの出演から20年の歳月を経て、満を持して苗場の地にエイフェックス・ツインが降臨すると、ようやく謁見する事が出来た鬼才の姿にオーディエンスからは大歓声が上がる。スクリーンから放たれる眩い光と過剰なまでの派手なライティングで、はっきりと彼の顔を認識することは難しかったが、それはミステリアスで掴み所のない凡人では理解出来ない存在という、我々の中に形成されて来た彼のイメージの反映でしかない。スクリーンの映像には、青いネコ型ロボットを初めとした日本のキャラクターを連想させるキャラクターが登場するなど、日本文化へのオマージュも散りばめられていた。豪雨が降りしきる中でバキバキの電子音を次々と投下していくステージは、まさに神から地上へ落とされた稲妻のようで、エイフェックス・ツインという迷宮入り寸前の難解なミステリーを完璧な形で私たちに魅せてくれた。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.


![ザ・スタイル・カウンシル - Caf Bleu [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/811fRno5gQL._AC_SX679_.jpg)