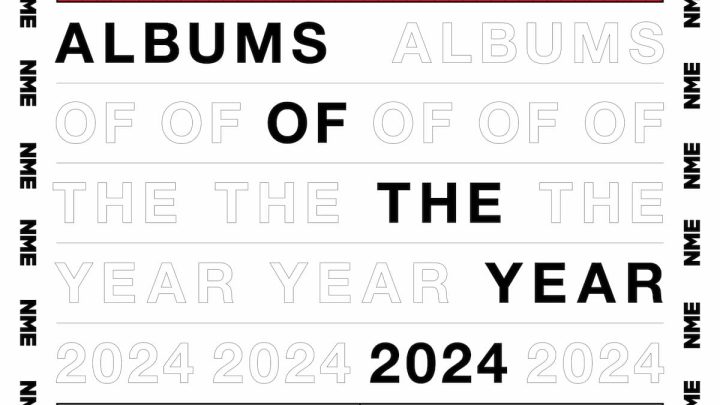Photo: All pics by Colin Greenwood
レディオヘッドのベーシストであるコリン・グリーンウッドは『NME』に対して新たなフォトブック『ハウ・トゥ・ディスアピアー』を刊行したこと、ならびに先日のバンドの再集結について語っている。
ジョン・マレー・プレスから刊行された『ハウ・トゥ・ディスアピアー』はコリン・グリーンウッドにとって初のフォトブックで、2003年から2016年発表の最新作『ア・ムーン・シェイプト・プール』まで、レディオヘッドの歩みを追ったものとなっている。コリン・グリーンウッドが撮影した写真と共に、本書には長文のエッセイも掲載されている。
「本当に美しい本で、自分も好きなポール・グラハムのようなファイン・アートのフォトグラファーたちと同じ厳格な基準で作られているから、みんなにも喜んでもらえると思うよ」とコリン・グリーンウッドは『NME』に語っている。「オックスフォードシャー出身の5人の人間がいろんな町のホールで一緒になって曲に取り組み、それを世界各地のステージに持っていく素敵な物語を伝えてくれていると思う」

当然のことながら、コリン・グリーンウッドの弟であるジョニー・グリーンウッドは本書に最もよく登場するメンバーなのだが、二人の関係が自然な撮影に適していただけじゃなく、ジョニー・グリーンウッドは常に撮影されることに乗り気だったと語っている。
「弟はレンズが大好きなんだよ。僕だけじゃなく、誰に対してもね」とコリン・グリーンウッドは語っている。「雑誌のために撮影をやったりすると、トム(・ヨーク)のことを前にしようとするけど、彼は押しのけて、自分を見えるようにするんだ。なんで、あんなにも写真を撮らせようとするのか分からないけど、いずれにせよ、彼は気にしていないんじゃないかな」
ジョニー・グリーンウッドはこれに対する反論はあるだろうか?
「その通りだけど、それは何年にもわたって撮られた写真の99%が同じようなひどい顔をしていたからなんだ。そんな写真を彼はたくさん撮っていた。彼ならその顔の耐え難い写真展を開くこともできるだろうね」とジョニー・グリーンウッドは先日『NME』のインタヴューで語っている。
「幸い、バカな弟の写っていない素晴らしい写真が何百枚もあったから、本は素晴らしいものになった。バンドにいるということが実際どうなのかがよく分かるよね」

最新作『ワイルド・ゴッド』にも参加したニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズのツアー・メンバーも務めていることについては「本当に有り難い特権」としながら、コリン・グリーンウッドはフォトブックの秘密についても腰を据えて語ってくれた。彼はレディオヘッドのステージ上、バックステージ、そしてスタジオにいることが実際どんな感じなのか、そして夏に再集結してリハーサルを行ったバンドの次の可能性について口にしている。
――こんにちは、コリン。『キッド A』収録の名曲からタイトルが取られた『ハウ・トゥ・ディスアピアー』ですが、このタイトルは目に見えない形で現場を目撃して、記録してきたあなたの立ち位置のことでもありますよね?
「そうなんだ。自分は写真を撮っていたから、この本に載るのかどうかも分からなかったしね。でも、トムのピアノに映る自分の写真と弟が撮ったもう1枚の写真を見つけた。何年もの間、僕は弟の写真を撮ってきたわけだけど、弟が私の写真を撮ったのはおそらく2枚だけなんだ。それが僕らの関係について知るべきことをすべて物語っていると思う。弟は僕の名前も覚えてないんじゃないかな」
「レディオヘッドを好きな人は気に入ってくれる本だと思うし、バンドのことを知らなくても写真や文章に興味のある人にも楽しんでもらえると思うよ」
――本書は2003年発表の『ヘイル・トゥ・ザ・シーフ』の制作から始まり、『イン・レインボウズ』や『ア・ムーン・シェイプト・プール』の制作までの時期を追っていますが、あなたはこれらの写真について「バンドの中期」と評しています。この時期ならではのことと言ったら、何になりますか?
「ニック・ケイヴが昨年ソロ・ピアノ・ツアーをやっている時期にこの本のことについてニックと話をしたんだよね。本をまとめている時期で、ニック・ケイヴが『いつ頃の写真なの?』と言うから、『初期でもなければ、最後でもないね』と答えたら、『これだけの成功を収めたバンドにいるのに未来が分からないというのはどんな感じなんだい?』と言われてね。アルバムを作る時はいつだって未来が分からないものだけど、『OKコンピューター』や『キッド A』、『アムニージアック』といったアルバムを作った後の未知の感じってどんな感じかなと思ったんだ」
「常にどうなるだろうと思っている。バンドにいるというのは、いつも大成功の波の頂点に乗っているわけではなく、未知の池を漕いでいるようなものなんだ。どんな方向に進んでいくのかは分からない。それがこの本で扱っていることなんだ。ザ・ビートルズのドキュメンタリー『ゲット・バック』みたいな感じだね」
――『ゲット・バック』では待ち時間や口論や対立にどれだけの時間が割かれているかが描かれていましたが……。
「あとはお茶をする時間だよね」
――そのような産みの苦しみの時期にあるレディオヘッドというのはどういったムードなんですか?
「自分たちをザ・ビートルズと較べるわけじゃないんだ。ただ一緒に過ごした時間を思い出させてくれたという意味合いだよね。僕らにはトーストを作ってくれる人はいなかったけど、何度もお茶を飲みながら、前の晩にテレビでやっていたことや新聞に載っていたことを話したりした。バンドをやっている人は誰でも、あのザ・ビートルズのドキュメンタリーを観て、まさにああいう感じと思うだろうね。ピーター・セラーズが出てこないだけだよ」
――でも、あなたたちには代わりにスタンリー・ドンウッドが……。
「その通り。ここに掲載されているのは中期で、成功は収めたけれど、繰り返すようなことはしたくなかった。この時期に写真を撮ったのはだからなんだ。『OKコンピューター』や『キッド A』とは違う種類の強度と焦点があった。こちらのほうが激しいものだったかもしれないね」

――ファンはアーティスト写真や雑誌の写真、よく知られているライヴ写真を食い入るように見てきたわけですが、この裏側の写真から何を知ることができると思いますか?
「これらの写真は僕だけが撮ることができたという意味ですごくユニークなものだよね。この本ではフォトグラファーでは撮ることのできない場所でのバンドを見ることができる。レコーディング・スタジオや楽屋やツアー・バスとかね。ガードを降ろしたプライベートの特別な場面で、プレスのフォトグラファーの前よりも自分たちが出ていると思う」
――バンドがカメラをしまえとは言いませんでしたか?
「愉快だったのはバンドは僕が写真を撮るのにすごく協力的だったということだね。有り難かったよ。バンドとして、僕らは各自がやることを応援してきたんだ。トム・ヨークがスタンリー・ドンウッドのアートワークでやったソロ・プロジェクトもそうだし、弟による手間暇のかかるプロジェクトもそうだし、エド・オブライエンの……エドがやっていることは知らないけどさ」
「ツアー中も、シカゴのバックステージでも、みんな自分なりに過ごしたいんだ。だから、演奏の前は時間を大切にしていて、誰かを撮影する時間はあまりない。だから、3万人の観客に見つめられているステージ上のほうがバンドを撮影する時間も自由もあるんだ」
――ステージで演奏しているアーティストが撮影した写真は珍しいですよね。
「そうなんだよ。ベースを弾くとか、他のことをやっているべきなんだろうけどね。自分は一体何をしているんだろうね?」

――ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズでも写真を撮っているのですか?
「そうなんだ。彼もリラックスしてくれている。彼とウォーレン・エリスはいくらでも写真を撮ることができるよ。本当にファンタスティックなキャラクターなんだ。すごい衣装と素晴らしいパーソナリティがある。ドラマーのラリー・マレンもウェスタン風のデニム・ルックだし、パーカッションのジム・スクラヴノスはワークウェアみたいな格好をしている。バック・シンガーの見た目もいいんだよね」
「ザ・バッド・シーズの人たちは自分たちのスタイルが固まっている年齢だし、誰にどう思われようと気にしない。そういう人たちといるのは楽しいよね」
――本書であなたはレディオヘッドとして再び活動することを長寿ドラマのボックスセットを観るのを途中から再開させることと喩えていますが……。
「その通り。僕らはあまりに多くの時間を過ごしてきたから頻繁に会うことはない。だから、その時には全員が歳を取っているだろうね。とは言っても、大したことじゃない。髪を全部剃ってカルトに入信するわけじゃないからね。白髪交じりの髭で音を出してみるということだよね」
「今は10歳ぐらい上のザ・バッド・シーズとやっているから、どんな感じでやっているのか分かるし、問題なさそうだしね。レディオヘッドが今後どうなっていくか考えているところだから、また報告するよ」

――トム・ヨークはニック・ケイヴにように完全なヴァンパイアになれるでしょうか?
「ああ。スーツを着始めたりしてね。面白い話があるんだけどさ。レディオヘッドを始めた時、1993年に“Pop Is Dead”のミュージック・ビデオを作ったんだけど、キャリアで最初にして最後だけど、レコード会社から服を買うためにお金をもらったんだ。EMIからスタイリストがついてくれて、服を買うために一人300ポンドくれた」
「バスに乗ってロンドンに行って、それぞれの服を買った。トムとジョニーはコヴェント・ガーデンにあるフリップというヴィンテージ・ストアに行って、フィル・セルウェイは白のデニム・スーツを買った。エドはきらびやかなシルヴァーのスーツを買い、僕は就職面接に行くようなスーツを買った。だから、4つの別々のバンドにいるような格好で、写真を撮っておいたらよかったと思うけど、インターネットにもたくさん出回っているよね」
――レディオヘッドというボックスセットの話に戻りますが、最近ディスク5をプレイヤーに入れて、バンドでリハーサルを行ったそうですね。
「夏に数日集まって、いろんな曲を演奏してみて、2018年にやり残したことに手を付けてみたんだ。みんなに会えて、よかったし、楽しかったよ。3〜4日やる予定だったんだけど、2日で終わった。問題なかったし、まだまだできたからね。弟は数週間リハーサルをやれば、ツアーに出られると言っていた。何も問題はなかったね」
「この先は、みんながそれぞれやっていることを終わらせることへと注力することになる。弟は体調も良くなくて、療養中なんだ。リハーサルは楽しくて、和気あいあいとしていたけどね。『OKコンピューター』を仕上げたザ・チャーチというスタジオでリハーサルしたんだけど、最後にあの場所を訪れたのは1996年に“Airbag”のベースをレコーディングする時だった。それでクラウチ・エンドに再び行ったんだけど、素晴らしかったよ。また集まって、今後の計画を練ることになると思うけど、どうなるかは分からないね」

――レディオヘッドのツアーが近いというわけではないということでしょうか?
「そうなんだ。ツアーが近いというわけじゃない」
――レディオヘッドというマシーンをもう一度稼働させるには大変な労力が必要になると想像されますが……。
「本当にそういうことなんだ。今のザ・バッド・シーズのツアーでも何人関わっているのか分からないけど、多くの人が動いている。大きなアリーナでやっているんだけど、慣れていくと、自分のホームになっていくのが好きなんだ。ステージがホームになっていって、出ていくと、安心できる場所になっていくんだ」
――レディオヘッドとして再始動する理由や時期を見つけていくには、どんな会話が必要でしょうか?
「分からないよ。そういう話になってないからね。でも、ニック・ケイヴともそのことを話していたんだけど、彼はリスナーとしても素晴らしくて、レディオヘッドはいつ何をどうやるかという点において、何でもできる立場にあると言ってくれたんだ」
「ニック・ケイヴはボブ・ディランの話をしてくれたんだけど、彼は2年間ツアーに出ることもできれば、まったくやらないこともできるし、ヒット曲を演奏することもできれば、毎晩違う曲をやることもできる。新作を出してもいいし、クレイジーなプロジェクトをやってもいい。そうした自由があることに感謝しなきゃいけないよね。最初の3枚のアルバムしか興味がないなんてことにはなっていないわけだから」
「自分たちはまだ次に何をやるのか知りたいと思ってもらえるバンドだと思う。そうなっているのは本当に幸運なことだよね」
コリン・グリーンウッドによる『ハウ・トゥ・ディスアピアー』は下記のサイトで販売されている。
レディオヘッドについてはトム・ヨークとジョニー・グリーンウッド、元サンズ・オブ・ケメットのドラマーであるトム・スキナーからなるザ・スマイルが先月サード・アルバム『カットアウツ』をリリースしており、トム・ヨークは11月にソロ・ツアーでの来日公演を行うことが決定している。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.


![トム・ミッシュ - Full Circle [Amazon限定 / 日本語帯付きLP / 解説書封入 / ルー・アンド・ホワイト・ヴァイナル] (BTG021LPABR) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/71EuFnkO80L._AC_SX679_.jpg)