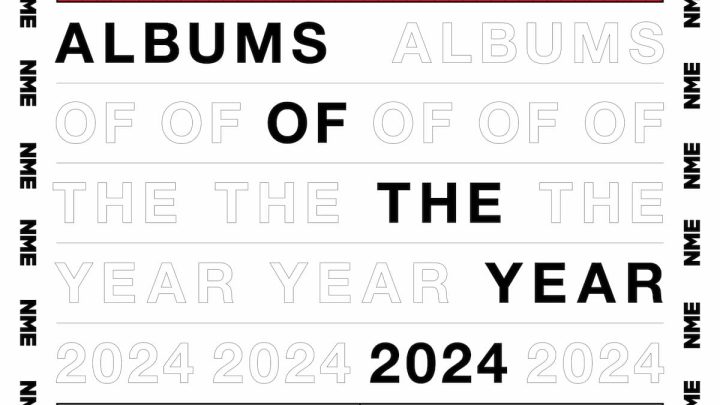Photo: Nicole Nodland
ポール・ウェラーは66歳の誕生日前日となる5月24日にリリースされたニュー・アルバム『66』についての全曲解説が公開されている。
ニュー・アルバム『66』はサッグス、ノエル・ギャラガー、ボビー・ギレスピーといったアーティストが作詞陣に名を連ねており、ドクター・ロバート、リチャード・ホーリー、スティーヴ・ブルックス、マックス・ビーズリーといったポール・ウェラーの旧友たちが参加している。
2021年の『ファット・ポップ』に続く3年ぶりの新作となる『66』はソロとしては17枚目、キャリア通算では28枚目のアルバムとなり、日本盤はSHM-CD仕様、ボーナス・トラックが1曲収録されている。
公開された全曲解説は以下の通り。
1. シップ・オブ・フールズ (Ship of Fools)
Q: サッグスと書いた曲ですね。
「ああ、サッグスが歌詞を送ってくれたんだ。特にどの曲のためというのではなく、ある種のポエムだった。それが俺が書いていた曲の歌詞にうまくハマったんだ。サッグスにとってどんな意味がある詩なのかは知っているが、俺はボリス・ジョンソンと保守党の取り巻き連中のことだと思えた。俺たちを奈落の底に導く愚か者たちのことだとね。同時に世界レベルでもそういう無能者が大勢いるだろ。俺はそんな意味として捉えているんだ」
Q: 最初からアルバム1曲目にと思っていたのですか?
「1曲目にすべく、他とは違う曲だと思ったんだ。通常1曲目というのは、例えばライヴのセットでも速い曲を持ってくることが多い」
Q: 「ホワイト・スカイ」(White Sky)のような曲ということ?
「ああ、まさにそれさ。そこで、普段とちょっと違うことをやるのもいいなと思い、アコースティック曲を持ってくるのはどうかと考えた。曲の雰囲気もいいし、ジャッコ・ピークのフルートも最高だ。とにかくこれまでの俺の作品にない、新しいタイプの1曲目だと思ったのさ」
2. フライング・フィッシュ (Flying Fish)
Q: 一度聴いたら忘れられない、頭に残る曲でした。まさにライヴ向けの曲だと思います。
「ステージでうまくいく曲かどうかはまだわからないが、一度はトライしてみるよ。あれは確かアルバムを作り始めて、最初に取りかかった曲だった。エレクトロニック風なサウンドで、ある時点では、アルバム全体がそうなるのかもしれないと思っていたんだ。実際はまるで違ったがね。もしかしたらアルバムの青写真というか、こういう方向になるんじゃないかと思っていたんだ。でも途中で変わり、結果的にはそうはならなかった」
Q: ル・シュペールオマールが何曲かで参加していますが、この曲では曲を書いた上に演奏でも参加しています。クリストフ・ヴァイランとはリモートで?それとも彼がスタジオに来たのですか?
「彼に送ったんだ。現代科学の驚異というべきか。こちらが送ったものに彼らが送り返してくれて、それで素晴らしいものができるんだ。そうやって彼がシンセを加えてくれた。他にもジョシュ・マクローリーがベースを弾いているが、ある日彼がスタジオに来てくれたんだ。もしかするとたまたま来ただけかもしれない。覚えていないよ」
Q: 顔を出してお茶でも…と思ったら、レコーディングに参加してしまうという危険、というかむしろ素晴らしい出来事があるんですね!
「ああ、ま、そういうことはそういつもあるわけではないけどね」
3. ジャンブル・クイーン (Jumble Queen)
実はヨーロッパ・ツアーですでに演奏していましたね。私も5月にアムステルダムで聞きましたが、その時は「Take」というタイトルだった。ヨーロッパ・ツアーが再開し、セットリストを見て「“Jumble Queen”?聞いていない新曲だ」と思ったら同じ曲でした。そこで質問は、ライヴで演奏してテストすることの良さは何か? そしてタイトルをどうやって決めるのか?の2つです。
「“Take”はあまりに退屈なタイトルだなと思ったんだ。そうだろ?(笑)あとはノエル(・ギャラガー)が“ジャンブル・クイーン”にすべきだと言ったから」
Q:「Bad Honey」と呼ばれていた時もありましたよね?
「ああ。歌詞と一緒で、タイトルは最後の最後まで、何回も変わるんだ。この曲はノエルにバッキングトラックを送って『何かいいアイディアはない?』と聞いたら、20分後には歌詞が送られてきた」
Q: たったの20分?
「それ以上でなかったことだけは確かだ。ぴったりとうまく行ったんだよ」
4. ナッシング (Nothing)
Q: とても美しい曲。これも間接的にサッグスの曲ということですね?
「ああ。この時も彼から“Nothing”というタイトルのついた美しいポエムが送られてきたんだ。それが歌詞の大部分になったわけだけど…当然、俺はサッグスの詩だと思って曲にし始めたんだが、実は彼の友人のチョーキー(アンドリュー・チョーク)というやつの詩だったと分かったんだ。サウスコーストあたりでキャラバン暮らしをしている男さ。幼なじみである彼とサッグスのことを書いた詩だったらしい。結果的には、それらの言葉を歌詞にして曲に乗せ、サッグスがコーラス部分の言葉を書き加え、チョーキーに「歌詞に使わせてもらっていいか?」と聞いたんだ。彼は自分の言葉に命が吹き込まれたことをすごく喜んでくれたよ。すごくいい話だと思う。彼はプロの物書きでも詩人でもソングライターでもない普通の男だ。でもそれは実に心温まる詩だったんだ」
Q: ラヴソングでもありますね?
「たくさんの解釈ができる曲だと思うよ。俺と家族のこと、何もなく慎ましかった子供時代から今に至るまでとも受け取れる。サッグスとチョーキーの関係はまた違う。いろんな解釈が可能だ」
Q: でも他人の書いた歌詞がポール・ウェラーの曲になるには、共感できる何かを見つけなければならないですよね?
「言葉に共感できたのさ。シンプルで美しいのはもちろん、自分なりの意味を読み取ることができた。どんな曲もどんなアートも、自分なりの解釈や意味を見つけられるかがすべてなんだ。重要なのは必ずしも作者の意図ではなく、そこから何を受け取るか。それが一番だということさ。俺自身、子供の頃から聴いてきて『この曲のこの歌詞にすごく共感できた』というのが沢山ある。でも後になって、本当の意味は全然違っていたり、その場で作ったナンセンスな歌詞だったと知ることもある。でもそれでもいいんだ。その時の自分にとって、どんな意味があったかが重要なわけだから」
5. マイ・ベスト・フレンズ・コート (My Best Friend’s Coat)
Q: ル・シュペールオマールのクリストフ・ヴァイランと共作した2曲のうちの1つ。ル・シュペールオマールのファースト・アルバム、EPの大ファンだったと聞きましたが、今回のコラボレーションはどのように?
「俺が彼のファンだってことは彼も知っていた。以前、“On Sunset”で素晴らしいリミックスをしてもらった。とにかく彼の音楽のファンなんだ。フレンチ・ゲーリックとも言うべきブルトン人的なメロディやコード、ハーモニーのセンス。言葉では説明しづらいが、音楽を聴けばわかると思う。実際、どうやって作っているのかわからないから、俺には説明はできないが、他にはない独自のサウンドだ。わかれば自分でもやってみたいんだが、どうにもわからない。とにかく彼の中にある何かだろう。俺から「一緒に曲を書いてみないか?」と声をかけたところ、6曲ほどバッキングトラックを送ってくれたんだが、“My Best Friend’s Coat”になった曲を聴いた瞬間――確か娘を風呂に入れていた時だよ――何度も聴き返した次の瞬間、メロディが浮かび、最初のヴァースが聞こえてきて、あっという間に全体像が出来上がった。イメージは、フランス語の歌詞を俺が英語にしている、というもの。なぜそう思ったのかはわからないが、それが俺の頭の中のイメージだった。つまり、フランスのシャンソン特有の“物語性=ドラマ”のある曲だ。ジャック・ブレル、エディット・ピアフ…トーチソングと呼んでいいようなシャンソン。そんな風にアプローチした。歌詞は決して自伝的とは言わないが、自分の経験も少しヒントにした。古いフランスのシャンソンの歌詞のような、胸を締め付けられるようなものをイメージしていたのさ」
Q: アビイ・ロード・スタジオで録音したハンナ・ピール・アレンジのストリングを収めたアルバム最初の曲ですね。
「素晴らしいね。高くついたが、その価値のある1日だった!かなりの数を録音したんだ。5〜6曲かな。サウンドが素晴らしい。No.2(第2スタジオ)でだが、非常に良い音時間だった。3時間のセッションを2回、短い休憩を挟むという、昔ながらのやり方だ。予定していたよりも早く録音も終了したよ」
6. ライズ・アップ・シンギング (Rise Up Singing)
Q: ブロウ・モンキーズのドクター・ロバートとMonks Road Socialというプロジェクトのために書いた曲としてスタートしたものを、あなたが手直しをしたのですね?
「そうだ。元々のヴァージョンは、スペインを拠点にしているロバートが作ったバッキングトラックに俺がイギリスで手を加えて作ったもので、リリースはされたもののあまり注目されることなく、そのままになってしまった。いい曲なのにそれでは勿体無いなと思い、それでもう一度録音し直したんだ。ストリングスやブラスを加え、最初に出た時よりは注目してもらえることを願ってね。実際、出たことさえ知らない人もいると思う。でも聴いてもらう価値のある良い曲だと俺は思った。歌いながら頭にあったのはメイヴィス・ステイプルズだ。メイヴィスがこの曲を歌っている姿が俺には想像できた。心を高揚させてくれる、ポジティヴなメッセージだね」
7. アイ・ウォーク・アップ (I Woke Up)
Q: この曲のインスピレーションはどこから?アコースティックギターで始まり“目覚めると 何もかもが消え去っていた 俺の家は俺の居場所じゃなくなっていた”と歌っていますが、みんなどこへ消えてしまったんですか?(笑)
「わからない。何か比喩的な意味があるわけじゃないんだ。これも先ほどと一緒で、リスナーがそれぞれの解釈で好きなように捉えてくれればいい曲の一つさ。目を覚ましたら、すべてがすっかり変わっていたという、そんな世界を想像して書いた短い物語にすぎない。そういう経験をしたとか、感じたということじゃない。理由はないが、ただ書けたんだ。いい曲だと思ったし、メロディも歌詞も気に入った。心を掴む何かがあったんだ。それが何を意味しているのかは、俺自身にもわからないし、もしかすると何の意味もないのかもしれない」
Q: ザ・ジャムのファンに嬉しい情報は、旧友スティーヴ・ブルックス がスパニッシュギターを弾いていることです。ヘッドホンで聴くと左チャンネルで彼が聞こえ、あなたと、ベースが右チャンネル。それとリチャード・ハーレイも……。
「ああ、スライドギターを弾いている」
Q: 彼もたまたま来ていて弾くことになったんですか?
「いや、シェフィールドにいる彼のところに送ったんだよ。トラックで。そして送り返してくれた」
Q: 曲の途中で、予想を裏切るような方向転換をしていますね?
「ああ。でも音楽論的にそれを説明できる知識が俺にはないので、自分でもわからないんだよ。俺からスティーヴ・ブルックスとハンナに、唯一参照点として名前を挙げたのはバッハだった。でも彼らがそれを参照にしたかどうかは…いや、スティーヴのプレイからは聴こえるが、ハンナはどうだろう?ともかく俺が挙げたのはそれだけ。一種のバロック風というのかな。でも俺はクラシックを学んだわけじゃない。聴いて『あ、これいいな。好きだな』と思えば拝借する」
Q: そういうルールを意識していない?もしくはルールを破りたいと思っている?
「今はもう音楽をジャンルに分けて区別化しないってところまで来たよ。すべてがそこにある音楽、というだけ。そこにある緑の線と一緒で、そこに存在している。そのうちのどれかとどれかが混ざってうまくいくこともあれば、少しずつ組み合わせることもある。いずれにせよ、俺は何かを勉強で学んだ経験がない。勉強するっていう頭がないんだよ。忍耐がないっていうか。君の家の前を通りかかったら、君が何か音楽をかけていたとか、子供がヒップホップ・トラックでも何でもいいけど、かけていたとする。それをチラッと耳にして『ああ、いいな。使えるな』と思ったり、無意識に自分の中に入っていたり…。意識的な時もあれば、無意識的な時もある」
8. ア・グリンプス・オブ・ユー (A Glimpse of You)
Q: シンプルで美しくも、2曲が一つになったかのような構成です。クリストフの作り上げたサウンドスケープの上に、あなたの言葉のメロディが乗り、まるで自分自身の上に歌っているかのようなコーラスといい…そういった構成は全部出来上がった形で思い浮かぶのですか?
「すべて偶発的さ。 リードのメロディを先に録音した後で「あ、こうすればいのか」と思い、あと2つの声を重ね、コーラスのようにしたんだ。でもあの曲に関しては、特に最初から考えてそうしたわけじゃない」
9. スリーピー・ホロウ (Sleepy Hollow)
Q: 歌詞はまるでポエムのようです。必ずしも曲の歌詞として書き始めたわけじゃないものが、歌詞になるといったこともあるかと思うのですが、この曲もそうでしたか?
「正直、記憶が定かじゃないんだが、歌詞は曲よりあとに書けたはずだ。最初に思い浮かび、口にしたのがその1行だ。でもどんな意味があるのか自分でもわからなかったんで、あとで変えようと思っていた。ところが他にいい言葉が思い浮かばず、気づくと”sleepy hollow”のモチーフに戻ってしまう。俺にとってあれはある種の子守唄だよ。俺の子供たち含め、世の子供たちのための子守唄。それ以上はわからない。ただ温かな雰囲気が気に入っている曲さ」
Q: 家でバッキングトラックに合わせ、携帯に向かって歌い、ギターを弾いたという感じですか?
「ああ。携帯に向かってギターでコードを弾きながら、ラララとメロディを口ずさみ、もしかすると“Sleepy Hollow”と意味もわからぬまま、歌詞を歌っていたのかもしれない。って今もわからないけどね。そこから生まれたものを俺が広げていって曲にしたというわけさ」
10. イン・フル・フライト (In Full Flight)
Q: ホワイト・レーベルのトム・ドイルとアンソニー・ブラウンとの共作です。この曲はどうやってできたのですか?
「確か、彼らからバッキングトラックが送られてきたんだよ。実はだいぶ前から手元にあり、いい曲が作れそうだと思いながらも、とっかかりがないままだった曲の一つだ。そんなわけで、時間がかかってしまったのは、俺の側の理由さ。ドラムをオーバーダブで重ね、ベースを入れ、その上にトムとアンソニーのトラックを乗せた。彼らの作ったものはそのまま残しながら、たくさんの音を上に重ねたんだ。また、ライヴのためにイギリスにいたセイ・シー・シーに来てもらい、バックヴォーカルを歌ってもらった。というのも、デモではトムかアンソニーか、どちらかがおそらくヴォイス・サンプルを使ったシンセを弾いていて、ぐわ〜んと回転するようなサンプリング特有の音が鳴っていたんだよ。それを人間の声を使って再現できないかと考えた時、セイ・シー・シーならできると思ったんだ。実際、いい仕事をしてくれたよ」
11. ソウル・ワンダリング (Soul Wandering)
Q: 今のところ僕のお気に入りの1曲ですが、ボビー・ギレスピーとの共作ですね。作詞が彼?
「ああ、作詞が彼だ。この時もかなりラフな、骨格だけの状態のバッキングトラックをボビーに送ったんだ。歌詞のフレージングのガイドとなるようなメロディを俺が口ずさんだものを上に乗せてね。ノエルもそうだったが、時間はかからず、その日の晩か翌日に歌詞が返ってきた。俺が感じていることにとても似た感情に触れる歌詞で、とても気に入ったんだ。ある年齢に達し、運が良ければ、人間っていうのは自分たちの存在についてとか、実存主義的なこと、精神的なことを考えるようになるものだ。うまく捉えることができたんじゃないかな」
Q:以前にも『22ドリームス』の“Big Brass Buttons”で共作していますよね。ボビーとは会って一緒に曲作りをしたのですか?
「いや。今までも他の人間とやった経験はあるが、毎回とは言わないまでも、俺にはすごく難しい作業なんだ。リチャード・ホーリーとも『いつか一緒に同じ部屋で書こう。曲を捻り出そう』と言って何年にもなるが、どちらも問題だらけの人間だろ?無理なんだよ。あまりに神経質っていうか、偏執的っていうか、なんなんだろう。お互いシャイすぎるのか、ぎこちなくて…。結局実現せぬままになっている。なのでお互いにアイディアを送り合う、今の形のままの方がいいんだ。どちらにせよ、俺の場合、何かを耳にして最初に思うのは『これは絶対に曲になるぞ』と思うか『後で何かを考えよう』と思うかのどちらかだ。もしくは『またあとで戻ってこよう』と思うか『どうやっても無理』か、そのどちらか。だから結局は、リモートでやるのが一番いいんだよ」
Q:でもそうやって戻ってきた時に、びっくりするようないい歌詞がつくのは最高じゃないですか?
「自分でやるよりずっと楽だしね。もう一つ思うのは、人は年齢を重ねるごとに、書くこと、書く題材を見つけることが難しくなる。なぜなら若い頃ほど、新しい体験がないからだ。長く生きていれば『これもやった、これも経験した。これはこうなる』と思うことばかりで、毎週のように驚かされることばかりじゃないんだ。すると結果的に、同じようなテーマの曲ばかり書いてしまうのは避けられない。俺自身を含めて、それを回避する方法はない。12曲か何曲か知らないが、これまで書いたことのないような曲を毎回書けるわけがないじゃないか。そんなの、俺ほど長く続けている人間には不可能だ。その自覚があるので、くだらない自分の基準以下の歌詞を書くよりは、自分以外の誰かに歌詞を書いてもらったほうがいい。作曲面では毎回何かしら新しいことができるが、作詞では難しいかもしれない。そんな時は外注し、彼らがどんなことを書いてくるか見てみればいい。クリエイティヴであることには変わりないよ。それもプロセスの一部だ。物事を動かし続けるという意味で、俺はそれでいいと思っているんだ」
12. バーン・アウト (Burn Out)
Q: アーランド・クーパーとの共作ですが、2023年初めジョニー・ハリス、ヴィッキー・マクルーア主演ITVドラマ『WITHOUT SIN 罪なき者』のタクシーのシーンとエンディングで少し流れましたね。番組のために書き下ろしたのですか?
「いや、違うよ。正直、ずっと前から俺の中にあった曲なんだ。出来上がってからもだいぶ経っている。おそらく2021年には完成していたんじゃないかな。なので結構昔からあったという気がするよ。持て余していて、どうすればいいかわからなかった。映画的な資質があるので、テレビか映画に使われたらいいんじゃないかと思ったりもした。当時はアルバムに入れる曲だとは考えていなかった。2〜3年くらい経っている。ところがレコーディングも終盤に差し掛かり、これがいいラスト曲になるんじゃないかと思ったんだ。ある種のフィナーレ。終末の日ではなく、時代の終わりの象徴としてね。いや、終末の日なのかもしれないが、間違いなく、時代の終わりというヴァイブだ。でもおもしろいのは、アーランドが歌詞を書き、この曲が完成したのは2021年だったということ。少なくとも俺にとっては、ロックダウンに関することが多く含まれているんだ。『この派閥の連中は 君と俺に飽きている これ以上詳しく述べる気はない 俺達が目にしてきたすべてについて』という歌詞。どの保守党のバカが言ったんだったか忘れたが、俺(ミュージシャン)は新しい仕事を見つけるべきだと言われたのだとしても…そんなことは絶対考えたりしない、と」
Q:何かを学びましたか?
「俺たちに何ができた? 何ができた? ひどい話さ。それはともかく、あの歌詞はそういう意味だったんだ。かなり殺伐としているが、アルバム最後の曲に合っているんじゃないかと思った。今の時代、今の世界を考えると、陽気でハッピーな曲でアルバムを終わるのは相応しくないと思った。今の殺伐とした時代を考えると、それでは合っていない。今は正直であるべき時代なんだ。俺にはそれが少し反映された曲であるように思える」
Q:でも最後、“生きることに疲れたわけじゃない 俺は大丈夫”と歌うところには、希望の火がありますね。そして音がすべてなくなり、静かになった後、あなたが“今のテイクでOK”…というようなことを言う。
「ああ、あれは2回も録っていないんだ。コード進行をメンバーに示す意味で、曲の半分くらいまでを一度やったが、次のテイクが結果的に収録されたテイクになった。そんなわけで、すべて偶発的だった。それを切り貼りして出来たのがあの曲だということさ」
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.


![トム・ミッシュ - Full Circle [Amazon限定 / 日本語帯付きLP / 解説書封入 / ルー・アンド・ホワイト・ヴァイナル] (BTG021LPABR) [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/71EuFnkO80L._AC_SX679_.jpg)