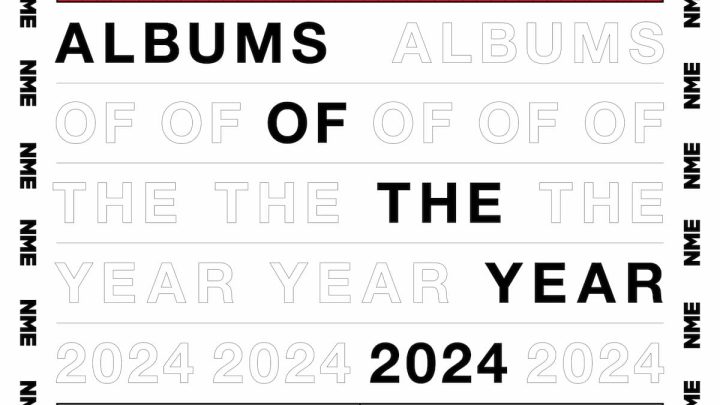Photo: Andy Hughes/NME
ジョージ・エズラのヒット曲“Shotgun”がHonda「オデッセイ」CMソングに起用されたことを受けて、『NME』では2018年のロング・インタヴューを掲載する。“Shotgun”を収録したジョージ・エズラのセカンド・アルバム『ステイング・アット・タマラズ』はデビュー・アルバム『ウォンテッド・オン・ヴォヤージュ』に続いて大成功を収め、2018年のイギリスの年間チャートでは2位を記録している。このインタヴューは同作がリリースされる直前に行われたものとなっている。
――
午前10時30分だというのにジョージ・エズラは騒がしい。「コーヒーの世界にはそんなに詳しくないんだ」と言う彼の顔には大きな笑顔が広がっている。「でも、これで何時間も過ごせるわけだからね」彼は今朝、今のところ2杯を飲んでいる。まるでタイミングを見計らったように撮影を行っている北ロンドンのスタジオではステレオから楽曲が流れてきた。ルー・リードの“Walk on the Wild Side”だ。
フォトグラファーが『NME』の表紙のための撮影を準備している間、洋服をめぐって口論があった。ジョージ・エズラとスタイリストは黒のロングコートにIKEAのスタンダードな白のマグカップを合わせることで落ち着いた。その見た目はジョニー・キャッシュと紅茶を入れにきた職業体験中の若者の間のような姿になった。マグカップを手に写真撮影を行う時、ロックスターがどうすべきかを知っているような落ち着いた無頓着さでジョージ・エズラはレンズをにらんでいた。近づいてみると、カメラは嘘をついていないことが分かった。彼の肌はほとんど毛穴もないほど美しく、彼のブロンドヘアーはヒヨコの毛のようにやわらかく、軽やかだった。「興奮してるよ」と彼は言った。「なんでも訊いてくれ」
ジョージ・エズラはたちの悪い風邪をひいている、私は心配するPR担当からそう言われた。しかし、ロックスターの他の人たちであれば、病原菌をハード・ドラッグと闘わせたり、インタヴューに現れなかったりするのだろうが、彼は楽しそうにカプチーノをもう一杯頼んで席についた。セックス・ドラッグ・ロックンロールについて訊いてみたいと思ったが、彼はあまりにも健全に見えた。そして、あまりに成功を収めていた。2014年に彼がデビュー・アルバム『ウォンテッド・オン・ヴォヤージュ』をリリースして以降、彼のキャリアは衝撃的なペースで離陸していった。あの年、彼以上の売上を上げたのはエド・シーランとサム・スミスだけだった。「『当然だ』なんて思ったことはないんだ」と彼は語っている。「当然なことなんてないことを当然だと考える、それが僕の学んだことだね」
代わりに私はツアーと4年ぶりとなるセカンド・アルバム『ステイング・アット・タマラズ』について訊いた。『ウォンテッド・オン・ヴォヤージュ』でジョージ・エズラは少年時代のボブ・ディランへの憧れをアップビートなギター・ソングに乗せて、恋愛や若者としての試み、彼方なるヨーロッパの都市への夢を歌った。それは完全に20代の若者がインターレイル・パスでヨーロッパを旅行する夏休みのサウンドとなっていた。新作のテーマについて訊いてみた。「最大のテーマは逃避することだね」と彼は椅子から私のほうに乗り出して語ってくれる。「ツアーをしている時は素晴らしい生活なんだけど、そこから放り出されると、何もないんだ。頼りにできるのは自分のクリエイティヴィティだけだった。僕は朝起きて、曲を書くような人間じゃないからね」
しかし、それこそがまさに彼がやろうとしたことだった。グラストンベリー・フェスティバルのピラミッド・ステージに集まった満員の昼間の観客に演奏したことを含め、成功を収めたアルバムのツアーを丸々2年間行った後、彼は気が遠くなるほど退屈な生活を送るようになった。テレビを観て、携帯をいじり、ハートフォードの自宅で夕方頃に起きる。彼は次のように語っている。「毎日、起きてから曲を書こうとしていた。毎晩床につくときに思うんだ。今日はなにかをやろうってね。でも、失敗するんだ。自分を役立たずだと思ったよ」
結局のところ、そうした低迷への癒やしとなったのはインターレイル・パスでヨーロッパを旅行する夏休みに出ることだった。彼は訪れたことがないにもかかわらず、曲に書いていたブダペストやバルセロナといった場所を見ることになった。バルセロナでは安くて汚いエアB&Bに泊まったところ、昔のアナログ盤やボヘミアンなミュージシャンで溢れていたという。「あれは素晴らしい旅だった」と彼は語っている。「想像してみたんだ。ジョージ、見知らぬ人と暮らしたら、楽しくなるんじゃないかって。実際、そうだったんだよ」その見知らぬ人はタマラという名前で、他にもそこまでエキゾチックな場所じゃなかったとしても、ノーフォークの養豚場やスカイ島のB&Bへの旅行はジョージ・エズラが彼の音楽に必要としていたもの――ゆとりを与えてくれたという。「僕のことを誰も知らない街にいて、何の決まりごともなかった。朝起きて、通りを歩いて、ノートを埋めていく。思考していくようになるんだよ。それを揉み消すことなんてできないんだ」
「僕の感じていたことにラベルを貼るとすれば不安だった」と彼は続けている。「家にいて11時にベッドに入ろうとしていて、世界の向こう側では何かが起きたという速報が入ってくる。それで、何もやってないんじゃないかと考え始めるわけだけど、でも何ができるっていうね。自分は地元でパジャマ姿なんだ。自分よりも大きなことばかりでさ。そこに参加することもできるんだろうけど、全部が自分の責任ってわけでもないからね。バルセロナへの旅は『もういい。今起きていることに常に詳しい必要なんてないんだ』と思わせてくれたんだ」
こうした考えは『ステイング・アット・タマラズ』からの初期のシングルとなった“Don’t Matter Now”にそのまま表れている。「Sometimes you need to be alone(たまには一人になる必要がある)」と彼は力強いバリトンで眩しいスカのリフに合わせて歌い出す。「Shut the door, unplug the phone(ドアを閉めて、電話の電源を切るんだ)」
「自分が解き明かそうとしていたのは自分が経験していることは世界のせいでも自分のせいでもなく、24歳だからなのかってことでさ」クオーターライフ・クライシスだろうかと私は示唆してみた。「ああ、子どもでもなければ大人でもないっていうね。その間なんだ。ジョージ、お前は何なんだ? 大人の子どもか? それが僕の感じていることだね」いつ大人になると思いますか?「自分を大人と呼べるようになるには、自分の笑い方を見つけないとだよね。今はくすくすと笑い過ぎだからね」
ジョージ・エズラには少年のような部分が間違いなくあるが、悪い意味ではない。彼は叔母が非常に素敵な若者と言うような人だ。彼は自分の音楽を「ユーザーフレンドリー」と評していて、そこは私も理解している。そう、それはうっかり“Budapest”にハミングしてしまうような朝を作り出してくれたりする。そのあたたかみのある親しみやすい楽曲はそこからココアを作れそうなほどだ。彼はこの曲を10代の終わりに書いた。人生はシンプルで、ツアーの感触を得ようとしている頃だ。「ヴァンの後ろに乗った最初のいくつかのツアーは観客を集めようとしている頃だった」と彼は振り返っている。「法の外で生きているように感じていた。すごいことをするわけでもないんだけどさ。でも、それ以上に誰にも気にされてなかったからね。夜だけの存在だったんだ」
ジョージ・エズラがこれまでのところキャリアですべて正しいことを行っているのには驚かされる。彼はブリストルの大学を中退したが、(レーベルの)コロンビアとの契約に漕ぎ着けた。彼は難しいセカンド・アルバムを急がなかった。彼はメンタル・ヘルスのチャリティのパトロンも務めている。待て。不品行はないのだろうか、私は疑問に思う。コカインの山は? 豪華な金のトイレは?「過剰と言えば、僕にとってはライヴをやることだね」と彼は残念そうに思い返している。「そういうものって単に僕より大きすぎるものなんだ。すべてがね」
大抵、インタヴューのどこかでロックスターはそうであることがどれだけ大変なのかの不平を口にする。しかし、ジョージ・エズラからはまったくなかった。彼はファンが巨大な営利企業の懸命に働く人物などではなく、10分でライヴにやってくる自由気ままな吟遊詩人と自分の見ていることを知っているのだ。「この業界はたくさんのまやかしに依存しているけど、僕はそれが気に入っているんだ。ソーセージがどうできるかは知りたくないからね」
代わりに彼は巨大な成功を集めたミュージシャンのための非公式なカウンセリング・サービスに情熱を注いでいる。それは人気のポッドキャスト『ジョージ・エズラ&フレンズ』と呼ばれていて、今のところ、エド・シーラン、ラグンボーン・マン、そして唯一無二のクレイグ・デイヴィッドが音楽ビジネスに関する批評的言説について話をしていた。ゲストたちはどうでした?と私は尋ねてみた。
「クレイグ・デイヴィッドはこれまで会った中でも最もポジティヴな人だったね。僕のためにビートボックスまでやってくれてね。部屋には僕と彼だけだったんだ。完璧だったよ。そうだろ?」それは一度限りだったが、もっと一般的なことも会話の話題に上ったという。「必ず僕がインタヴューした人たちはこう言うんだ。『自分のやってることが気に入っているんだ。葬式や結婚式、出産などが恋しくなることもあるけど、世界最高の仕事をやることを考えれば小さな代償だよ』ってね」
この大きな冒険が今終わってしまったら、どう思うだろうか? ジョージ・エズラの整えられた髪以上にハードな形で『ステイング・アット・タマラズ』が失敗してしまったら?「正直、それで問題ないよ。自分のやったことを信じていたら負けを認めるのも楽だと思うんだ」
「このアルバムではちょっと汚い言葉もあるんだ。これまで以上に正直になったからね。他の人を標的としたものじゃなく、自分自身に対してね。今は恋愛をしていて、書くにはもってこいの内容だからね」
恋愛中? ジョージ・エズラは既に元恋人について話をしてくれて、その人物はファースト・アルバムの「ミューズ」だったと述べている。「ピラミッド・ステージで演奏していたら、彼女が別の男性の肩に乗っているのが見えたんだ。『うーん』と思ったよね」現在の女性とはどこで出会ったのだろう?「フェスティバルで通りがかりに出会ったんだ。そうしたら同じ街に住んでいてね。いちかばちかでメッセージを送ってみたんだ。『豪華なディナーでもどう?』ってね。そうしたら来てくれたんだよ。いつも相手を探していない時にこういうことって起きるんだ」
彼女がセカンド・アルバムの恋愛ナンバーについて影響を与えたのかを尋ねると、彼は「君は誰かに向けてラヴソングを書いたことはないと思うんだけどさ」と語っている。「あれって相手が与えてくれる感情に気づくことなんだよね。『座ってくれ。今から演奏するけど、君についての曲なんだ』なんてことは絶対にないからね」
成功を収めた人物ならではの厳しく管理されたスケジュールにジョージ・エズラは忠実なため、私たちはインタヴューを終えざるを得なくなった。車に乗って、おそらく風邪薬のエキナセアを摂取しに行くのだろう。彼は力強く握手をして、再び大きな笑顔を見せ、私は『ステイング・アット・タマラズ』の途轍もなくアップビートな1曲目である“Pretty Shining People”の歌詞の数行について考えさせられることになった。彼がアルバムでもお気に入りの一節と言っていたものだ。
「Took it in turns to dream about the lottery / What we might have done if we’d have entered and we’d won / We’re each convinced that nothing would have changed / But if this were the case why is it a conversation anyway? / Are we losing touch?(宝くじの夢について代わる代わる話をした/もし買って当たったら何をするだろうって/僕らはそれぞれ何も変わらないことを分かっていた/でも、そうなら、なんでそんな話をしたんだろう/僕らはもう離れ離れになってしまったのだろうか)」
私はまさに宝くじを当ててしまった人物に会っていたのだと思う。そして、どうやら彼は自分と心を通わせてくれたようだ。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.