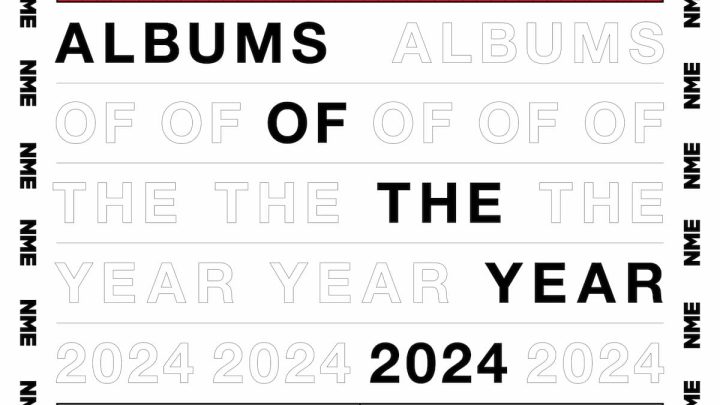Photo: PRESS
先日、『パート1』が今年のマーキュリー・プライズにノミネートされたが、フォールズが今年リリースする『エヴリシング・ノット・セイヴド・ウィル・ビィ・ロスト』という2部作は2019年のUKロックを代表する作品として語られていくことは間違いないだろう。『パート2』がつい先日、10月18日にリリースされることも発表されたが、「守られないものはすべて失われる」という意のアルバム・タイトルは2019年という時代の核心に突き刺さるものとなっている。政治も、経済も、環境も、ヒューマニティも、途轍もないスピードで拙速な変化が行われ、一方で未来は先すぼみなものに見えていく。驚異的なライヴ・バンドとして知られ、サマーソニック2019での来日も決定している彼らだが、その前にこの2部作が見据えているものは何なのかを明らかにすべく、NME Japanで行った超ロング・インタヴューを掲載する。
――『エヴリシング・ノット・セイヴド・ウィル・ビィ・ロスト』という作品はテクノロジーの面でも、政治の面でも、環境の面でも、ヒューマニティの面でも、崩壊と混乱がテーマになっているように思います。インスピレーションとなった出来事、ニュース、本、映画、アートなどで思いつくものをいくつか教えてください。
「そうだね、多くは単にニュースに接しているだけでインスピレーションを得たんだ。今はニュースから離れることができないような状況だからね。インターネットが登場する前はニュースに触れることこそできたけど、そこから身を切り離すこともできたわけでね。今は常に情報が押し寄せてくる状態だから、そういう状況自体に影響を受けたと思う。永遠に情報と接続されていて、心身が疲弊してしまうほどの、そういう状態にね。(インスピレーションになった)本もいくつかあるよ。環境問題を扱っているイギリス人作家のジョージ・モンビオットが書いた『フェラル(原題)』という書籍に、『ジ・エンド・オブ・ジ・エンド・オブ・ジ・アース(原題)』という(アメリカ人作家の)ジョナサン・フランゼンが書いた環境に関するエッセイ集。それから、『アローン・トゥギャザー(原題/注:シェリー・タークル著『つながっているのに孤独 人生を豊かにするはずのインターネットの正体』を指していると思われる)』……これは著者が誰だったか忘れしてしまったけど、インターネットとテクノロジーについて書かれた本なんだ。それも本作のファクターになったね」
――こういった本は前作『ホワット・ウェント・ダウン』のツアーが終わった後のバカンス中に読まれたのでしょうか。
「そうだね、その頃に読んだのもいくつかあるよ。バカンス中はできるだけ本を読むようにしているんだ。といっても、ツアー中も読んでいるけどね。今挙げた本が、アルバムの曲作りをしているときに頭の中にあったんだ」
――ちなみにバカンス中は敢えてネットから離れて、情報が絶えず流れてくる状態をできるだけ断ち切ろうとしたりはしたのでしょうか?
「まあね。ただ、誰もがそうであるように、情報を断つのは本当に難しいことなんだ。自分は中毒なんじゃないかって思ってしまいそうになるくらいだからね。ただ、何回かはオフラインになることができたよ。インドに行った時とかね。とはいえ、それは比較的最近になってからのことなんだけどさ。あの時はオフラインで過ごす時間の大切さに改めて気づく貴重な機会になった思う。それから、ギリシャでは人里離れた場所を旅することが多くて、そういうところはWi-Fiがあまり強くないんだ。だから、ギリシャにいる時は頭の中に余裕ができることが多かったね」
――インドでインターネットから離れた時には、アルバムのコンセプトがある意味正しかったと実感しましたか?
「そうだね。本作の歌詞では自分の心の中で一番差し迫った問題を表現したいと強く思っていたんだ。それはここ10年くらいの間に、自分たちの生活があまりに目まぐるしく変化してきたということについてなんだけどね。人間としての僕らの日々の生活に、ものすごく大きな影響を与えていることだと思うんだ。僕はそういうことを曲にしたいと思った。そういう懸念や最大の関心事をアートという形にするのが狙いだったんだ。そういう懸念を表現することによって、アルバムが外の世界とより繋がる内容のものにしたかったんだよ」
――ちなみにイギリスのEU離脱をめぐる騒動はあなたの目にはどう映っているのでしょうか? あまりに色々なことがありすぎて現状が分からなくなり始めていますが。
「EUからの離脱が完全に理解できないのは、辻褄が合わないことが多いからなんじゃないかな。今は政治的な出来事を論理的に分析するのが難しくなっているからね。然るべき形では理解不能というか、予測が難しいというか……」
――イギリスのEU離脱について、あなた自身の率直な心情を聞かせてください。
「よくないアイディアだと思うね。EUからの離脱は僕たちのためにならないと思う。イギリスはヨーロッパの一部でいるべきだと思うし、ヨーロッパの中での自国の役割に誇りを持つべきだと思うんだ。去ってしまうのは何か後ろ向きな感じがするよ。EUは決して完璧な組織ではないし、その欠点抜きに語ることはできないと思うけど、だからと言ってイギリスがそこから離れるというのは正しい選択ではないと思うんだ」
――“On The Luna”ではドナルド・トランプ米大統領にも言及されていますが、実はここ日本でも保守化が進んでいると感じています。ソーシャル・メディアの時代に入って、こうした政治的空気が顕在化してきていますが、あなたはどんな思いで見つめていますか?
「ソーシャル・メディアがそういう傾向の顕在化に影響しているという考え方には賛成だね。世界中で見られる傾向だと思う。イギリスやヨーロッパのみならず、世界的な現象になっている。ある意味では、社会が変化するスピードが速いことへの反動かもしれないなんて思ったりするんだ。インターネットを通じてグローバル化が進んでいることにみんな圧倒されてしまって、恐怖を感じてしまっているんじゃないかな。人間というのは圧倒されて恐怖を感じてしまうと、保守的になることが多いんじゃないかと思うんだ。そうすることによって、既に自分たちがよく知っているものを強化しようとするんだよ。そして、その多くは歪んだ愛国心や国粋主義と繋がっているものが多い。物事の変化のスピードが怖いから、そういうものに活路を見出すんだ。由々しきことだよね。思うに僕たちの多くは、そういう保守的なイデオロギーに過去への執着を感じているんじゃないかな。今になってそういうのが再浮上したっていうのは、なかなかにショッキングだよ。過去の過ちと同じ罠にはまらないように気を付けないといけないね」
――そうですね。あなたが言っていたように、後退してしまうことは避けなければいけないと思います。
「そうだね。それに、概して保守的なイデオロギーというのは、いつも過去を見ているような気がするよ。進歩的なイデオロギーは未来の話をしているけど、保守派の人はいつも『昔のほうがよかった』って言っている気がする。言うのは簡単だけど、過去のほうが本当によかったかどうかは僕としては疑問だね。ロマンティックに見ているだけなんじゃないかって思うよ。過去を美化しているんだ。現実的じゃない。虚構だよ」
――こうした時代になっているのは、内省する時間が減っているのが理由の一つかもしれないと考えています。なので、“Sunday”の楽曲の構造と歌詞、“I’m Done With The World (& It’s Done With Me)”には感銘を受けました。”Sunday“は波がたゆたうような感じが考える時間を与えてくれて、そこからアンビエントなものがトランス的な曲調に流れていきます。また、”I’m Done~”は物静かな、ピアノ主導型の曲ですよね。この流れは特にこういう時代にリスナーが共鳴できるものだと思いますが、“Sunday”や”I’m Done~”はどのように生まれたのでしょうか?
「実はその2曲は成り立ちが違うんだ。”Sunday”はそうだね、確かに内省を促す感じではあるな。”I’m Done~”はジミー(・スミス/ギタリスト)が中心になって曲を書いたんだ。彼がドイツにいた時に思いついて、僕にデモを送ってくれてね。僕はそれを持ってスタジオに行き、歌詞を考えた。すぐに思いついたよ。なかには以前からあたためていたフレーズもいくつかあるけど、ジミーが送ってくれたコードが僕の心と共鳴したんだ。ある意味で、この2曲は対になっているというか、どちらも炎のイメージでね。アルバムの最後のほうに置いているのもそういう理由なんだ。炎のあるイメージの中でアルバムが終わるという感じでね。質問の答えになっているかな? もっと説明した方がいいかい?」
――それでは、歌詞についても話を伺えますか? “I’m Done~”は曲が先行してできていたようですが。
「歌詞というか、ポエムだね。ジミーが曲を作って、僕は曲とは関係ないところで詩を書いていたんだ。その日、僕は朝から二日酔いですごく疲れていたんだけど、窓の外を見たら庭に怪我をしたキツネがいたんだ。ロンドンにもキツネがいるんだよ」
――そうなんですね。
「実はロンドンはキツネが多いんだ。どこにでもいるよ。1匹のキツネが家の庭に怪我をした状態で来ていて、その後亡くなってしまったから、すごく悲しくなってしまった。だから、あの曲は『キツネが庭で死んでいる(The fox is dead in the garden)』から始まるんだ」
――なるほど。
「そう。で、それとは別に、僕には終末論的な未来のイメージがあったんだ。田舎で山火事がが起きるようなイメージかな。もし自分に子供がいたとしたら、子供たちの目にはそういう世界がどんな風に映るのだろうって思ったんだ。あの曲は、そうだね、ダークなレンズを通して世界を見ているような感じかな」
――ここまでライヴをやってきて“Sunday”で熱狂するオーディエンスはあなたの目にどのように映っているのでしょうか?
「そうそう、みんなの反応がとてもよくてね。新曲がそういう形でオーディエンスの心に通じていくのを目の当たりにするのは心地がいいよ。人の心が動いていることを実感できるしね。あの曲に限らず、最初に休息を与えるようなムードからオーディエンスをエクスタシーに導くことができるというのは、最高の気分だよ」
――『エヴリシング・ノット・セイヴド・ウィル・ビィ・ロスト』(救われないものは失われる)という警鐘の対象には、ギター・ミュージックも含まれていると思いますか?
「ある意味ではそうかもね。僕がこのフレーズをとても気に入っているのは、すごくたくさんのことと通じるものがあるからなんだ。確かに最近は、ギターのあるバンドをやっていると、絶滅の危機にあるとまでは言わないけど、今までに増して貴重な存在になってきたなって思うよ。だからこそ、お互いの存在をありがたく思うようになるんだ。みんなでひとつの部屋に入って、本物の楽器を使って、一緒に音楽を作ることができることにね。確かに、(ギター・ミュージックは)このタイトルが共鳴しているもののひとつかもしれないね」
――ギター・ミュージックがオールドスクールな音楽として見なされてしまうような状況下で、本作が現在進行形なアルバムになっていることにとても感動しました。アルバムのサウンドを組み立てていく上で、どのような部分に気を遣っていたのでしょうか?
「単に、レトロなアルバムにならないように意識していたっていうことかな。いつでもフレッシュでいられるように心がけているんだ。モダンでコンテンポラリーなアルバムを作りたいと考えていたのは間違いないね。そのためにはテクスチャーに気を遣うというのが一つの方法だと思う。テクスチャーとアンビエンスがアルバムには重要なんだ」
――最近のギター・バンドで興味深いと思っているバンドを教えていただけますか?
「プチ・ノワールというケープタウン出身のアーティストがすごく好きなんだ。彼はギターを多用していて、アフリカのリズムとモダンなエレクトロニクスを融合させつつ、インディーな感覚も持ち合わせている。すごく興味深いと思っているよ。今最も心を掻き立てられるのは彼だね」
――『NME』のインタヴューでメンバーが(ストリーミング・サービスの)アルゴリズムでヒットが決まる時代を揶揄していましたが、この時代にロック・バンドやポップ・ミュージックといった芸術が成し遂げられる、アーティスト側としての達成とはどのようなものだと思いますか?
「自分がどれだけ満足できるかだと思うね。自分が作ったものに対する達成感。それがどのくらい人々の心に通じることができたかっていうことだね。通じ合えた人数ではなく、その繋がりのクオリティで測ることができると思う。僕らが重きを置いているのは、アルバムをリリースした時に、それがどの程度ファンのコミュニティに受け入れてもらえるかという部分なんだ」
――あなた自身が人生を変えられた音楽体験を教えていただけますか?
「僕の人生でかい? もちろん経験があるよ。人生を音楽に捧げたいと思うようになるには、自分以外の人からの刺激が必要だからね。幼少期の頃はピクシーズに影響を受けた。彼らの音楽を聴いてギターをやりたいと思うようになったし、音楽をやりたいと思うようになった。その後は、アーサー・ラッセルの音楽が色々な意味で僕の心を開いてくれた。その二人が挙げられるかな。他にも山ほどあるけどね」
――ファンから『音楽に共感しました』と言われた時には、どのような気持ちになりますか? ファンと交流する中で、嬉しい気持ちになるのはどのような時でしょう?
「感想を聞くだけでもとても嬉しいし、中でも、『あなたの音楽を聴いて人生が変わりました』なんて言ってもらえる時はミュージシャン冥利に尽きるよね。最高の報われ方だよ。それから、バンドの名前をタトゥーにしている人を見つけると、愛されているなって思うよね。よくファンが見せてくれるんだ。だからと言って、タトゥーを入れることをオススメはしないけどね(笑)。それほどまでに僕たちに夢中になってくれているんだって、感激するんだ。ファンからいろいろな話を聞くだけでも楽しいよ。感情的、心理的に辛い状況から抜け出すのに僕たちの音楽が役立ったなんて聞くと、音楽は人々の心理に実際に影響を与えることができるんだっていうことを実感するよ。最高の気分だよね」
――そういう感想をアーティストに直接伝えることができるのは、ソーシャル・メディアのいい面かも知れませんね。いかに人生が変わったのかを伝えることもできますし。
「そう、それは間違いないね。それがソーシャル・メディアの素晴らしい長所だと思う。いろいろな境界線を乗り越えて、より親密に相手と接することができるからね」
――本作をレコーディングしたペッカムの123スタジオはどんな雰囲気だったのでしょうか? これまでのアルバムとは異なるスタジオでレコーディングしたのですよね。
「そう。今回は自分たちの住んでいるところの近くで録音できたのが大きかったと思う。地域に根ざしているという実感が強かったんだ。地元という環境が、制作する過程で役に立ったと思う。特に歌詞の面では、地元にいたおかげで周りの人たちが抱えている問題にグッと感情移入することができたしね。スタジオそのものというよりも、スタジオの周りの環境が役に立ったと思っている。イギリスのスタジオだったし、イギリスから見た世界の感触を得ることができたからね」
――ご近所なんですね。
「まぁ、ものすごく近所というわけではないけど、僕は歩いてスタジオに行っていたよ。10分ちょっとだったかな」
――歩くのにちょうどいい距離ですね。往復する中で、世の中の状況を垣間見ていたという感じなのでしょうか。
「そうだね。歌詞の多くは、スタジオを出た後で寄るパブで書いていたんだ。地元にパブがあってさ、そこで書いていたんだよ。その時は気が付かなかったけど、今になって思うと、一つのコミニュティのような環境だった。人に囲まれながら書いていたわけでさ。そのことが、外の世界と繋がることに役立った気がする。もしプライベートな空間で書いていたら、もっとプライベートな歌詞になっていたかもしれないからね。公な環境の中で書いていたからこそ、他の人たちのことをより考えながら書くことができたのかもしれない」
――“White Onions”などを聴くと、個人的には『パート1』だけでもギター・ミュージックの復権を叶えてくれたアルバムだと思っています。『パート2』はさらにギターに重きを置いたアルバムになるとのことですが、この順番でリリースしようと思った理由を教えてください。
「とりわけ、歌詞の物語の流れがそうさせたんだと思う。アルバムの中で感情の移り変わりみたいなものがあるんだけど、僕たちが決めた『パート1』の曲順からすると、『パート2』は第2章の始まりみたいな感じに僕たちは考えているんだ。そういうわけで、『パート2』を先に出してしまうと意味を成さなくなってしまうっていうね。『パート2』は『パート1』が終わったところから始まるんだ」
――なるほど。『パート1』は”I’m Done~”で静かに終わりますが、『パート2』はまったく違う雰囲気で始まるのでしょうか。
「そうだよ」
――それは楽しみです。…ところで本作は『パート2』も含めると6作目のアルバムになり、あなたがレコーディング・アーティストとしてデビューしたのは2008年だったので、その時からは10年以上が経過していることになります。ところが、2000年代にデビューした多くのロック・バンドが今となっては既に解散してしまっていますよね。それこそアリーナ・バンドやヘッドライナー級として生き残っているのは、アークティック・モンキーズやブリング・ミー・ザ・ホライズンぐらいではないかと思ったりもします。フォールズはなぜ生き残れたのだと思いますか?
「アルバムを出す時に進歩できるように心がけているとは言えるかな。どうにかして進化したいと思っている。それから、バンド内での友情も役に立っていると思うな。自分たちがやっていることにやりがいを感じていられるのは、僕たちが自分たちの歩んでいる道にワクワクしていられるからなんだ。止めたいと思ったことは一度もないよ。それが大きいと思う。あとはやっぱり、ファンが素晴らしいっていうことかな。みんな僕たちの歩んでいる道を理解してくれているし、ずっとついて来てくれているんだ。最高だよね」
――とても忠誠的なファン・ベースなのですね。
「そう、そうだと思うね。それよりも、僕たちがやろうとしていることを理解しようという意欲を持ってくれているんだと思う。同じことを繰り返すのではなく、進歩しようとしているっていうことをね。それがファンにとって興味深いものとして映ってくれていることを願うよ」
――フォールズの音楽を最も最高の形で享受できるのはライヴだと思います。今回のツアーはどのようなものにしたいと考えていますか? 5曲くらいの新曲をセットリストに入れていると言っていましたが、今年はたくさんツアーがありますよね。
「そうだね。今年は8月の終わりくらいまでは、『パート1』の曲をやることに専念する。もちろん、これまでの4作からの曲も入れるつもりだよ。『パート2』をリリースしてからは、大胆にセットリストを変えるつもりなんだ。『パート2』と『1』に、昔の曲を織り交ぜてね。ショウの時間も少し長くなるんじゃないかな」
――最後の質問です。『NME』のインタヴューで「実際のところ、ギターを弾いたり自分たちの方法で取り組んだりすることは、ある種のレジスタンス的な行為」だとおっしゃっていましたね。その真意をもう少し教えていただけますか? 演奏するのが抵抗だというのはとても興味深いと思いました。
「ほら、ギター・ミュージック自体がどんどん希少なものになっているわけでね。ソフトウェアを多用するバンドが増えているし、『バンド』という概念すらオールド・ファッションなコンセプトになりつつある。若手のミュージシャンの多くが、パソコンのソフトウェアを使って自分だけで曲を作っていたりする。過去にはできなかった手法だよね。だから、そういう時代において一つの部屋に友だち同士が集まり、本物の楽器を使いながら人間同士の繋がりを通じてマジックを生み出すということには、何か特別なものを感じるんだ。一人が一人のパソコンとの関係で生み出すものと比べてね」
――それはまったく同意します。一方で、常に進歩し続けていくこととの兼ね合いを考えて、ギターの比重を減らしたりですとか、コンピューターの比重を増やすことでしたり、そういうことを考えたことはありますか?
「今回はシンセサイザーを多用しているし、そこにはコンピューターの要素がある。でも、もっと大切なのは、人間同士の繋がりなんだ。人間同士がコラボしているというのがバンドの重要なところだと思う。人間とパソコンの関係というのはそれよりも特別感がないとまでは思わないけど、あまりに普通のことになってしまったから、他人とコラボレーションできることの特別感が強まっているとは思うね」
――こちらこそありがとうございました。サマーソニックでの来日を楽しみにしています。
「楽しかったよ。ありがとう!早くみんなに会いたいよ!」
来日公演
SUMMERSONIC 2019
8月16日(金)17日(土)18日(日)
ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
舞洲SONIC PARK(舞洲スポーツアイランド)
作品情報

アーティスト:FOALS / フォールズ
タイトル:EVERYTHING NOT SAVED WILL BE LOST PART1 / エヴリシング・ノット・セイヴド・ウィル・ビィ・ロスト・パート1
品番:SICX-122
価格:¥2,400+税
仕様:歌詞・対訳・解説付
発売日:2018年3月8日(海外同発)
1. Moonlight
2. Exits
3. White Onions
4. In Degrees
5. Syrups
6. On The Luna
7. Cafe D’Athens
8. Surf Pt.1
9. Sunday
10. I’m Done With The World (& It’s Done With Me)
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.