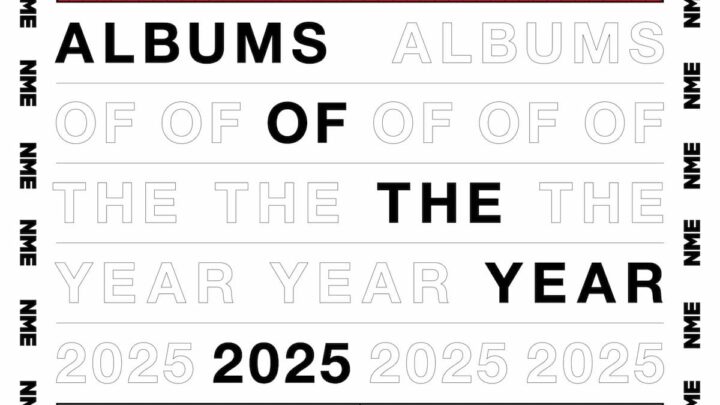Photo: PRESS
ミューズの「ドローンズ・ツアー」のサポート・アクトへの抜擢や、今年のグラストンベリー・フェスティバルではリアム・ギャラガーと同じステージに出演するなど、デビュー以来順調にキャリアアップを果たしてきたナッシング・バット・シーヴスは、今の時代においてもイギリスならではの真っ当なロック・サウンドを真正面から奏でられるということを証明してきたバンドである。しかしながら、一見すると順当にステップアップしてきた印象の彼らも、この2年の間には解散危機も経験したのだという。そんな彼らがアークティック・モンキーズらを手がけたマイク・クロッシーをプロデューサーに起用して作り上げた新作『ブロークン・マシーン』は、一度壊れてしまったものから美しいものを生み出すことがテーマになっている。ここに掲載するのは、ヴォーカルのコナー・メイソンとギタリストのドム・クレイクによるインタヴューだ。アルバムのソングライティングも手がけている二人が、アルバムに込めた思いやリリースまでの2年間について率直に語っている。
――素晴らしい新作『ブロークン・マシーン』を聴かせてもらいました。メロディアスで繊細で美しいパートはとことんそれを突き詰め、ラウドでノイジー、激しくのたうつロック・パートもとことんそれを突き詰めるという、前作にもあったそんな両極をさらに押し広げていった作品だと感じました。あなた方自身の手応えを訊かせてください。
コナー・メイソン 「君が今言った通りだと思う。ドンピシャだよ。前作でやったことをさらに極めた感じだ。と言うのも前作は、手探り状態で自分たちらしさを探っていた中から生まれた楽曲から成り立っていたわけでね。曲を作り始めたのだって17歳、18歳で、まだ全然若かったんだ。自分たちがどういうバンドなのか、ミュージシャンなのかを知る過程で書いた曲だった。今作は、ある特定の時間、場所で生まれた曲から成り立っていてね。ツアー中、6ヶ月かけてこのアルバムに向けて曲を書いたんだ。その時に自分たちが直面していたことが曲に反映されている。より時間と場所が特定されているんだ。そこが面白いと思う。あとは君が言ったように、前作でやったことをさらに極めることができたんだ。ソングライターとしてもミュージシャンとしても成長した証だと思うし、自分たちのこともより分かっている。それは長いツアーであったり、経験を重ねたことの結果だと思う」
ドム・クレイク 「でも、意識的にやったわけじゃないんだ。レコーディングの過程で気づいたらそうなっていたっていう。今作は曲作りの方法が前作と違っていたんだ。今回は曲作りをツアー中に行っていてね。ツアーに出っぱなしだったから、ホテルの部屋やツアーバスの後方にスタジオを持ち込んで、曲作りができる時間を見つけたら、そこで曲を書いたんだ。だからアルバムをレコーディングするという段階で、40曲もの候補曲があった。そこからみんなでじっくりと『誰がどの曲を気に入っているか』、『どの曲をレコーディングするべきか』といった話し合いをした。その2ヶ月後には完成していたよ。いい感触を感じているよ。前作から確実に成長している。どんなバンドも、アルバムを作る毎に前よりも色々なことが分かってくるんだと思う。僕たちの場合、まだ行き当たりばったりなところはあるけどね。でも今作はすごく手応えを感じているよ。早くリリースされないかって待ち遠しいね」
――本作でバンドとして目指した方向性、コンセプトはどういうものでしたか?
コナー・メイソン 「そうだな。ナッシング・バット・シーヴスの場合、自分たちを型に嵌め込むことは絶対にしたくないし、方程式を当てはめることもない。自然に思いつくがままに曲を書くことに尽きる。そしてそれを楽しむこと。やる以上は楽しめなきゃだめだと思うんだ。何をやるにしてもね。僕たちの場合、自分たちで作った曲をとにかく楽しむことが大事だった。所謂『アーティスト』としての一番の醍醐味は、自由に自分たちが作りたいものを作るということだ。そうやって僕たちはずっとやってきた。と言いつつ、今作の方がずっと作品としてのまとまりがあると思うし、ある時間と場所から生まれた11曲と言えるね。自分たちとして目指したサウンドもあったけど、それはレコーディングの段階での話なわけでね。曲作り、デモ作りの段階は、『なんでもあり』だからさ。ものすごくロックなものもあれば、メロディアスなものもあるし、純粋で美しいパートもあって、前作よりもさらにそれを突き詰めた。ただ言えるのは、今作の方がまとまりがあるっていうことだね。テーマと言えるものがあるんだ。ビデオやアートワークにしても今作の方が一貫性がある。それは、バンドとして長く活動してきた結果だと思う。経験からきていると思うよ」
――アートワークは「金継ぎ」がモチーフになっているようですが、金継ぎという日本伝統の技術についてどこで知ったのですか?
ドム・クレイク 「どこで知ったのかは覚えていないな。日本にいた時に誰かに教えてもらったのかな。何かの時に目にして、メンバーの誰かが『アートワークかグッズのデザインに使ったら面白いね』って言ったんだ。それで、今作が絶好のタイミングだろうと思ってモチーフとして使うことにしたんだよ」
――一度はバラバラに請われてしまったものの不完全さを敢えて生かした美しさ、金継ぎにはそういう禅の哲学があるわけですが、それはこの『ブロークン・マシーン』というアルバムにも通じるものがあると言えますか?
ドム・クレイク 「歌詞の面で通じるものがすごくあると思うし、一方で、音楽的な部分でも、不完全なものがある。レコーディングの段階で、ちょっとした間違いなどをわざと残しておいたんだ。その方が人間臭くて味があると思ったからね。『金継ぎ』を初めて見たときにすごく印象的だったのは、その背景にある哲学も含め、自分たちの身に起きている事や、過去に起きたことと通じるものがすごくあると感じたんだ。出会うべきして出会ったと思えたほどさ。『これしかない』と思ったんだ。何ヶ月もの間、いろんなアーティストから、『金継ぎ』をモチーフにしたアートワークを募ったんだけど、これというものがなくて、2週間前にスティーヴ・ステイシーという前作のアートワークも手がけてくれたアーティストからデザイン案が届いた時、それがあまりに素晴らしくて嬉しさのあまり発狂しそうだったよ。本当に美しいものに仕上がったと思う。意外性もあってすごく満足しているよ」
コナー・メイソン 「金の液体を使って修復することで、元々のものよりも美しいものを生み出す、という発想がまさにこのアルバムの曲に込めた思いだったり、アルバムが伝えようとしていることを包括していると思って、『これしかない』と思った。アルバムのテーマにぴったりだってね。本当に素晴らしいものに仕上がったよ」
――ツアー中6ヶ月かけて曲作りをしたと言うことですが、どのようなタイミングで始まったのか教えてください。まとまった時間を充てて曲を書いたのか、断続的に書き続けていたものなのか。
コナー・メイソン 「前作から2作目に向けて曲作りをやめなかった、ということかな。前作を作るのに時間が本当にかかったから、2作目では曲が足りないという状況を作りたくなかったんだ。だからそのまま継続して曲を作り続けた。今、振り返ってみても、自分たちはすごく意欲的だったと思う。でも、そこから長いツアーが始まったんで、中断を余儀なくされてしまってね。『曲作りを続けるにはどうしたらいいか』って考えた結果、録音機材をツアーバスに持ち込めばいいってことになったんだ。そうやって6〜7ヶ月の間、ツアーバスに機材を持ち込んで作業することが何度もあったよ。そうやって進めていったんだ。うまくいったと思う。最初慣れるまでは大変だったけどね。理由はいろいろあるけど、何よりツアー生活の中で自分たちの時間を見つけることがそもそも難しい。でもそこをなんとか頑張って、かなりいいものが生まれたと思うよ。あの環境でデモ作りをしたことが、曲にいい効果をもたらしたと思っている」
――前作のリリース後、ツアーを挟んでの2年の間にはバンドの危機的状況もあったようですね。できたらどういうことだったのか訊かせてもらえますか? 今振り返って、あなたたちを追いつめていたのは何だったのか、またそこからブレイクスルーするきっかけとなったこととは?
コナー・メイソン 「まさにそのツアーでのことだった。さっきも大変だったと言ったけど、僕自身不眠や健康状態で本当に苦労したんだ。精神的にも追い詰められてしまってね。バンドとしても、僕自身も危機的状況に陥った。何ヶ月もの間、全然眠れなくて、その結果、不安神経症と鬱になってしまったんだ。そしてあるツアーを終えた時点で、バンドの他のメンバーに言ったんだ。『助けが必要だ。でなきゃ、これ以上続けられない』ってね。その時にバンドとして今後どうするのかと言う話し合いを持った。スタッフもメンバーもレーベルも親身になって助けてくれたよ。『きちんと手当をして治そう』と言ってくれた。突発的な症状だったんだ。長年抱えていたわけではなくね。当時、いくつか悩みを抱えていて、それを自分だけでは背負いきれなくなって押しつぶされてしまった。それにプレッシャーもあった。悩みを抱えながら、過密なツアー日程もこなさなければいけなかったわけでさ。その組み合わせがまずかったんだ。長いツアーが一段落して、家に1ヶ月ほど戻った際に、自分で乗り越えようと決めて医者にも行ったよ。もう無理だと思ったんだ。この先ツアー生活がずっとこんなだったらと不安で仕方なかった。だからみんなに『一回リセットして自分を取り戻さなきゃダメだ。これ以上続けられない』と言ったんだ。そしたら、みんながすごく助けてくれたんだよ。アルバムには、このことに触れている曲もいくつかある。僕たちが経験したあの短い期間と場所、みんなでそれとどう向き合ったかっていうね」
ドム・クレイク 「どんなに前もって覚悟を決めていようと、実際のツアー生活に備えることは不可能なんだ。人から教えてもらえるものでもないしね。常に移動の連続で、家から離れて、家族や友人とも離れて、スーツケースに詰め込んだ身の回りのものだけで暮らす。ツアー中はアドレナリンが駆け巡る興奮状態の毎日で、でも家に1週間帰ると今度はライヴをやらないからその興奮が奪われて、またツアーに出るっていう。しかも行ったことのない場所に行って、言葉が通じなくて、とにかく計り知れないものがあるよ。メンバーそれぞれ受け止め方があったと思う。特に去年、アメリカを回った時は、ツアー日程があまりに長く過酷だったせいで、コナーは不眠に悩んでたこともあって本当に苦しんでた。その時点でバンドを続けられるかも分からなかった。『彼がこれを楽しめなくて、苦しんでいるのであれば、これ以上は続けられない。なぜなら、僕らは第一に友達だから。僕たちだって人間だ。音楽も自分たちにとってもちろん大事だよ。でもその思いが、人としての判断を左右させててはいけない。友情に影響を及ぼしてはいけない』といった会話をしたんだ。おかげで僕たちは友達として結束がより強くなったよ。一方で、コナーはすごく強い人間で、曲作りの時に彼が経験した辛い経験のネガティヴなエネルギーをポジティヴなものに向かわせたんだ。だからアルバムには精神衛生上の葛藤について歌っている曲もあるけど、政治について触れている曲だってある。君もご存知の通り、イギリスとアメリカを筆頭にいろいろなことが起きているからね。他には、信仰について言及している曲もある。宗教そのものというよりも、自分たちの身近で交わされる会話だよ。今、挙げたどの題材にしても、その根底に目を向けてみると、この世に存在するいろいろな制度や仕組みというのは、長い間続いていると思い込んで、それが当たり前だと思って無意識に受け入れてしまっているっていう、その発想に僕たちは異議を唱えているんだ。だから、僕たちはアルバムのタイトルを『ブロークン・マシーン(壊れた機械)』にしたんだ。なぜなら、僕たちが住むこの機械的な世界は、必ずしも完璧だとは限らないからね」
――制作に当たってインスピレーションを得たアーティストや作品、もしくはモノに限らず経験や体験があったら教えてください。
コナー・メイソン 「特定のアーティストや作品というのはなかったと思う。それでよかったと思っているけどね。前作は、僕たちがそれぞれ影響を受けたものが坩堝となった作品だったけど、このアルバムは僕たち自身の創造性を発揮して、自分たちがやりたいことをやったんだ。だから他のアーティストからのインスピレーションというよりも、自分たちの中から出てきたものを信じて、それをとことん極めて形にしていく、ということだった。と言いつつも、インスピレーションを得たものは他にいろいろあってね。アルバムの中で触れているテーマとしては、政治、信仰、それと心の健康といったものがあるけど、『ブロークン・マシーン』という作品全体のテーマというのは、表向きは機械的だったり、厳格に管理されているように見えるもの、例えば愛、政治、信仰、心の健康というのは、一皮剥いてしまえば、水面下では物すごく不安定なもので、壊れてしまっていたりするからこそ、じっくり時間をかけてしっかり取り組まないといけない。というのがこのアルバム全体のテーマになっているんだ」
ドム・クレイク 「そうだな、今はいろいろな違う種類の音楽を聴いているからね。まず心奪われるのは『いいグルーヴ』だね。思わず踊りたくなったり、身体を動かしたくなるようなものにね。音楽にエネルギーがあるのが大事だと思う。それと同時に、個人的にはサウンドも大事な要素で、誰も聴いたことのないサウンドと出会うとそれが曲のインスピレーションにもなるんだ。だから、このアルバムにしても、すべての曲のどこかしらに、聴いた人が『この音は何の楽器?』、『何の音?』と思ってしまう瞬間をもたしたいと思った。例えばある曲の冒頭2秒を聴いて、どうやったらそんな音が出せるか想像できない、と思わせる。冒頭の数秒を聴いてリスナーの頭の中に『?』を芽生えさせる。そういうのができたら個人的にワクワクするんだ。具体的な音楽だと、バンド内で好きな音楽はすごく幅広くてね。ポップも好きだし、コナーは古いジャズやブルースが好きで父親が昔家の中でカントリー・ミュージックをよく彼に聴かせていたんだ。一方でジョーはロックンロール一筋でフー・ファイターズだったり、先週はトム・ペティーを見に行ってた。僕はもっぱらフルームやグライム・ミュージック、ヒップホップを聴いているけど、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジにどっぷりハマることだってある。というように、本当にバラバラなんだけど、だからこそ、すごく幅広い音楽の坩堝が生まれるんじゃないかな」
――歌詞のテーマで政治、信仰、心の健康という話がありましたが、やはり今の世界情勢からの影響もありましたか。
コナー・メイソン 「もちろん。2016年を経て、何も言及しないわけにはいかないからね。怒りをぶつけずにはいられなかった。自分たちの心に何らかのの影響を与えたことを歌にして音楽を通して思いを伝えることが僕たちにとって大事なんだ。去年の政治について言及することはすごく大事だと思った。アルバムには他にもいろいろなテーマがあるから、1曲だけではあるんだけど、“Live Like Animals”という曲がそれだよ」
――前作の成功はプレッシャーになることはありませんでしたか?
コナー・メイソン 「プレッシャーなんて今まで信じてなかったけど、実は1月にレコーディングに入る2週間前になっていきなり物凄い緊張に襲われたのを覚えているよ。『このままレコーディングに入っていいのか?』、『いいものを果たして作れるのか?』という不安がよぎったんだ。でも、いざレコーディングが始まってしまえば、すべてが合致したんだ。個人的には前作の10倍いいものができたと思っているよ」
ドム・クレイク 「僕はなかったね。なぜかと言うと、前作がリリースされる前から既にこの2作目の曲作りを始めていたからさ。あとになって窮地に追い込まれることのないように、そうしたんだ。他のバンドの友達から聞いていたんだよ。デビュー作をリリースして、何年もツアーをしてから、いざ2作目のレコーディングをしようと思ったら、準備不足だったっていう話をね。すごく苦労したって。彼らの過ちから学んで、『できるうちから曲作りを始めよう。ちょっとしたアイデアでもいいから。2作目を作ろうと思ったときに曲が足りないってことにならないように』って自分たちに言い聞かせていたんだ」
――本作はロサンゼルスでレコーディングしたそうですが、レコーディングのプロセスや方法論において前作と意図的に変えてみたことは?
コナー・メイソン 「今回違ったことと言えば、まずレコーディング期間が6週か7週だったということ。前作は断片的に1年掛ったからね。なかなか納得できなかったり、確信が持てなくて録り直してを繰り返した。というのも、自分たち自身についてだったり、レコーディングのプロセスが今ほど分かっていなかったんだ。あれから3年が経ったわけで、その間、多くのことを学んだ。あらゆることをね。おかげで作業がずっと速く進んだよ。今回レコーディングを行った環境も良かったんだと思う。ロサンゼルスは天候もいいし、宿泊していた家もよくて、週末はオフだったんだ。前作は例えば4週間休みなしでぶっ続けで作業して1ヶ月オフをとる、っていうあまりいいやり方ではなかったんだよね。今回は週末はしっかり休んで、7週間で完成させた。週末でしっかりリフレッシュして、またしっかり作業に集中するっていう。一日11時間は長いけど、まとまった期間に集中してやるのはレコーディングことだけを考えてやれるからいい。ある時、取り組んでいた曲のドラムの音が頭から離れなくて一晩中眠れなかったこともあったけど、それだけレコーディングに全神経を注いでいたわけでさ、よかったと思うよ」
ドム・クレイク 「前作のレコーディングはちょっと手間取ったんだよね。1年も掛かってしまったわけでさ。あまりに優柔不断で、自己批判がひどくて、何度も録り直しをするはめになってね。ピシャリと『もうこれで完パケだ。もう手を加えられない』と言ってくれるプロデューサーなのか誰か第三者が必要だった。今回はとても親しくしているマイク・クロッシーとのレコーディングだったんだ。才能に満ちたプロデューサーだよ。彼はとにかく作業が速いんだ。二つのスタジオが隣同士にあって、その両方で常時何か作業が行われていてね。だから手を止めて考える暇がないんだ。決断して、録って、『はい、次』と言う具合にどんどん進んでいったんだ」
コナー・メイソン 「実はつい今彼から携帯にメールが届いたところなんだよ。『アルバムにはすごく満足しているよ。今でも聴いているし、最高のアルバムだ。リリースが待ち遠しいね』と言ってくれたよ。とにかく最高だったね。人として素晴らしいんだ。そこが一番かな。もちろん、彼がこれまで手がけて来た作品もすごいよね。フォールズやアークティック・モンキーズといった素晴らしいバンドばかりだ。でも、それよりも陽気なアイルランド人という彼の人柄が一番大きかった。接しやすくて、人格者で、音楽の才能も素晴らしいし、音楽オタクでもあるっていうね」
ドム・クレイク 「そうだな。彼はシンプルなものが好きなんだ。すごく大事なことだと思う。あとは……僕自身もプロデュースをするから、技術的な面、機材、ドラム・サウンド、といった普通の人が気にしない部分で随分勉強になったよ。数ヶ月の間、学校に通っているみたいだったね。最高だったよ。あと彼はこれまで誰もやったことのないやり方でコナーの歌声を扱ったんだ。コナーはいろいろな声色を持っているんだけど、彼はそれら一つ一つに名前をつけたんだ。10パターンもあるコナーの声に、例えば『ここのパートはボブに歌ってもらおう』、『ここはジェフで行こう』と言って指示を出すんだ。各パートをどう歌うか、二人だけの暗号があるみたいだった。側から見ていて『すごい』と思ったな。コナーの歌声の多彩さを改めて知ったよ。コナーはそれらをどう引き出して、上手く曲の中で生かしていくかを学んだと思う」
――「あのハイトーンの歌い方」といった呼び方ではなく、人の名前を声色にそれぞれつけたんですね。
ドム・クレイク 「そうなんだよ。一つ一つの声を識別するのに一番手っ取り早い方法さ」
――面白いですね。
ドム・クレイク 「そう。コナーはいろんな歌い方ができるからね。同じ単語でも、歌い方によって発音が変わってくるし、腹から歌うのか喉で歌うのかでも声が変わってくる。そこで『あの曲のAメロを歌った感じで』と言う代わりに、一言『ボブ』と言えばどの声か分かるんだ。実際どんな名前をつけたか忘れてしまったけど、どれもかなり馬鹿馬鹿しい名前ばかりだったよ」
――レコーディングの中で最も飛躍した曲は?
コナー・メイソン 「多分、ファースト・シングルの“Amsterdam”じゃないかな。あの曲をドム(・クレイク)とジョー(・ラングリッジ・ブラウン)と僕とで最初に書いた時、僕は『これ、いいじゃん。絶対にいい曲になる』って確信したんだけど、他の二人は『それほどでも』という感じでさ。それで、『レコーディングしてみてどうなるか見てみよう』と思ったんだけど、実際にレコーディングするまで彼らを説得しなきゃいけないくらいだったんだ。『これ絶対に最高だからレコーディングしようぜ』っていう具合にね。僕以外はみんな『そうかな』ってあまり乗り気じゃなくて。『まあまあじゃん。他にもいい曲があるからシングルではないよ』ってさ。でも、僕は最初の書いた時からフー・ファイターズの“Monkey Wrench”やクイーンズ・オブ・ザ・ストーンエイジの“No One Knows”を初めて聴いた10代の頃の自分を思い出していたんだ。腹の底に響くギター・ロックっぽさを感じていた。最初にデモを録音したとき、歌入れをしてヴォーカル・ブースから出たときは汗だくで息も切れ切れだったよ。『これは本当に最高のものになる』と興奮したね。それから、レーベルに聴かせた時に、レーベルの社長に『これをファースト・シングルにしたい』って言ったんだ。その時のドムの表情ときたらもう。俺の方を見て『マジか』って言ったんだ。『まだ分からない』って。それで、そのデモから曲が徐々に進化してく中で、ストレートなロックではなく、もっと音楽的に凝ったものになっていったんだ。それでも核には最初に書いたときに僕が惚れ込んだ腹の底に響く感じがまだ残っていてね。結果的にこれをシングルに頑張って押してよかったと思っているよ。普段は自分の意見を何が何でも押すタイプじゃないんだ。でもこの曲をファースト・シングルにすることだけは譲れなかったね。そうしてよかった。反響がすごいんだ。これまでの自分たちのどのシングルよりも反響があるね。ライヴでも感じるんだ。ラトビアやフィンランドで初めてライヴをやったとき、なんとなく聴いたことがあるという感じでみんなライヴを聴いていたんだけど、“Amsterdam”を演奏すると、みんな一緒に歌って、踊って、まるで何年も前から知っているという反応だったんだ。僕が最初にこの曲を耳にしたときもそういう感覚だった。『これは最高に盛り上がるはずだ』って確信があったんだ」
ドム・クレイク 「僕は“Particles”という曲かな。最初はサビしかなくて、それ以外のAメロやBメロはできてなかったんだ。僕が書いたインストはできていてね。3分半のトラックで、サビにいくまでは何も入っていない状態だった。レコーディングの最初の週に、マイクから2階に部屋を用意するから曲を仕上げるようにと言われたんだ。そしたら信じられないことに30分後に曲ができていたっていうさ。完璧なAメロとBメロに完璧なブリッジもできた。それが加わったことでサビまでもが前よりもよく聞こえたんだ。マイクが2階に完成した曲を聞きにきたのを今でも鮮明に覚えているよ。僕たちがクリスマス当日の子供のように興奮して『聴いてみてよ。最高だから』と言って聴かせたら、彼は満面の笑みを浮かべてくれた。その時に彼が『これで決まりだな。もう手を加えなくていい。保存しよう』って言ったのを覚えているよ。そして『今から早速ドラムを録ろう』とも言ったかな。曲が完成した10分後にはもうレコーディングしていたね」
――では、最もゴールに辿り着くのが難しかった曲は? 理由も含めて教えてください。
コナー・メイソン 「おそらく、“Live Like Animals”という曲じゃないかな。最初はリフしかなかったんだ。最高のリフでさ。僕からするとドムの性格がそのまま音になったっていう感じでね。突飛でナンセンスでクレイジーな彼そのものだ。最高のリフでさ。彼には脱帽するよ。それで、まあ、そのリフがまずあったんだけど、その上に歌を重ねるのが本当に難しかった。不規則で構成もないようなもので、形にするのに物すごく時間が掛かったんだ。レコーディングしながら構築していったという感じでね。ギリギリのところでできたわりにはいいものができたと思っているよ。何が違うって、僕がラップっぽいことをしていることだよ。ラップそのものというよりも、むしろLCDサウンドシステムっぽい語り口調だけどね。でも、あの曲でかなり限界を押し広げたっていう手応えはある。あんな曲はこれまでなかったからね。そこが気に入っているよ。他と本当に毛色が違う曲だね。一番苦労した曲だったよ」
ドム・クレイク 「何があったかな。そうだ、“I Was Just A Kid”という曲があるんだけど、去年のクリスマス前に自分たちで『エアビーアンドビー』で宿を海辺に抑えたんだ。言っておくけど、イギリスの12月の海辺は決して快適な場所とは言えないからね。周りに何もないところで、僕とコナー、ジョーとでスタジオを設置したんだ。他から完全に隔離された環境でね。そこで『アルバムのオープニング曲が必要だ』って話になってさ。爆発的で、興奮を呼ぶ、予測不可能の展開の曲がまだ自分たちにはなかったんだよ。そこで曲を書き始めたんだ。冒頭のぶっ飛んだドラムのイントロを僕が提案して、そこから曲を書いていった。そしたらAメロの後の部分で煮詰まってしまったんだ。『この後どうする?』って顔を見合わせたまま、みんな戸惑ってしまってね。だからそのまましばらく寝かせることにしたんだ。で、ロサンゼルスに飛ぶ直前になって、コナーだったかジョーだったか忘れたけど、『あの時の曲覚えている?』って話になって、保存しておいたものを引っ張り出して聴き直したんだ。『すごくいいじゃん』ってなってね。曲が完成できるかやってみようってことになった。今まさに僕がいるこのベッドルームに1人で集まって、保存したファイルを開けて、続きを書いたんだ。それからロサンゼルスで、一つにまとめて完成させたんだよ。1ヶ月以上掛かってできた曲だった。2ヶ月近かったかもしれないな。つまり、1時間でさっと書けたって曲ではなかったということだよ。あの曲のサビがまた面白くて、もともとの構成はA・Bだったのが最終的にB・Aに入れ替わったんだ。つまり、最初は“I Was Just A Kid”という歌詞から入って、その後に『アアア~』というコーラスが続いたんだ。でも途中でそれを入れ替える事にした。そしたらもっと良くなったっていう」
リリース詳細

ナッシング・バット・シーヴス
セカンド・アルバム『ブロークン・マシーン』
<国内盤CD>
2017年9月13日(水)発売
全17曲 2,200円+税 SICP-5578
国内盤ボーナス・トラック2曲収録
<輸入盤CD>
2017年9月8日(金)発売
<デジタル配信>
2017年9月8日(金)配信開始
01. I Was Just A Kid | アイ・ワズ・ジャスト・ア・キッド
02. Amsterdam | アムステルダム
03. Sorry | ソーリー
04. Broken Machine | ブロークン・マシーン
05. Live Like Animals | リヴ・ライク・アニマルズ
06. Soda | ソーダ
07. I’m Not Made By Design | アイム・ノット・メイド・バイ・デザイン
08. Particles | パーティクルズ
09. Get Better | ゲット・ベタ―
10. Hell, Yeah | ヘル・イェー
11. Afterlife | アフターライフ
12. Reset Me | リセット・ミー ※
13. Number 13 | ナンバー・サーティーン ※
14. Sorry (Acoustic) | ソーリー(アコースティック)※
15. Particles (Piano Version) | パーティクルズ(ピアノ・ヴァージョン)※
16. I Need Air (Demo) | アイ・ニード・エアー(デモ)*
17. Stuck On You (Demo) | スタック・オン・ユー(デモ)*
※=輸入デラックス盤&国内盤のみ収録
*=国内盤ボーナス・トラック
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.


_2563 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415lxbfrdVL._AC_SL1000_.jpg)