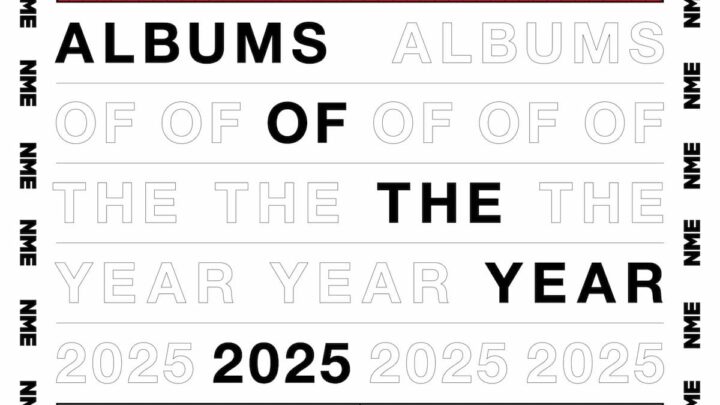Photo: PRESS
ロックンロールの裏の裏を知り尽くしたヤクザ者が、ダンス・ミュージック界の貴公子を連れて、更なる悪役(ヴィラン)として帰ってきた! クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジにとって通算7作目となった『ヴィランズ』は今年を代表する傑作である。タイトルである『ヴィランズ(悪党)』について、「ロックンロールは最高にダーティーで、同時に最高にピュアなものなんだ」とジョシュ・ホーミは説明している。マーク・ロンソンとの共同作業は少々意外に思えるかもしれないが、ジョシュ・ホーミ自身が豪語するように、一曲目の“Feet Don’t Fail Me”を聴いた瞬間に、彼らが生み出す化学反応に「あらゆる先入観」が吹き飛んでいくのだ。全英1位、全米3位を獲得した本作を完成させたジョシュ・ホーミのインタヴューをここにお送りするが、ロックンロールの裏街道を回り回ってきた彼らだからこそ、こんなにも最高に純粋無垢なロックンロール・アルバムを作り上げることができたのだ。
――新作『ヴィランズ』はどんなアルバムでしょうか?
「『ヴィランズ』はクイーンズが新しいものを探して出る旅路であり、とても誠実なアルバムなんだ。俺たちのアルバムは、数枚ごとにグループ分けすることが出来るんだよ。最初の3枚は三部作で、『ルールなんかない。何をやっても自由』というステートメントだったんだ。それに続く『ララバイズ・トゥ・パラライズ』(2005)『エラ・ヴルガリス』(2007)は自分たちの足場を見出すものだった。そして前作『…ライク・クロックワーク』(2013)と『ヴィランズ』は、俺たちが築いた足場を軸にして、さらに前進していく作品になんだ。過去にやってきたことの影響はあるけど、同じ地点に留まることなく、過去を燃やし去りながら新しい道を進んでいくことが大事なんだよ。前作から始まった新章が次のアルバムまで続くのか、それとも『ヴィランズ』で完結するのかまだ分からないけど、クイーンズの歴史において最も充実してエキサイティングな時期のひとつであることは間違いないよ」
――マーク・ロンソンによるアルバムのプロデュースは、どのようにして実現したのですか?
「俺たちはずっと前から相思相愛だったんだ。マークは『R指定』(2000)の頃からクイーンズのファンでね。それに俺は彼の“Uptown Funk”(2014)が大好きで、家族でよく聴いていたんだ。彼の方が先に惚れたから、俺の勝ちだな(笑)。俺たちは新しい価値観を築こうとしてきた。それには古い価値観を捨て去らなければならないんだ。何を残すか、何を捨てるかの選択肢があったんだ。『俺たちがモダンになったらどうなるか?』という命題を実現するにあたって、マークは不可欠な要素だった。このアルバムはタイトでドライなサウンドにしたかったんだよ。『ハァ?マーク・ロンソンがクイーンズをプロデュース?ふざけるなよ』と思ったファンがアルバムを聴いたら、そのサウンドにあらゆる先入観が吹っ飛んでいくはずさ。その瞬間がたまらないんだよ。論議を起こして欲しかった。そうして大地が浄化し、炎が再燃し、ゴミがリサイクルされるんだ。マークは音楽のマッサージ師だった。俺たちの血流が凝り固まっているところをほぐして、作業をスムーズにしてくれたんだ。バンドをベスト・ヴァージョンにしてくれたんだよ。彼はクイーンズのファンだったし、彼が求めるクイーンズ像があった。それを具現化させたのが『ヴィランズ』だったんだ」
――前作『…ライク・クロックワーク』にはエルトン・ジョンやデイヴ・グロール(フー・ファイターズ)、トレント・レズナー(ナイン・インチ・ネイルズ)、アレックス・ターナー(アークティック・モンキーズ)など多数のゲスト・アーティストが参加していましたが、『ヴィランズ』は基本的にバンド・オンリーで作られています。その違いは何故でしょうか?
「正直、『…ライク・クロックワーク』のときも豪華ゲスト陣を招いたという認識はなかったんだ。とても難しいアルバムだったし、気晴らしにいろんなミュージシャンに遊びに来てもらっただけだよ。アルバム作りの作業は楽しかったし、俺たちは地獄への道のりだって楽しむタイプだけど、地獄への道のりは地獄への道のりだからね。楽しみながらも疲れきっていたから、友人や知り合いにスタジオに遊びに来てもらったんだ。それで、せっかく来てくれたんだから、何かやってもらうことにしたんだ。そうして気がついたら12、3人がゲスト参加していたってわけだ。ただ、彼らがアルバムの音楽性に影響を与えたわけではなかったよ。100%クイーンズのアルバムだった」
――『ヴィランズ』の「新しいサウンド」をどう表現しますか?
「クイーンズの初期の作品にはダーティーなスプリング・リヴァーブがかかっていたし、ヴォーカルも輪郭がハッキリしなかった。ドラムスにもゆったりした空気感があったんだ。でもこのアルバムの1曲目“Feet Don’t Fail Me”でジョン・セアドアがバシッと叩き始めた瞬間、すべてが新鮮な刺激に包まれる。古いスタイルは吹っ飛んでいくんだ。そして新しいサウンドがリスナーの顔面にへばりつく。仮面のようにね。ドライなドラム・サウンド、クリアーな音像。ゴーグルをつけて水中に潜って、底にあるものがすべてハッキリ見えるようなんだ」
――“Feet Don’t Fail Me”はダンサブルなロックで、まさにクイーンズとマーク・ロンソンの合体を象徴する曲ではないでしょうか。
「うん、最高のドラム・ビートの曲だよ。オートマティックで身体が動くように仕組まれている曲だ。ただ実際のところ、俺は常に“踊れる”ロックをやってきたと思う。『…ライク・クロックワーク』は比較的ミッドテンポでフィーリング重視だったけど、『エラ・ヴルガリス』の“Misfit Love”なんてダンス出来るタイプの曲だろ?案外みんな気がつかないものなんだ。これまであったダンサブルな鍵のダイヤルがピッタリ合って、みんなが気付いてくれたっていう。そのことを決して悪くは思わないよ。『俺たちがダンサブルだと気付いてくれてありがとう!』と感謝しているよ」
――アルバムのタイトルを『ヴィランズ』=“悪党”としたのは何故でしょうか?
「俺にとってのロックンロールの“悪党”は、1956年ぐらいのジェリー・リー・ルイスなんだ。彼がTV番組に出演したときの映像を見たんだけど、彼の周囲を若者たちが熱に浮かされたみたいに取り囲んで、トランス状態で彼のことを見つめていた。まったくクレイジーだったよ。もし俺が彼らの父親だったら、ジェリーが本物の“悪党”に見えるだろうな。俺にとって『ヴィラン=悪党』とはそういう意味を持つんだ。たまにインタビューで『“悪党”とはドナルド・トランプのことか?』とか訊かれることがあるけど、あんな奴のことを題材にしたりしないよ。誰だってやっているクソみたいな題材だ。 ロックンロールは最高にダーティーで、同時に最高にピュアなものなんだ。ロックンロールはナイーヴで、暴動の引き金にもなる。そういうものだ。俺の仕事は、月曜を土曜みたいに思わせることだ。正午を午前零時みたいに感じさせて、尻の穴から虹をかけることだ。ロックンロールには、どこか純粋無垢な要素があるんだよ」
――ロックンロールの元祖“悪党”といえばエルヴィス・プレスリーですが、アルバムの最後を飾る“Villains of Circumstance”はエルヴィス・プレスリーの“Blue Moon”からインスピレーションを得たそうですね?
「うん、エルヴィス・ヴァージョンの“Blue Moon”、それからディーン・マーティンの“Memories Are Made Of This”かな。“Blue Moon”はいろんなアーティストが歌っているけど、エルヴィスのヴァージョンが一番『孤独』が表れているよ。若い頃のエルヴィスのやり場のない孤独が見事に表現されている。“Villains of Circumstance”もそんな孤独を描いた曲なんだ」
――一方で、“Un-Reborn Again”のノリもグラム・ロックっぽくて良いですね。
「T.レックスのバック・ヴォーカルが好きなんだよ。“Children Of The Revolution”とか、ファルセットが入って、ちょっと女性っぽかったりする。あの『ニャーー』というバック・ヴォーカルはクイーンズのキャラのひとつとなったと思う。意識はしていなかったけど、リズムのノリも似たタイプかも知れないね。この曲のリズムは好きだし、一日中だってやっていられるよ」
――“Head Like a Haunted House”は『エラ・ヴルガリス』の時期に書かれた曲だそうですが、ベーシックなパンク・フィーリングがあるのは、それが理由でしょうか?
「うーん、どうだろうな。この曲は『エラ・ヴルガリス』のために書いた曲ではないんだ。同時期に、別のアーティストがレコーディングすることを前提に書いた曲だった。でも当時は完成できなくて、もっと何かワイルドな要素が欲しくて、しばらくしまっておいたんだ。歌詞もまだなかった。『ヴィランズ』に入れるために完成させたけど、確かに『エラ・ヴルガリス』は怒りに満ちたアルバムだったし、この曲にもそんな感情が込められているね。走って行くリズムを追いかけていくような曲調が好きなんだ」
――クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジの初来日は2002年のフジ・ロック・フェスティバルでしたが、どんなことを覚えていますか?
「完璧に、海を隔てた異国に来たという印象だった。お客さんのノリがアメリカやヨーロッパと異なっていて興味深かったし、新鮮だったよ。すごく盛り上がっているかと思うとフッと静まりかえって、それからまた盛り上がるんだ。俺はステージ上で一瞬何が起こっているんだろう?と戸惑って、当時のベーシストだったニック・オリヴェリと顔を合わせて『ワーオ』と驚いていたよ。ただ、それは文化の違いというもので、おそらく日本の人々は、音楽をより真剣に聴いてくれるんだと思うね」
インタヴュー:山崎智之
リリース詳細

label: Matador / Beat Records
artist: Queens of the Stone Age
title: Villains
クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ『ヴィランズ』
cat no.: OLE11822
release date: 2017/08/25 FRI ON SALE
国内盤CD(スリーヴケース付):解説書/歌詞対訳封入
スペシャル・フォーマット:オリジナルTシャツ付きセット(S/M/L/XL)
01. Feet Don’t Fail Me
02. The Way You Used To Do
03. Domesticated Animals
04. Fortress
05. Head Like A Haunted House
06. Un-Reborn Again
07. Hideaway
08. The Evil Has Landed
09. Villains Of Circumstance
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.