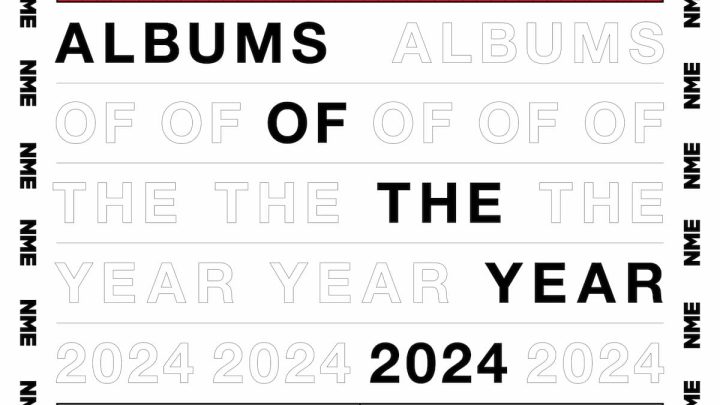Photo: APPLE CORPS
日本では9月22日から公開されたザ・ビートルズのドキュメンタリー映画『ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years』だが、公開を記念してアカデミー賞授賞歴のあるロン・ハワード監督にマッシュルーム・ヘア時代のザ・ビートルズについて訊くことができた。ロン・ハワード監督のインタヴューをお送りする。
──ザ・ビートルズは、この映画に収められている最後の年――つまり1966年の『リボルバー』とそれに続く実験的な作品の段階で冷めていったという通説が今日では一般的です。監督はこれに別の見方を提供したかったのですか?
「彼らはとても特別なバンドだと僕は考えてるんだ。僕はアップル社のチームから、この映画を制作するにあたってのヴィジョンを示されたんだ。ザ・ビートルズのキャリアのなかでも、ツアーをしていた期間に目を向けるように説明された。なかでも主な動機付けとなったのは、ジャイルズ・マーティン(プロデューサー、“5人目のビートルズ”ことジョージ・マーティンの息子)が使えると感じた新しい映像や、ブートレグ音源が発見されたという事実なんだ。だから、チームはライヴ体験やザ・ビートルズがいかに素晴らしかったか、いかにスタジアム・ロック・ツアーのパイオニアであるかについての映画を作ることにすごく関心があったんだよ」
──映画監督として、そのヴィジョンにどのような魅力を感じましたか?
「彼らに説明した通りに言えば、僕はそこに冒険とサバイバル、そして成長の物語を見始めていたんだ。そのすべてをシンプルな言葉で書き留めていった。もし僕がこの脚本を書いていれば、彼らがビートルマニアの時期──周りからのプレッシャーや社会の大混乱──をどのように切り抜けたかにとても興味を持っただろうね。そして、ビートルマニアの強烈さを理解しだすと、それは決して可愛らしいものではなく、リアルなドラマとして存在し始めた。だから、あの当時のツアーの日々を描くことが、映画的に、物語的に面白いと感じたんだ。その後に続く話は山のようにあるけど、彼らはこの部分も誰かに描いてほしいと思ってるはずだよ」
──それはあなたでしょうか?
「僕もとても興味があるけど、アップルがそれについて深く掘り下げてほしいと思っている部分なのかどうかは僕もわからないからね」

Photo: APPLE CORPS
──ライヴ演奏が悪くなっていくバンドを題材に映画を制作するのは、ある意味もどかしかったのではないでしょうか。リバプールやハンブルクで活動していた初期は、彼らは生き生きとしていました。しかし、最後のほうには彼らがライヴを気にかけていないことをあなたも感じとったと思います。
「僕らはマンチェスターやワシントンDCで初期に行った公演を新たに復元した映像をじっくりと観たんだ。マンチェスターの映像は35mmフィルムの素晴らしいもので、1964年にアメリカに行く前の彼らがいかに素晴らしかったかを示していた。熱狂的、まさに熱狂的だった。でも、そうだね、物事は移りゆくんだ。リンゴが日本で演奏しているすごいショットがあるんだけど、その彼はどう見たってかなり悲惨だったよ!」
──ザ・ビートルズの物語は数も多く、かなりの長さですが、約2時間でザ・ビートルズの物語をまとめるのは大きな挑戦でしたか?
「そうだね。例えば、本を読み始めたら──僕も全部を読み切ったわけじゃないんだけどね──彼らの物語についてはたくさんの興味深い視点があるのに気付くだろう。それを僕のレンズ、僕のフィルターを通して見たものがこれだ。筋金入りのファンたちは、すべてのディテールを盛り込んでほしいだろうが、その長さには至っていないかもしれない。しかし、音楽に対して本当の愛着と感謝、敬意を持っていて、ビートルマニアを知っているけど網羅はしていない人たち、つまり僕に近い人々のような、もう一つの重要な集団は、この映画を観る体験を求めてたんだよ。そして、淀みなく展開していく物語を望んでいたんだ。僕はこの点に関しては厳密にならなければいけなかったし、他の映画と同じく、難しい選択を迫られたよね」

Photo: APPLE CORPS
──あなたは子供の頃、ビートルマニアでしたか?
「いいや。僕はテレビ番組の『ザ・エド・サリヴァン・ショー』で彼らを観て、10歳の誕生日を迎える3月1日まであと20日だった当時、欲しいものをビートルズのウィッグとビートルズのブーツに決めたんだ。ビートルズのブーツは貰えなかったけど、ウィッグは手に入れた。それはすぐに隅っこの箱に仕舞われて、最終的には野球カードと一緒に捨てられたよ。ずっと好きではあったけど、楽曲はあまり購入していなかったね。彼らの音楽は好きだけど、惹かれていたのは彼らの物語なんだ」
──今ではスタジアム・ライヴは普通にありますが、ザ・ビートルズのスタジアム・ライヴはあまり素晴らしい体験だったとは言えそうにありません。映像に映っている観衆には怯えている人もいて、タンノイ(のスピーカー)からのサウンドは……。
「そう、タンノイにはちょっと……笑っちゃうね! あれはインパクトがあったし、それにザ・ビートルズがツアーをやめた数年後には、ザ・ローリング・ストーンズやザ・フー、イーグルスがスタジアム・ライヴを上手くやっていて、ノウハウを習得していった。ザ・ビートルズはそれを勝ち取るほど長く続けていないんだ。彼らは語りたがらないけどね! でも、あの警備と人だかりを見ると──そう、安全ではなかったんだよ」

Photo: APPLE CORPS
──ドキュメンタリーとしての前作『メイド・イン・アメリカ』では、ジェイ・Zを題材にしていました。ポールやリンゴとジェイ・Z、どちらがやりやすかったですか?
「どちらも素晴らしかったよ! ジェイ・Zには何度かインタヴューをさせてもらった。ポールはオープンな人だし、リンゴは面白くて、二人とも受け答えがうまいんだ。だって、彼らはリバプール独特の気の利いた言葉を返さずにはいられないからね。ポールは今も現役で、ツアーを行い、制作を続けている熟練のアーティストだけど、彼はザ・ビートルズのことを語る時、やっと少し楽しめるところまで来たんだよ。彼の過去の本当に重要な部分に、リラックスして対応できるようになったんだ。ザ・ビートルズについて語るという観点では、彼をこれまででも最も上手に語ってくれたんじゃないかな」
──ジョン・レノンとは、1970年代のシットコム『ハッピーデイズ』であなたがリッチー・カニンガムを演じていた時に会ったことがあるそうですね。
「そうなんだ。彼の息子がドラマのセットを見たり、ヘンリー(・ウィンクラー、フォンジー役)に会いたがったりした。ヘンリーもジョン・レノンにぜひ会いたいと思っていたそうだよ。私はもちろんジョン・レノンに対して憧れを抱いていたけど、熱狂的ファンというわけではなかったんだ。ヘンリーにとってはまさに神聖な体験だっただろうね。僕は挨拶を交わしただけで、10分とか15分くらいで終わったよ。その数年後にリンゴとキース・ムーンもドラマのセットを見学しに来たけど、慌ただしかったから、彼らがあの体験をあまり覚えているとは期待していないな!」
──『リボルバー』の発売から50周年となりました。なぜ今でも若い人がザ・ビートルズに関心があると思いますか?
「そうだな、いまだに音楽が素晴らしいからだろうね! 彼らはカリスマ的でセクシーで、そして見ていて興奮するんだ。それに彼らは以前に増して気持ちを代弁してくれているからね。今の若い人たちは5倍洗練されていると思うんだ。でも、ザ・ビートルズという人たちや、彼らが寄り添ってきたものには、社会的で、知的で、そして哲学的な要素というのが含まれている。彼らの歌は次の言葉に集約されるだろう。楽しくてノリがよく、夢中になるけど、目に映るものよりも、大体いつだって少し多くのものが潜んでいるんだ」
──例えば?
「そうだな、彼らは説明しないところがいいね。ポールがニューヨークからワシントンDCに電車で行くシーンがあるんだけど、そこで彼にインタヴューをしていて、彼は『アートじゃないんだ!』と言うんだ。『それでは何です?』と尋ねられた彼は『笑いだよ!』と答える。あの気取らない言動がマントラとなり、それを彼らは今も大切にしているんだ。素晴らしいとしか言えないね」
映画の詳細は以下の通り。
『ザ・ビートルズ〜EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years』
出演:ザ・ビートルズ 監督:ロン・ハワード
プロデューサー:ナイジェル・シンクレア、スコット・パスクッチ、ブライアン・グレイザー、ロン・ハワード
エグゼクティブプロデューサー:ジェフ・ジョーンズ、ジョナサン・クライド、マイケル・ローゼンバーグ、ガイ・イースト、ニコラス・フェラル、
マーク・モンロー、ポール・クラウダー
2016年/イギリス/英語/カラー/配給:KADOKAWA 提供:KADOKAWA、テレビ東京
協力:ユニバーサル ミュージック合同会社 後援:ブリティッシュ・カウンシル
更なる映画の詳細は以下のサイトで御確認ください。
http://thebeatles-eightdaysaweek.jp/
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.