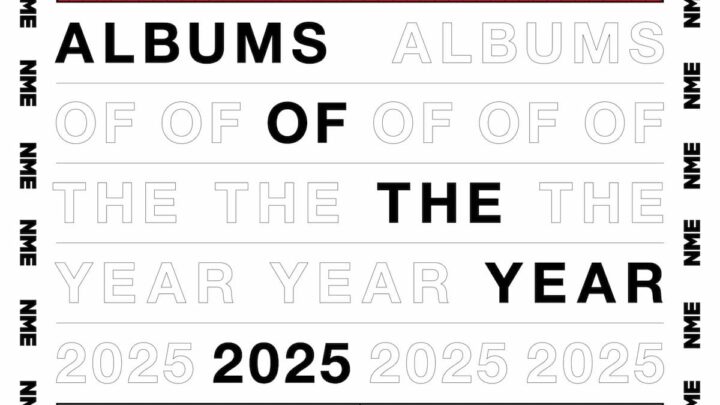05位 ヴルフペック(7/26 GREEN STAGE)

Photo: Taio Konishi
「めでたし、めでたし」で終わる御伽噺を聞いているかのような気分だった。山下達郎らが多くの観客を集めた2日目のGREEN STAGEを締めくくったのがヴルフペックだった。言うまでもなく全員が一流の音楽職人であり、バイプレイヤーも多く、セオ・カッツマンがドラムとヴォーカルを担当した“Animal Spirits”から始まったライヴは遊び心に溢れている。ジャック・ストラットンは法被姿でステージをあちこちへと動き回っている。その後もコリー・ウォンやベーシストのジョー・ダートをフィーチャーしたりといった感じで、各メンバーの持ち味が如何なく発揮されていく。“Tender Defender”ではアンワン・スタンリーがヴォーカルを務め、“Tokyo Night”では初日のFIELD OF HEAVENに出演していたマヤ・デライラが呼び込まれる形で登場する。そして“Matter of Time”だ。その音楽的遺産による桃源郷は2025年の現実などとは一切の接点を持たせることなく、中日のヘッドライナーを務め上げることになった。
04位 ハイム(7/27 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse
アラナが一番に入ってきて、デビュー作の“The Wire”からステージは始まったのだけど、コンセプトが最新作のモードなのは明らかだろう。ステージ上方には電光掲示板が設置され、「アイ・クイット・◯◯」というフレーズが表示されている。“Now I’m in It”に“My Song 5”と、曲に合わせて終わらせるテーマは変わっていき、最新作からの“Relationships”では大きな歓声が上がり、ハンドクラップが広がる。“The Steps”と“Everybody’s trying to figure me out”、“Gasoline”ではダニエル・ハイム自らがドラムを担当して、“Blood on the street”ではドラムのビートに合わせてダニエルが歩を進め、観客を煽ってみせる。ここからライヴは終盤に突入して“Want You Back”、“Summer Girl”といったキャリアの節目を飾った楽曲が続き、最後は最新作からの“Down to be wrong”だったのだけど、この日のライヴを観て感じたのは詰まるところハイムとはこの3人なのであり、そのステージは多くの観客を集めていた。
03位 バリー・キャント・スウィム(7/26 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse
リリースされたばかりの最新作と同じく重厚な“The Person You’d Like to Be”で始まったのだが、UKのエレクトロニック・アクトはこういう導入が本当にうまい。これから展開されるサウンドのスケールと手触りが呈示され、そこから一気に“About to Begin”、“Dance of the Crab”を挟んで“Kimbara”と畳み掛けていく。キャリア初のバンドセットということだったが、じゃあ他アクトと較べて目新しいものがあったかというと、そうでもない。しかし、その圧倒的な完成度たるやすさまじい。“Blackpool Boulevard”でピアノの演奏によってさらに懐を見せたところで、“Like It’s Part of the Dance”から“Kimpton”へとスムーズにギアを上げていく。後半から終盤にかけては観客の数も膨らみ、名曲“How It Feels”が披露される頃にはすっかりバリー・キャント・スウィムの術中の中だ。“Deadbeat Gospel”もライヴならではのアンセムとしての可能性が引き出されていて、伸び盛りのアーティストならではのステージだった。
02位 ロイエル・オーティス(7/27 WHITE STAGE)

Photo: Masanori Naruse
オーセンティックなギター・ポップをやるバンドなのにベーシストがいないのが面白い。そう思いながら“Going Kokomo”から始まったライヴを観ていると、曲目などを表示するバックドロップの映像を含め、いろんなものが統一された世界観を持っているのに気付かされる。キーカラーはショッキング・ピンクで、上部のヴィジョンに表示されるライヴ映像はすべてモノクロで、その上には一貫してショッキング・ピンクのロゴとアイコンが表示されている。その上で自由なのはロイエルとオーティスの二人だ。乾杯してみたり、「ファック・ユー」と言ってみたり、セットリストとしては“Kool Aid”、“moody”、“car”、“Fried Rice”など、珠玉の楽曲が次々と演奏されていったのだけど、この無垢なメロディーを2025年に鳴らすために様々な意匠が徹底されている。シンセ・ポップの軽やかさを持った“Murder on the Dancefloor”とクランベリーズの“Linger”のカヴァーも素晴らしく、新たな才能の台頭を感じさせてくれた。
01位 フレッド・アゲイン(7/25 GREEN STAGE)

Photo: Masanori Naruse
ステージ裏側を通って、観客の前に辿り着くまでが手持ちのカメラでヴィジョンに映し出される。そのままピアノの弾き語りに入って、“Kyle (i found you)”を経て、今回が初めての日本公演で、それがフジロックで、なぜ『アクチュアル・ライフ』という作品を作ったのかが端的に字幕で説明される。機材の問題があって、開演時間が遅れることになったが、そこからは圧巻のパフォーマンスだった。サブ・ステージでサンプラーを叩きまくる“Jungle”やギターを使った“Turn On the Lights again..”など肉体を駆使したライヴ性と、映像も含めてテクノロジーを使ってリアルタイムで実現していく同期の部分、それがコントラストを見せる形で同居していく。後半は『アクチュアル・ライフ』からの楽曲で、“Angie (i’ve been lost)”の前に感謝を伝えながら「本当に怖かったんだ」と語っていたフレッド・アゲインだが、そのステージで見せてくれたのはラップトップで音楽を作るのが主流になった時代における本質的なライヴのアプローチだった。
※公開後、記事を修正しました。
Copyright © 2026 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.
関連タグ


_2563 [Analog]](https://m.media-amazon.com/images/I/415lxbfrdVL._AC_SL1000_.jpg)