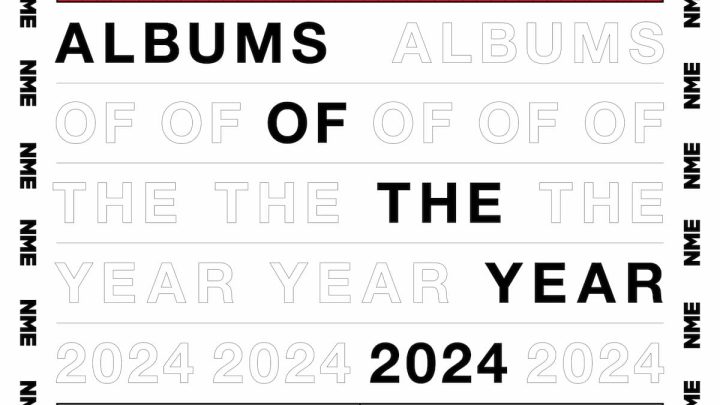Photo: JORDAN HUGHES/NME
4枚のアルバムを残し、数え切れないほどのギグを行なったこの14年間を終え、ザ・マッカビーズが解散を発表した。これを機に彼らのベスト・ソング10曲を振り返ろう。
10位 “Marks To Prove It”
強烈でめまいのするようなサウンドと深くて感傷的な歌詞(「夏の間に/人生が変わった/人生についていくためにすべてが変わった/複雑でこんがらがりすぎていて/誰にも話すことなんかできない」)でもって、”Marks To Prove It” は、この南ロンドナーたちのラスト・アルバムからの爽快なリード・シングルとなった。大興奮のギター・サウンドとサム・ドイルの連打するドラムでイントロからクライマックスを迎える。時速1200キロを超える抗えない楽曲だ。
9位 “Toothpaste Kisses”
2007年のデビューアルバム『カラー・イット・イン』からの4枚目のシングルであるこの曲は、グループのいつも以上に柔らかい部分が出た無邪気な子守唄だ。憂鬱に浸りながら、すべてがうまくいかなくなってしまう前の彼と名もなき恋人との幸福だった日々への寄る辺のない追憶である。ヴォーカルのオーランド・ウィークスは「僕と一緒にいてくれ。君と一緒にいるから」と必死に嘆願する。しかし、その甲斐もなく我々はただ大きな悲哀と共に取り残されてしまう。
8位 Grew Up At Midnight
“Grew up At Midnight” は、2012年のマーキュリー・プライズにノミネートされたアルバム『ギブン・トゥ・ザ・ワイルド』の素晴らしい締めくくりの曲であるとともに、多くのザ・マッカビーズの曲のように10代のノスタルジアに満たされている。「そのとき僕たちは少年だった/頭からつま先までびっしょりと濡れていたんだ」とオーランド・ウィークスは歌う。そっと優しく始まり、曲は聖歌のような高みに向かっていく。そして、ノイジーなギター、連打するドラム、ストリングスから成るスケールの大きいクライマックスに辿り着く。そして、無音。そこで曲は途切れ、アルバムはここに結末を迎える。議論の余地はあるかもしれないが、彼らの武器庫にこれほどフェスティバル用のセットリストを締めくくるのにふさわしい楽曲はないだろう。
7位 “One Hand Holding”
マーカス・ドラヴスによりプロデュースされた2009年リリースのセカンド・アルバム『ウォール・オブ・アームズ』からの最高の楽曲の一つである”One Hand Holding”は、歯を食いしばるほど高まっていく狂乱状態の曲である。オーランド・ウィークスの情熱的な声は、弱まることのなく繰り返される「どうして君は死ぬ前に殺さないの」という叫びとともに大きくなっていく。そして、共に叫びたくなるようなコーラスを迎えて、どうして長年”One Hand Holding”が最もファンに愛されてきた楽曲の一つであったか分かるだろう。ライヴではずば抜けて楽しめる楽曲でもある。
6位 No Kind Words
2009年発表の”No Kind Words”は、バンドにとって本物の出発となった曲だ。若き楽観思想を抜け出し、ファースト・アルバム『カラー・イット・イン』のレゴについての曲でもなく、影が入り込んだものに取って代わっている。挑発的なベースラインにのって「言うべき優しい言葉が見つからないなら/それ以上は何も言うべきではない」とオーランド・ウィークスが歌うとき、彼の声は穏やかで超然としている。蛇足だが、この曲のサウンドは、素晴らしいアルバムである『ウォール・オブ・アームズ』の中で最も優れたものであると同時に、グループのすべてのアルバムを通してもそうであると言える。
5. First Love
多くのザ・マッカビーズのファンにとって、失恋についての楽曲“First Love”は、まさに駆け出しのインディバンドだった彼らの魅力に惚れ込んでしまうきっかけとなった楽曲だろう。歌詞は、若者の愛の不安や渇望を完璧にとらえ、そしてオーランド・ウィークスは「完璧なものなどない/そして、僕はそうすることを望んでいるけど/でもそうはしない/なぜなら完璧なものなどないから/だから、なんとかしないといけない」と感傷的に歌う。僕は相手としてふさわしいだろうか? それに値するものなのだろうか? “First Love”には普遍的なパラノイアがあり、それは陽気に、そして猛烈なスピードで歌われている。
4位 “Pelican”
ザ・マッカビーズにとって音楽ジャンルをまたがって最大のヒットとなった“Pelican”は、今日ではフェスでの大合唱となることが運命付けられていたように思える。明らかに広い会場を満たすように作られた“Pelican”は、天下を取ったアルバム『ギーヴン・トゥ・ザ・ワイルド』から最初にシングル・カットされ、これまで進化を続けてきたバンドの考えを陽気に表明したものである。“Pelican”はオーランド・ウィークスの美しい歌声と、素早く掻き鳴らされるギター、そして熱狂的な速さによってリスナーを息切らせるが、でも、その左右からジャブを繰り出すようなスタッカートに彩られた楽曲は、フェスティバル会場がベスト・ライヴとして記憶することになる、そのオープニングにすぎないのだ。ライヴにおいて、この曲はモンスターだ。“Pelican”は、ザ・マッカビーズへの胸の高鳴りを当然のものだと感じさせ、ザ・マッカビーズが、無邪気な発達段階の数年間から、より彼らにふさわしいものと進化することを示すシグナルだったのだ。
3位 “Spit It Out”
4作目のアルバム『マーク・トゥ・プルーヴ・イット』収録の中でも傑出した楽曲、“Spit It Out”は胎位で体を丸めて泣くような異例のオープニングで幕を開けるバラードで、オーランド・ウィークスによれば「忘れられた英雄たちと、クジラがテムズ川を泳ぎ渡ったという7、8年前の奇妙な瞬間を繋げようとしてみたもの」だという。霧のような雰囲気のなか曲の幕を開けるピアノは、シャーロット・ブロンテの小説『ジェーン・エア』を映画化した時のサウンドトラックのオープニングのようで、楽曲は激しく焼け付くような旋律と怒りほとばしるヴォーカルへと辿り着き、「嵐が来て木の枝を引き裂く/溺れているクジラのように/そして、そういう思いを巡らせて僕らは皆ひざまずく」と吠えてみせる。臆病なインディの原点から、ザ・マッカビーズはどんなに遠くへとやってきたのだろうということを、この曲の激しさや恐れ知らずさは思い知らさせてくれる。
2位 Latchmere
水の波を引き起こすウェーヴマシンに着想を得た楽曲であり、そして、まさに“Latchmere”という贅沢なインディの波の中に巻き込まれずにいるのは、ほぼ不可能なことなのだ。ザ・マッカビーズのファースト・アルバム『カラー・イット・イン』に収録の本曲は、最近のザ・マッカビーズのような細密に洗練された楽曲ではないかもしれないが、この曲は彼らの楽曲の根底に今なお潜んでいるエネルギーと熱狂の好例であろう。速くて、楽しい。ザ・マッカビーズの色褪せない魅力を持った名曲だ。
1位 Forever I’ve Known
アルバム『ギーヴン・トゥ・ザ・ワイルド』収録の“Forever I’ve Known”がザ・マッカビーズの最高の到達点であるといえよう。オーランド・ウィークスの歌声はとても優しく繊細で、喪失感を綴った歌詞が、ほとんど囁くように耳に入ってくる。「頭の中の君では満たされないんだ」とオーランドは震えるように歌う。引っ掻くようなギターの音が広がる曲は今にもすすり泣くように4分を迎え、オーランドは「ずっとわかっていた/何も永遠には残らないのだと」と認めてみせる。しかし、次の瞬間にはリスナーは耳を覆うような轟音の海へと放り込まれて、曲は幕を閉じることになる。この“Forever I’ve Known”こそ、マッカビーズの奏でた最も素晴らしい楽曲である。
Copyright © 2025 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.
関連タグ