- Rating
- ★★★★★★★★☆☆
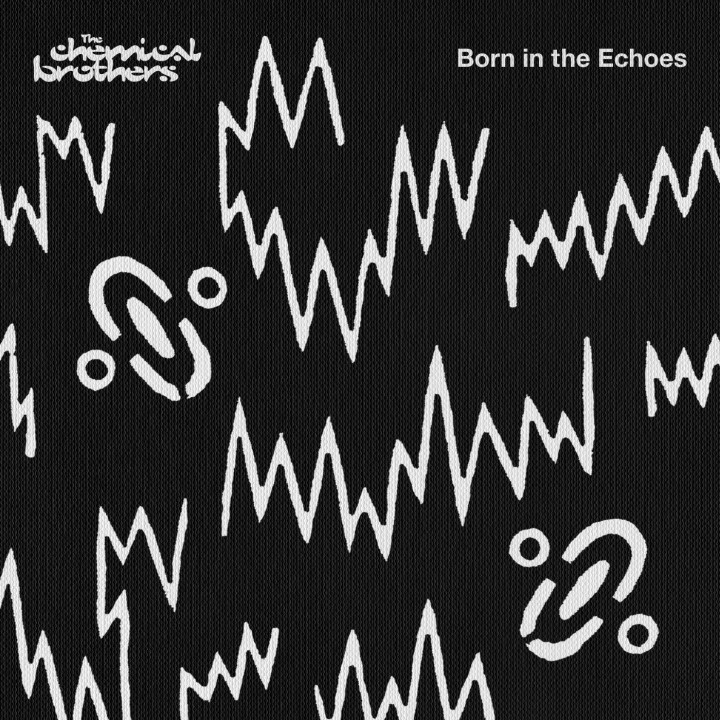 異論はあるだろうが、ケミカル・ブラザーズはダンス・ミュージックの歴史において最も重要なグループの一つだ。トム・ローランドとエド・サイモンズによる唯一無二の1997年作品『ディグ・ユア・オウン・ホール』は、ダンス・ミュージックの領域にロックとサイケデリアを導入してみせた。また、初期の音源では、ノエル・ギャラガーとのコラボレーションによる“Setting Sun”(1997)や “Let Forever Be”(1999)のように、インディ・ヴォーカリストにビッグ・ビートをかけ合わせてみせる先駆者でもあった。
異論はあるだろうが、ケミカル・ブラザーズはダンス・ミュージックの歴史において最も重要なグループの一つだ。トム・ローランドとエド・サイモンズによる唯一無二の1997年作品『ディグ・ユア・オウン・ホール』は、ダンス・ミュージックの領域にロックとサイケデリアを導入してみせた。また、初期の音源では、ノエル・ギャラガーとのコラボレーションによる“Setting Sun”(1997)や “Let Forever Be”(1999)のように、インディ・ヴォーカリストにビッグ・ビートをかけ合わせてみせる先駆者でもあった。
しかし、2000年代に入ると、彼らはマンネリという危機に直面するようになる。2002年の『カム・ウィズ・アス』から2007年リリースの『ウィー・アー・ザ・ナイト』まで、この時期のアルバムは驚きのない仕上がりで、ちっとも面白くない。ケリー・オケレケ(“Believe”)やリチャード・アシュクロフト(“The Test”)といったゲスト・シンガーに、分かりやすいビート。盛り上がりという点で楽しめはするものの、初期のような革新性はそこにはなかった。そのためか、2010年リリースの『ファーザー』はゲスト・シンガーを呼ばずに制作され、より深くダークで神秘的な仕上がりとなっており、実際、かなり楽しめる一枚となった。
彼らにとって8枚目となるスタジオ・アルバム『ボーン・イン・ザ・エコーズ』は、『ファーザー』以降初となる作品で、ゲスト・シンガーが戻ってきている。ただし、楽曲の大半で主導権を握っているのはケミカル・ブラザーズで、ゲスト・シンガーの歌声は作品が本来持つ力を補助する役割に留まっている。
セイント・ヴィンセントが参加した“Under Neon Lights”を例にとってみても、「そして彼女は自殺へと向かう/ネオン・ライトに囲まれて」という歌詞が淡々と歌われており、最終的にセイント・ヴィンセントの声は機械的な音の断片となり、スタッター・エフェクトがミックス音源に施され、車の盗難防止警報音が壊れたような音になっている。ロンドンのシンガー、アリ・ラヴ(『ウィー・アー・ザ・ナイト』のシングル“Do It Again”にも参加)を迎えた“EML Ritual”でも二人は似たようなトリックを使っており、ピッチ・シフターをかけられてレイヤー化されたアリ・ラヴの声が、正気を失う様を描写する歌詞(「どうしたらいいか分からない/気が狂いそうだ」)のエコーと共に、深い夜にとらわれてしまったような不安定さを作り出している。
前述の2曲は、『ファーザー』での物憂げなエレクトロニカとダークなサイケデリック・ロックの浮遊感がうまく融合した曲だ。しかし、このアルバムの真のハイライトは、これまでケミカル・ブラザーズが作ってきたことのないタイプの曲にある。彼らは未知の領域をさらに奥へと進み、初期のピンク・フロイドと、ミニマル・テクノを代表する変わり者リカルド・ヴィラロボスと、そして1968年にロンドンで誕生した実験的なエレクトロニック・グループであるホワイト・ノイズという、これらの中間に位置するような音を作り出したのだ。
“I’ll See You There”は、ライヴのサウンドを再現した(とてもファンキーな)電子ドラムにフェイザーをかけ、激しいシンセサイザーを合わせた曲で、ビートルズによるサイケデリック・ロックの永遠の金字塔“Tomorrow Never Knows”にこれまでになく近づくことに成功した。その結果、テーム・インパラのジャム・セッションをケミカル・ブラザーズのマザーボードを通したようなサウンドが実現している。“Taste Of Honey”もさらに変わった曲で、あまり売れなかった1968年の7インチ・レコードの中から発見した、目立たない宝石のような曲だ。単調で変化なく続くサイケデリック・ポップに、悩ましいヴァイオリンの音色とハチの羽音がアクセントとなっている。一方、“Born In The Echoes”(feat. ケイト・ル・ボン)はブロードキャストの“Pendulum”を新しいシンセサイザーで誰かが爆音で練習するような、そんなことを思い起こさせる。
後半のエレクトロニックなサイケデリック・ミュージックの旅は、非常にすばらしい“Radiate”でクライマックスを迎える。“Radiate”は、まるでダフト・パンクが恋人たちのドロドロの別れを題材にしたような曲で、すべてが歪んだ電子音、不安定なオーケストレーション、そしてトム・ローランドの心のこもった歌詞(「これは何/僕に見えるもの?/ただ降り注ぐ/僕への君の愛」)をまとめた、容赦なく心に響くデジタルな失恋ソングだ。この曲は最高の締めくくりになれたはずだが、実際には退屈な“Wide Open”にアルバムの最後の座を譲っている。沸き立つようなハウス・ビートにベックのメランコリーなヴォーカルが合わさる“Wide Open”は、アルバムに溢れるダークな雰囲気からは外れている。また、“Go”(Q−ティップが参加)も同様に浮いている曲で、小さくまとまったアシッド・ハウスのサビと大げさなベースが、嘘くさい応援メッセージ調のひどいコーラス(「休んでいる時間はない/ただベストをつくすんだ」)によって台無しになっている。
しかし、ありがたいことに、そんな点もさほど気にならない。『ボーン・イン・ザ・エコーズ』は、ケミカル・ブラザーズにおける後期ルネサンスを告げた『ファーザー』をさらにダークで複雑にした、大胆で革新的な一枚だ。(ベン・カーデュー)
Copyright © 2024 NME Networks Media Limited. NME is a registered trademark of NME Networks Media Limited being used under licence.














